興銀事件

目次
債権者側の事情も踏まえ、社会通念に従って総合的に判断
概要
解除条件付債権放棄をした事業年度での貸倒損失の損金算入は、債務者の資産状況だけでなく、債権者側の事情も踏まえ判断すべきであるとして、貸倒損失の損金算入が認められた事案(日本興業銀行事件)。
相関図
事案の概要
■納税者である日本興業銀行は、B者に対して約3,760億円の貸付債権を有していた。
■納税者は平成8年3月に当該債権を放棄し、平成8年3月期の事業年度の法人税について、本件債権相当額を損金に算入して確定申告を行った。
■これに対して、課税庁は、当該債権相当額の損金算入を否認し、法人税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定を行った。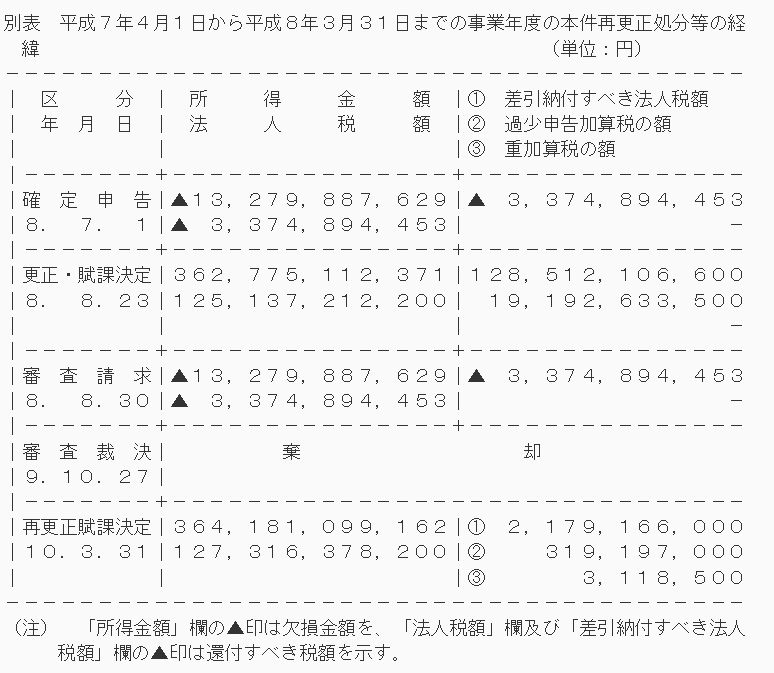
概要
- ■概要
- ■納税者(旧日本興業銀行)が解除条件付で住宅金融専門会社向けの債権を放棄し、債権放棄損を当年度の損金として申告したところ、課税庁がそれを否認したことから生じた訴訟事件。
■納税者は、新事業計画の破綻により多額の債権について回収不能な状況に陥っており、政治問題化し、関係者から責任を追及され、より大きな損失を避けるためには債権放棄しかないと判断、株主代表訴訟リスクを避けるため、解除条件付き債権放棄を実行し、法人税の申告において貸倒損失として損金算入した。課税庁は損金算入できないとして更正処分をした。
■地裁は、納税者の主張を認めたが、高裁は、判断を覆し、課税庁の主張を認めた。ところが、最高裁において、債務者側の状況だけでなく、債権者側の事情、経済的環境等も踏まえ、社会通念に従って総合的に判断すべきであり、当時の状況では債権者(銀行)の債権の全額が回収不能であることは客観的に明らかであるとし、これは債権放棄が解除条件付きでされたことによって左右されるものではないから納税者の請求を認容した第1審判決が正当であり、課税庁の控訴を棄却すべきであるとして判断し、納税者勝訴となった。
■判決の結果、約1,500億円の課税処分が取り消され、その額が返還されるとともに、還付加算金として、約1,000億円が納税者に支払われ、地方税についても約700億円が納税者に支払われた。金額の巨額さだけではなく、「債務者側の事情のみならず、債権回収に必要な労力、債権額と取り立て費用との比較衡量、債権回収を強行することによって生ずる軋轢などによる経営的損失等といった債権者側の事情、経済的環境等も踏まえ、社会通念に従って総合的に判断されるべきものである」と、「社会通念」の重要性を示した租税史上大変重要な判例である。
■本件は、一審は納税者側が全面勝訴、二審は、課税庁側が逆手勝訴、そして最高裁では、再び納税者側が再逆転全面勝訴という展開で、社会の注目を集めた。 - ■裁判所情報
- 東京地方裁判所 平成13年3月2日判決(藤山雅行裁判長)(全部取り消し)(納税者勝訴)(被告控訴)
東京高等裁判所 平成14年3月14日判決(村上敬一裁判長)(原判決取消し・被控訴人の請求棄却)(被控訴人上告)
最高裁判所 平成16年12月24日判決(滝井繁男裁判長)(破棄自判・被上告人の控訴棄却)(納税者勝訴)(確定)
争点
判決
東京地方裁判所
→納税者勝訴
解除条件付き債権放棄による貸倒損失の損金算入は、当時の状況から回収不能な状態にあり、解除条件付きでも債権放棄の効力がある。
東京高等裁判所
→納税者敗訴
解除条件付き債権放棄をした事業年度での貸倒損失の損金算入は、(期末に全額回収不能とはいえず、条件不成就が確定した事業年度に損金算入すべきだから)認められない。
最高裁判所
→納税者勝訴(確定)
解除条件付き債権放棄をした事業年度での貸倒損失の損金算入は、債務者の資産状況だけでなく債権者側の事情も踏まえ判断すべきである。
解除条件付債権と農協系統金融機関
解除条件付債権放棄
例えば、「お金をあげるが、就職に失敗したら返せ」というように、一定条件の成就により法律効果を消滅させることを解除条件付法律行為という(民法127条②)。解除条件付債権放棄もその1つである。
興銀事件では、興銀は住専子会社のJHL社(日本ハウジングローン株式会社)に対し、「平成8年12月末までに政府の住専処理法が成立しないこと」を解除条件に、債権放棄を行った。
本件では、このように、債権放棄に解除条件(条件が成就したら、債権放棄の効力を失わせるという条件)が付されており、その不成就が確定しなければ、債権放棄の効力も確定的なものとならないのではないか、という問題もあったため、課税庁が処分に踏み切り、控訴審も最高裁と反対の結論に至った。
しかし、最高裁は、放棄に至った経緯を詳細に分析し、放棄時には、債権全額の回収が社会通念上不可能となっていたと判断した。
本判決により、回収不能の判断をかなり柔軟に行うことができるようになった。その意味で、本判決が実務に与えた影響は非常に大きかったと言われる。当事案により、納税者を取り巻く状況を踏まえた妥当な貸し倒れ処理が可能になった。
(参考)
「就職出来たら車をあげる」というように、一定条件が成就したときに効果を生じさせることを、停止条件付法律行為という(民法127条①)。
系統
本事案で「系統」と呼ばれる金融機関は、農協系統金融機関を指す。
Q金庫都道府県単位で組織されているR農業協同組合連合会、並びに都道府県単位で組織されているS農業協同組合連合会、及びT共済農業協同組合連合会(S農業協同組合連合会と併せて「T農業協同組合連合会等」)、以上をまとめて、「系統」という。
キーワード
■キーワード
回収不能、貸倒損失、債権放棄意思表示、訴えの交換的変更、条件付債権、貸倒損失、藤山判決、無理からぬ事情
■重要概念
社会通念
東京地裁/両者の主張
納税者の主張
“Bは、昭和51年にいわゆる住専の一社として、原告、E銀行及び本件証券母体三社を設立母体として設立されたものである。Bをはじめとした住専は、住宅ローンの供給という国策に基づき設立され、ノンバンクとしては異例の大蔵省直轄の準金融機関とされる等、設立当初から大蔵省の強い関与の下にあった。
原告は、Bの設立母体ということのみならず、資本、資金及び人的関係のあらゆる観点において極めて密接な関係にあり、その経営に深く関与してきた。そのため、B設立の翌年から開始された系統によるB向けの融資に当たっては、原告がこれを保証することなった。そして、かかる保証はその後大蔵省と農林水産省の行政指導によって集合債権譲渡担保方式に切り替えられ、原告はその協定幹事行として、自己及び系統をはじめとした他の債権者のために担保の管理をなすべき立場に就いた。こうした経緯からも、系統はBへの与信は原告の信用に支えられたものだとして、住専向け貸付をインターバンク取引と位置付けて、その取引を拡大していった。”
“しかし、昭和50年代後半に至り、都市銀行(以下「都銀」という。)等の住宅ローン分野の蚕食が始まり、さらに平成3年から4年にかけて、いわゆるバブル経済の崩壊による事業者向けローンの不良化等により住専の財務・経営状態が急激に悪化した。これをうけ、住専を直轄する大蔵省は各住専の財務状況の実態を把握するべく第一次立入調査を行うとともに、各住専の母体行に対して住専の再建計画の策定を要請するに至った。
かかる大蔵省の要請をうけて、Bの責任母体行である原告は、平成4年5月、Bの事業計画(以下「第一次再建計画」という。)を立案し、系統らに対して「融資残高の維持」を要請した。これに対して、系統は自らの債権保全を確実にするべく、融資残高の維持に応じる条件として、①原告が母体支援を文書により表明すること、及び②系統債権の優先弁済性を確保するために系統債権を全額有担保化することを要求してきた。
当時、系統はBの最大の貸し手であり、系統が残高維持に応じない場合にはBの事業はたちまち行き詰まってしまうことから、原告は、かかる系統の要請に応じて、①母体が責任を以て支援していく旨を直接口頭で表明した上で、B名義でその旨を明らかにしたQ金庫宛の「書簡」等を差し入れるとともに、②原告のBに対する有担保の長期証書貸付を無担保の短期手形貸付(約1560億円)に振り替えることで、系統のBに対する無担保貸付を有担保貸付に振り替えることとした。
“前述のように、原告がBの第一次再建計画を策定し、その際に母体として支援することを明確に表明し、系統債権の全額を有担保化したことによって系統の融資残高は維持されたものの、地価の下落がなおも続いたため、担保不動産の価値の目減りによる住専の財務状況の悪化は一層顕著となった。
そこで、大蔵省は、自らが「直轄」する住専から金融不安を招く訳にはいかないという「政策的判断」から、各住専及びその母体行に対して、関係金融機関による金利減免を軸とする第二次再建計画を立案するように要請した。この要請に対して、当初原告は金利減免だけでは問題の先送りにしかならず、抜本的解決策を採るべきであると提言した。
しかし、大蔵省銀行局の戊審議官(以下「戊審議官」という。)は「再建の作文を作って勧進帳的に関所を越えたい」とまで述べ、大蔵省自らが問題の先送りでしかないことを認めつつ、敢えて「政策的判断」として再建策の体裁を整えることを求めてきたことから、原告は最終的にはかかる再建策の実現可能性が極めて乏しいことを認識しつつも、大蔵省からの要請に従い、Bの新事業計画を策定することになった。”
“このとき、大蔵省が、系統が金利軽減を受け入れる「条件」として提示してきたのが、①整理の段階における系統への優先弁済の確保と②母体責任を明確にした文書の提出であった。原告は、①系統への優先弁済を認めることは、既に第一次再建計画の策定に当たってBを支援していくことを系統に対して明確に表明した上で残高維持を求めた経緯があったことから、やむを得ないものとして同意した。そして、かかる弁済順序は、大蔵省の指導に従い、最終的に新事業計画において「高利優先弁済」という形で「金利の差」を以て明確に具体化されることとなった。”
“つまり、Bの事業資金の貸し手の中では、4.5%と最も高利の債権とされた「系統債権」が「最優先」であり、金利0%とされた「母体行債権」が「最劣後」となることが、定められるに至ったのである。また、②母体責任を明確にした文書の差入れについても、大蔵省が極めて強い調子で、正式の社印でなくても構わないとまで述べてきたことから、結局、原告はこれに応じることとし、母体五社間で確認の上、大蔵省に「Bの再建に責任を持つ」旨の念書を差し入れることとなった。このように、大蔵省が系統債権の優先弁済と母体責任を明確にした文書の差入れにこだわったのは、大蔵省と原告との面談の前日である平成5年2月3日に大蔵省と農林水産省との間で締結された「大蔵・農水覚書」において、これらが新事業計画による金利軽減に系統が応じるための条件とされていたからである。”
“このような経緯を経て、Bの「新事業計画」は、平成5年5月に作成され、原告及びBの担当者が関係者に持参の上説明し、平成5年12月27日を以て関係者の全てが書面を以て新事業計画に「同意」することとなった。また、これによって、担保協定に基づく集合債権譲渡担保の行使順序においても母体行債権が最劣後に置かれることになった。”
“前述のように、新事業計画について関係者の合意が成立し、新事業計画に基づくBに対する支援が開始されたものの、その後も経済環境は悪化の一途をたどり、平成7年8月に実施された住専各社に対する大蔵省の第二次立入調査によって、住専の破綻が完全に明らかとなり、弁済順序において最劣後に置かれる本件債権がもはや回収不能であることが誰の目にも明らかとなった。
この結果をうけて、与党金融・証券プロジェクトチーム(以下「与党PT」という。)が「住専問題についての勧告」を発表し、住専問題の早期解決を求めたのに応じて、原告も平成7年9月22日にはBの母体各社を招集して同社を整理する方針を確認し、大蔵省に報告した。さらに、与党PTは、各住専の処理状況を確認するために各住専の母体に対するヒアリングを開始したが、特に、住専の中でも最大手であるBの責任母体行であった原告に対しては、与党PTの〈B〉座長から直接に、原告が先頭を切って模範を示すようにとの発言がなされるなど、住専問題解決において主導的な役割を果たすことが強く期待されていた。”
“他方、平成7年9月以降、与党PTの勧告に従って、母体行と系統による系統協議が始まったが、その際、当事者間では、Bを整理する段階でも母体行債権が最劣後に置かれ、系統債権が最優先とされることについては何らの齟齬もなかった。しかしながら、第二次立入調査によって、新事業計画における「合意」に従って母体行債権(3兆5000億円)のみならず一般行債権(3兆8000億円)の全額(合計7兆3000億円)を劣後させてもなお、系統債権に全住専合計で約2000億円もの元本ロスが生じることが確認されたため、系統協議では、新事業計画時には意識もされず従って「合意」されていなかった系統債権に生じる元本ロスを、誰がどのように負担するかという点を巡って協議が進められることとなった。”
そこで、大蔵省は農林水産省との協議に入った。大蔵省と農林水産省は、母体行の負担を債権全額までに留める一方、系統の元本ロス負担を最小化するべく、住専に生じる約7兆5000億円の損失のうち第Ⅳ分類に該当する約6兆3000億円の損失を「一次ロス」として切り分け、かかる「一次ロス」の大部分を母体行債権全額の放棄によって処理する大蔵省案を、予算内示も押し迫った同年12月17日に原告に提示してきた。原告は、この母体行債権の全額放棄について同意することを大蔵省に伝えた。系統もこれに「合意」し、ここにおいてより明確な形で「母体行債権の最劣後性」を前提とした母体行債権の全額放棄を基底とする「一次ロス」負担についての全ての「関係者間の合意」が成立したのである。そして、それを受けて平成7年12月19日深夜に、本件閣議決定がなされ、かかる合意が公的にも確認されることとなった。
“このように、系統協議の眼目はこれまでの合意においては定められなかった系統の元本ロス負担の問題であったが、これについて母体行と系統との議論は平行線をたどった。しかしながら、住専問題は、その損失額の大きさ及び大蔵省直轄の準金融機関の処理として、内外から注目を集めており、金融システムの秩序維持のためには年内に処理方針を固めることが必須であった。そこで、平成7年11月29日に、大蔵省は母体行の役員を招集して、大蔵省と農林水産省が住専処理案の取りまとめのあっせん・仲介を行うことを伝えた。このあっせんの一環として大蔵省は母体行に対するヒアリングを行った。原告の〈U〉正雄副頭取は、その際、新事業計画に基づく母体行債権全額までの負担はやむを得ないが、かかる負担が株式会社として負担し得る限界であることを明確に伝え、大蔵省もかかる原告の意向等を受けて農林水産省との協議に入った。”
“大蔵省と農林水産省は、母体行の負担を債権全額までに留める一方、系統の元本ロス負担を最小化するべく、住専に生じる約7兆5
“このように、本件閣議決定により「一次ロス」の処理が固まったことから、大蔵省は、残る第Ⅲ分類債権から生ずる損失見込額一兆2000億円の「二次ロス」の処理について、農林水産省とも連絡をとりながら原告を含めた各金融機関とさらに協議を重ねた。そして、予算委員会開催(平成8年1月26日)を目前に控えた平成8年1月24日には、大蔵省及び農水省を通じて関係者に対して「二次ロス」処理の最終案が提示された。
かかる処理案における議論のポイントは、本件閣議決定で確認された「一次ロス」処理を当然の前提として、「二次ロス」をいかに処理するかという点であった。当然のことであるが、平成8年1月以降の協議においてはもはや「一次ロス」をどのように処理すべきかについては全く議論の対象となっていなかった。このことからもまた、既に平成8年1月の段階においては、母体行債権の最劣後性を前提とした母体行債権の全額放棄が「合意」されており、もはや動かしようのないものとなっていたことが明らかである。そして、最終的には、当該「二次ロス」については、系統も含めた〈C〉の金融機関が拠出した基金の運用益等によって処理されることとなり、原告をはじめとした金融機関は系統も含めこれに同意し、右合意に基づき本件閣議了解がなされるに至った。ここにおいて二次ロス部分まで含めた住専処理スキームが「関係者の合意」の上で完全に固まった。”
“原告は平成8年3月21日にBの一般行全てに対して母体行債権の全額放棄を基底とする本件閣議決定を前提とした負担見込額を書
“そして右合意に基づき債務者であるBから債権放棄の要請がなされ、同月29日に母体行債権の全額放棄について出資母体間協定を
“以上の事実からすれば、本件債権放棄が、母体行債権の最劣後性を前提とした本件閣議決定における全関係者の「合意」に基づいて実行され、その要請に従って早期の住専処理を実現するために行われたものであり、決して税務上の考慮によるものではないことは明らかである。また、原告は、本件債権放棄の時点で平成8年度予算及び住専処理法の成立は確実な状況にあり、原告はBの営業譲渡及び解散が行われることについて確信を持っていたのである。”
本件債権は平成8年3月期において、①合意により又は②社会通念上、弁済順序において「最劣後」のものとなっていたのであって、当時のBの資産価値をどのように高く見積もるとしても、本件債権の全額が回収不能の状態にあったのである。
“企業会計上適正に計上された本件の損失は、法人税法22条に照らして損金算入されることについてそもそも平成8年3月期に原告が本件貸出金償却を行い、本件債権の全額を「損失」として計上したことは、商法上、「企業会計の専門家の通説を含む企業関係者の社会通念」に照らして本件債権の取立不能を合理的に判断したものであり、また、企業会計上も適正なものである。
そして、法人税法22条は、「別段の定め」がない限り、損失の額を公正処理基準に従って計算すべきものとしているところ、被告は、同条にいう具体的な「別段の定め」を何ら主張し得なかったのであるから、公正処理基準に基づいて計上された本件債権に係る損失の全額が「損金」として取り扱われるべきことは同条に照らして明らかと言わざるを得ない。”
“法基通9-6-2に照らして本件債権の全額が貸倒れであることについて本件債権は平成8年3月末の段階において回収不能な債権となっていたのであって、法基通9-6-2に照らしても、全額について「貸倒れ」が認められるべきである。より具体的には、本件債権は平成8年3月期において、①合意により又は②社会通念上、弁済順序において「最劣後」のものとなっていたのであって、当時のBの資産価値をどのように高く見積もるとしても、本件債権の全額が回収不能の状態にあったのである。”
“本件債権の最劣後化についての合意が存在していたこと平成5年に策定され合意されたBの新事業計画においては、本件債権をはじめとする母体行債権が弁済順序において最劣後に置かれることが計画上明らかにされ、これに対して関係金融機関の全てが書面を以て明確に同意し、ここにおいて本件債権が弁済順序において最劣後に置かれることについて「関係者の合意」が成立していた。
そして、かかる本件債権の最劣後性についての「関係者の合意」を前提として、平成7年12月には母体行債権の全額放棄を基底とする「一次ロス」処理案について「関係者の合意」が成立し、さらには本件閣議決定においてかかる「合意」は公式に確認され、異例なことではあるが文書にて公表されるに至った。その後、かかる本件債権の最劣後性及び本件債権の全額放棄についての関係者の合意を前提とする「二次ロス」処理についても平成8年1月25日には「関係者の合意」が成立し、同月30日の本件閣議了解によって公式に確認され、右と同様に文書にて公表された。さらに、最終的には、原告から本件閣議決定に沿ったBにおける具体的な損失負担の見込額が書面によって一般行に通知され、これに対して異議申出期限である平成8年3月25日までに全く異議は出されなかったことによって、母体行債権が弁済順序において最劣後化し弁済を受けないものであることがBの関係者全員により「合意」され、確認されたのである。”
“右のような「合意」による劣後化の成否にかかわらず、過少資本等の一定の事由がある場合には社会通念上劣後化が認められ、倒産手続上も最劣後に扱われる債権については、経済的利益を回収することは期待できないのであるから、税法上当然に貸倒れが認められる。
そして、①Bが1パーセントを下回る過少資本の状態で推移し、原告の債務保証や不足資金の供与に支えられていたこと、②原告がBの二度にわたる再建計画の過程で、母体行責任を明確に表明してきたこと、及び③住専処理に当たって、住専最大の母体行であった原告が世論から厳しい追及を受け、母体行債権を超える負担を求められ、系統協議から閣議了解に至った経緯にかんがみれば、本件債権が社会通念上も最劣後に位置し、回収を図り得なかったこともまた明らかである。”
本件閣議決定によって定められた損失負担の割合は、大蔵省及び農林水産省という行政機関たる「第三者」のあっせん・仲介によって合意され成立したものであるから、法基通9-6-1(3)にいう「協議決定」に当たり、その内容はプロラタ(比例按分)負担ではないが、住専設立以来の経緯を反映している点で同通達にいう「合理的な基準」に該当するから、同通達によって本件債権の全額について「貸倒れ」が認められるべきである。被告は、税法上債権放棄の効力が生じるためには、「確定」が必要であるなどとも主張しているが、法人税法22条3項3号の損失」には、同項二号に定める「債務確定」とは異なり、「確定」は不要である。そもそも債権放棄の効力は解除条件の有無にかかわらず生じ、意思表示の時点で債権は消滅するのであるから、改めて「確定」を要する理由が見当たらない。その上、既に平成8年3月末までには政府の住専処理案の成立・実行は既定の方針となっており、解除条件の不成就は確実であったのだから、いずれにせよ平成8年3月期に本件債権放棄の効力は私法上も税法上も完全に生じていたことは明らかである。確定申告期限までに平成8年度予算と住専処理法が成立し、Bの営業譲渡及び解散が決議されていたという「客観的事実」にかんがみれば、あえて理論的見地から検討してみても、債権放棄の効力には疑念を挟む余地はない。
“Bが平成5年3月期以降平成8年3月期に至るまで相当の期間大幅な債務超過状態を継続し遂に事業を閉鎖したことにかんがみれば、本件債権の全額について「書面による債務免除」が行われている以上、法基通九-六-一(4)に照らしても、本件債権の全額について「貸倒れ」が認められるべきである。この点について、被告は①本件債権放棄の効力が私法上あるいは税法上平成8年3月期には発生していないとか、②同通達に基づく「貸倒れ」が認められるためには債権放棄の対象となった債権について、法基通九-六-二と同一の意味において回収不能でなければならないなどと主張しているが、以下のとおり、貸倒れが認められるべきである。”
“ア 私法上、解除条件付債権放棄の効力が意思表示の時点で生じることは疑う余地がない。
イ 被告は、税法上債権放棄の効力が生じるためには、「確定」が必要であるなどとも主張しているが、法人税法22条3項3号の損失」には、同項二号に定める「債務確定」とは異なり、「確定」は不要である。そもそも債権放棄の効力は解除条件の有無にかかわらず生じ、意思表示の時点で債権は消滅するのであるから、改めて「確定」を要する理由が見当たらない。その上、既に平成8年3月末までには政府の住専処理案の成立・実行は既定の方針となっており、解除条件の不成就は確実であったのだから、いずれにせよ平成8年3月期に本件債権放棄の効力は私法上も税法上も完全に生じていたことは明らかである。
ウ 確定申告期限までに平成8年度予算と住専処理法が成立し、Bの営業譲渡及び解散が決議されていたという「客観的事実」にかんがみれば、あえて理論的見地から検討してみても、債権放棄の効力には疑念を挟む余地はないところである。”
“本件債権放棄は法基通9-4-1の要件をすべて満たしていることBは原告との関係で「子会社等」に該当し、本件債権放棄はかかる子会社等の解散・整理に際してなされたものである。そして、平成8年3月当時、原告をはじめとした母体行が、①住専処理が円滑にいかなかった場合に生じる金融システムの混乱ないし崩壊による莫大な損失及び②世論からの完全母体行責任に基づく母体行の債権全額を超える追加負担要求によりさらなる損失を被るおそれにさらされていた。本件債権放棄は、原告の取締役会が事実関係に関する十分な情報を収集した上で、①本件閣議決定に従った母体行債権の全額放棄を粛々と進めることによってBの処理を円滑に進め金融システムの混乱ないし崩壊を回避するとともに、②母体行としての責任を果たすことによって、母体行に対する世論からの非難が沸騰してさらなる追加負担を強いられることを避けるべく実行されたものであって、まさに法基通9-4-1において「相当な理由」がある場合として例示されている「より大きな損失を避けるためにやむを得ず」行ったものに他ならないのである。”
“加えて、本件債権放棄は、原告にとって「事実上高度の強制的効果」を有する本件閣議決定(しかも本件閣議決定は「文書」によってなされた異例のものである。)及びそれに基づく大蔵省からの免許事業に対する監督権を背景とした強い指導が介在した上で行われたものであり、まさに原告にとっては「やむを得ざるもの」だったのであって、この点からしても法基通9-4-1の「相当な理由」が認められることは明らかである。”
“本件債権放棄による損失について法基通9-4-1が適用されるべきことは明らかであり、被告も翌期の平成9年3月期には法基通9-4-1の「相当な理由」があることを認めているところであって、平成9年3月期においては「相当な理由」が認められるとしながら、平成8年3月期にはそれを認めないという被告の主張には何ら合理的な理由は見い出せないのであるから、本件事実関係の下で、平成8年3月期において法基通9-4-1による損金算入を否認することは許されない。”
国税庁の主張
本件債権とBに対するその他の債権との法的整理手続における法的な優先劣後関係は、本件新事業計画や政府の住専処理策によっては全く影響を受けていない。
平成8年3月末当時、原告は、政府の住専処理策が実現しBが同処理策に従って整理されるならば原告は本件債権を全額放棄することが予定されてはいたものの、同処理策が実現するか否かについては全く予断を許さない状況にあり、仮に同処理策が実現せずBの法的整理手続に移行した場合には、債権者平等の原則による配当の可能性が残されていたことも事実である。本件債権放棄は、本件債権について原告が把握していた経済的価値を全く変動させていないという意味において、原告に何らの経済的効果をも生じさせていない。
” 本件債権とBに対するその他の債権との法的整理手続における法的な優先劣後関係は、本件新事業計画や政府の住専処理策によっては全く影響を受けておらず、平成8年3月末当時、原告は、政府の住専処理策が実現しBが同処理策に従って整理されるならば原告は本件債権を全額放棄することが予定されてはいたものの、同処理策が実現するか否かについては全く予断を許さない状況にあり、仮に同処理策が実現せずBの法的整理手続に移行した場合には、債権者平等の原則による配当の可能性が残されていたことも事実である。原告は、右のような状況において本件解除条件付債権放棄をしたのであるが、これはその実質において法的整理手続における回収の途を確保するという地位を放棄したものではなく、本件解除条件付債権放棄の前後において、政府の住専処理策が実現せずBの法的整理手続に移行した場合に債権者平等の原則による配当の可能性があるという状況に全く変化は生じていない。”
“要するに、原告は、本件解除条件付債権放棄をしようがするまいが、政府の住専処理策が実現すれば本件債権を回収することができない一方で、同処理策が実現せずBの法的整理手続に移行した場合には債権者平等の原則による配当を受けることができたのであり、本件解除条件付債権放棄の前後で、原告が本件債権を回収できる場合、時期及び方法には全く変化が生じていないのである。したがって、本件債権放棄は、本件債権について原告が把握していた経済的価値を全く変動させていないという意味において、原告に何らの経済的効果をも生じさせていないものと評価すべきものである。原告は、①本件新事業計画、②政府の住専処理策、③平成8年3月末におけるその実現の確実性、④本件解除条件付債権放棄の意義、目的に関する事実関係の評価を誤り、これに基づいて、⑤本件解除条件付債権放棄の経済的効果についての評価を誤っているというべきである。”
原告は、本件債権は歴史的経過の中で劣後化してきたと主張して、原告がBの「幹事母体行」「責任母体行」としての地位にあったことをはじめとし、平成5年策定の本件新事業計画以前の事情までも本件債権の劣後化をもたらした「歴史的経過」として主張しているが、このような事情は、平成8年3月における劣後化の有無を検討するに当たり、事情としての意味も有しないというべきである。
本件新事業計画に先立ち、乙大蔵省銀行局長と丙農林水産省経済局長の間では、平成5年2月3日、「大蔵・農水覚書」が締結されていたが、この大蔵・農水覚書はあくまで住専七社の再建を前提とするものであって、第二次再建計画が大蔵・農水覚書を踏まえていることを理由として本件新事業計画が整理計画としての側面を有すると評価することはできない。
第二次再建計画は、Bの再建を図ることを目的として策定されたものであることは明らかであり、そこにおける弁済順序の合意もあくまで再建計画における弁済順序であり、整理段階における弁済順序を示すものでない。第二次再建計画は、長期間はかかるであろうが、当時の状況認識の下での実現可能な文字通りの再建計画として策定されたものであり、ただ、その後の地価の急激な下落と長期間にわたる低迷までを予測できなかったために、結果的に実現できなかったにすぎない。したがって、本件新事業計画の実現が当初から不可能であったなどとして整理計画としての性格を肯定することはできない。本件閣議決定が示され、住専を整理する方針が示された後に、本件新事業計画どおり母体ニューマネーの返済が行われたからといって、その後の整理の場面において、当然に母体行の他の債権の返済が受けられなくなるというものではない。
“原告は、本件債権は歴史的経過の中で劣後化してきたと主張して、原告がBの「幹事母体行」「責任母体行」としての地位にあったことをはじめとし、平成5年策定の本件新事業計画以前の事情までも本件債権の劣後化をもたらした「歴史的経過」として主張しているが、このような事情は、平成8年3月における劣後化の有無を検討するに当たり、事情としての意味も有しないというべきである。”
“本件新事業計画は、平成5年における住専七社の第二次再建計画の一つとして策定されたものであるところ、右再建計画の策定に先立ち、乙大蔵省銀行局長(当時。以下「乙銀行局長」という。なお、以下、役職名等は当時のものを指す。)と丙農林水産省経済局長(以下「丙経済局長」という。)の間では、平成5年2月3日、「覚書」(以下「大蔵・農水覚書」という。)が締結されていた。しかし、この大蔵・農水覚書はあくまで住専七社の再建を前提とするものであって、第二次再建計画が大蔵・農水覚書を踏まえていることを理由として本件新事業計画が整理計画としての側面を有すると評価することはできない。”
“住専七社の第二次再建計画が再建を図ることを目的としたものであって、原告も、本件新事業計画を再建のための支援措置と位置付け、Bの再建を図ることを目的としてこれを策定したものであることは明らかであり、そこにおける弁済順序の合意もあくまで再建計画における弁済順序であり、整理段階における弁済順序を示すものでないことは明らかである。”
“第二次再建計画は、長期間はかかるであろうが、当時の状況認識の下での実現可能な文字通りの再建計画として策定されたものであり、ただ、その後の地価の急激な下落と長期間にわたる低迷までを予測できなかったために、結果的に実現できなかったにすぎないものというべきである。したがって、本件新事業計画の実現が当初から不可能であったなどとして整理計画としての性格を肯定することはできない。”
“本件新事業計画における弁済の順序の合意は、あくまで右新事業計画を進めBに「余裕資金」が生じた場合の弁済順序にすぎないものであって、整理段階における弁済の順序を定めるものではないし、また、母体行債権が弁済順序において最劣後することを定めているとも認められないから、整理段階における母体行債権の最劣後性を示すものではないことは明らかである。”
”本件閣議決定は、「母体ニューマネー」を対象とするものではないから、これについては、本件新事業計画どおりの返済を行うことは十分あり得ることであり、このことは大蔵大臣等の国会答弁からも明らかである。したがって、本件閣議決定が示され、住専を整理する方針が示された後に、本件新事業計画どおり母体ニューマネーの返済が行われたからといって、その後の整理の場面において、当然に母体行の他の債権の返済が受けられなくなるというものではない。”
”一般にある処理策が決定するまでには、基本的事項から周辺事項へというように各部分ごとに順次定まっていき、周辺事項は基本的事項を前提として決定されていくのが通常であるが、それが不可分一体の案である以上、全体が決定され実施されて初めてその実効性を有するのであって、それが実施に移されるまでは、基本的事項、周辺事項を含めて「案」の一部にすぎず、仮に実施に至らなければ、それまでに定まった部分を含めて白紙に帰することになるのであって、その一部に合意したからといって当該一部に従わなければならないわけでもないし、その一部のみが実施されるわけでもない。そして、政府の住専処理策も不可分一体のものであって、原告が主張するようにこれを「基層」部分と他の部分などと恣意的に分離し、「基層」部分に合意したからといって、全体が実現しない場合にも「基層」部分に拘束されるといえないことは当然のことである。”
”本件の具体的事実関係に照らしても、政府の住専処理策の目的、内容、その策定に至る経緯、政府側及び原告の認識、関係者の合意の状況に照らせば、同処理策で提示された損失負担割合はあくまで同処理策の実現を前提とするものであって、同処理策が実現せず法的整理手続に移行した場合には白紙に戻り、債権者平等の原則による配当の可能性が残されていたのであり、仮に平等の割合を超える損失負担があり得るとしても、それは裁判所の関与の下における、その時点における社会的・経済的状況を踏まえた各金融機関の自由な経営判断にゆだねられることが予定されていたというべきである。”
政府の住専処理策は、我が国経済を本格的な回復軌道に乗せるため、その早期解決を図る具体的な方策として講じられたものである。すなわち、法的整理手続による場合に生ずる社会的・経済的危機を回避するという政治的目的の下に策定されたものであり、右の危機によって個々の金融機関が被るであろう損失も計り知れないものであったから、これを避けるために個々の金融機関が平等の割合を超える損失負担に合意したことには経営判断としての合理性が認められる。しかし、法的整理手続自体は、裁判所が債権者平等の原則に従って財産を分配することを目的とする制度であって、政府の住専処理策のように政治的目的を実現するための手段ではない。平成8年の段階では、法的整理手続に移行したときには既に右の危機は現実化し、次第に重篤化することが予測されていたのであるから、平成7年12月や平成8年1月段階で平等の割合を超えて損失負担をしたとしても、政府の住専処理策と同様の見返りがあるとはいえず、そのような状況の悪化を予測できたにもかかわらず、平成7年12月の段階で法的整理手続までを含めて損失負担割合を定めることは到底合理的な経営判断とはいえない。
したがって、政府の住専処理策で提示された損失負担割合に同意した母体行は、あくまで同処理策の実現を前提として、これに同意
したものと解するのが合理的であり、同処理策が実現せず法的整理手続に移行した場合において仮に平等の割合を超える損失負担があり得るとしても、それはその時点における社会的・経済的状況を踏まえた各金融機関の自由な経営判断に基づく合意にゆだねられることが予定されていたと解するのが合理的である。
”政府の住専処理策は、住専をめぐる問題が金融機関の不良債権問題における象徴的かつ喫緊の問題であるとの認識の下、我が国の国際金融システムの安定性とそれに対する内外からの信頼を確保し、預金者保護に資すると同時に我が国経済を本格的な回復軌道に乗せるため、その早期解決を図る具体的な方策として講じられたものである。すなわち、政府の住専処理策は法的整理手続による場合に生ずる社会的・経済的危機を回避するという政治的目的の下に策定されたものであり、右の危機によって個々の金融機関が被るであろう損失も計り知れないものであったから、これを避けるために個々の金融機関が平等の割合を超える損失負担に合意したことには経営判断としての合理性が認められる。”
“これに対し、法的整理手続自体は裁判所が債権者平等の原則に従って財産を分配することを目的とする制度であって、政府の住専処理策のように政治的目的を実現するための手段ではない。また、これに参加する個々の金融機関は自己の社会的・経済的目的を実現するために平等の割合を超えて損失を負担することができるであろうが、平成8年の段階では、法的整理手続に移行したときには既に右の危機は現実化し、次第に重篤化することが予測されていたのであるから、平成7年12月や平成8年1月段階で平等の割合を超えて損失負担をしたとしても、政府の住専処理策と同様の見返りがあるとはいえず、そのような状況の悪化を予測できたにもかかわらず、平成7年12月の段階で法的整理手続までを含めて損失負担割合を定めることは到底合理的な経営判断とはいえない。”
“したがって、政府の住専処理策で提示された損失負担割合に同意した母体行は、あくまで同処理策の実現を前提として、これに同意したものと解するのが合理的であり、同処理策が実現せず法的整理手続に移行した場合において仮に平等の割合を超える損失負担があり得るとしても、それはその時点における社会的・経済的状況を踏まえた各金融機関の自由な経営判断に基づく合意にゆだねられることが予定されていたと解するのが合理的である。”
して、母体行の債権全額放棄、一般行の債権一部放棄、農協系統金融機関(以下「系統」という。)による贈与及び公的資金を引当と
する一次ロス(住専各社の有する第Ⅳ分類債権相当額の6兆2700億円ないしこれに欠損金1400億円を加えた6兆4100億円の損失。以下同じ。)の処理と、その他の住専資産の住専処理機構への引継並びに住専処理機構におけるその後の二次ロス(住専処理機構に引き継いだ住専各社の資産から生ずる損失。以下同じ。)の処理が不可分一体となった策であり、公的資金の投入や住専処理機構の設立をその不可欠の要素とするものである。
このように、法的整理手続と政府の住専処理策とは、内容的にも、処理される損失額及び損失負担者が大きく異なることが予想され
る上、その損失負担割合を決定するに当たり考慮される原則及び個別事情も異なるのであって、しかもその時における社会的・経済的状況が異なることも予想される以上、法的整理手続において仮に原告が平等の割合を超える損失負担を相当と認めることがあるとしても、当該損失負担割合が政府の住専処理策と同一になるとはいえないことは明らかである。
“政府の住専処理策は、住専七社の一括整理及びその際に生じる七兆6100億円の損失の一括処理を前提に、その基本的な枠組みと
“これに対し、法的整理手続に移行した場合、そこで処理される損失は、住専処理機構で生じるはずの二次ロスとの区別のない全損失であって、その金額も増大している可能性が高く、それを公的資金の投入なくして処理しなければならない。そして、そこにおける損失負担割合は債権者平等の原則を前提とするのであり、仮に諸般の事情からこれを超える負担を求められることがあるとしても、そこで考慮される事情は、裁判所が関与する手続であることから、政府の住専処理策が考慮していた事情とは異なることが予想され、さらに個別の住専ごとに行われる手続であるため個別の事情も考慮され得ることになる。”
“このように、法的整理手続と政府の住専処理策とは、内容的にも、処理される損失額及び損失負担者が大きく異なることが予想され
これに対し、政府の住専処理策が実現されず法的整理手続に移行した場合には、公的資金の投入や住専処理機構への営業譲渡はない
のであって、母体行が追加負担をせずに系統の損失負担を5300億に留めることは不可能であり、政府の住専処理策における損失負担割合と同一の合意はやはり成立し得ないことになる。そして、法的整理手続において特別な合意が成立しない場合には、債権者平等の原則に従って配当を行うより他はない。
“政府の住専処理策に対する母体行の合意は追加負担がないことを、系統の合意は公的資金の投入を、それぞれ不可欠の前提条件とし
これに対し、政府の住専処理策が実現されず法的整理手続に移行した場合には、公的資金の投入や住専処理機構への営業譲渡はない
“政府の住専処理策は、平成8年度予算や住専処理法が成立するのみで実現できるものではなく、それらの成立後に個別の住専ごとに
本件閣議決定において決定された住専問題の処理のための資金支出等が織り込まれた平成8年度予算案は、同年6月18日に至ってようやく成立した。公的資金投入に対する世論の反対は極めて強く、平成8年度予算の審議再開の原因となった参議院岐阜補欠
選挙の結果についても、政府の住専処理策に対する信任を意味するものではないと解するのが世論・政府の共通の認識であり、政府側も世論の反対の強さに配慮して十分に国会審議を尽くそうとしていたのであって、このような段階で住専処理法の成立が確実であったなどというのは、あまりにも世論を無視した暴論である。よって、平成8年3月末の段階で、住専処理法が可決されるかどうかは不透明であり、政府の住専処理策が実現するか否かについては全く予断を許さない状況にあったことは明らかである。
“本件閣議決定において決定された住専問題の処理のための資金支出等が織り込まれた平成8年度予算案は、平成8年1月22日に衆
本件解除条件付債権放棄を承認した原告の取締役会において「仮に政府案が不成立となって法的整理となったとしても」として政府
の住専処理策が実現しない場合を具体的に想定した検討が行われていた。そして、原告は、仮に将来法的整理手続に移行すれば、債権者平等の原則に従った配当を受けられるという認識を有していた。平成8年3月末の時点においては、原告自身も政府の住専処理策が実現することが確実であるとは考えていなかったことが明白である。
“本件解除条件付債権放棄を承認した原告の取締役会において、「政府案の成立可能性に対する見通し」として「現時点で政府案の成
原告が、他のほとんどすべての銀行が債権放棄を見合わせたことを知りながら、かつ、代表訴訟のおそれがあるにもかかわらず、本
件事業年度において本件解除条件を付して本件債権を放棄することとしたのは、それが株主代表訴訟を牽制しつつ、他方で本件債権額を税務上も本件事業年度の損金に算入する最後の方法であったことによると推認することができる。本件解除条件付債権放棄は、課税負担を免れるとともに将来の法的整理手続における回収の途を確保するという意味を有していたといえる。
“原告が、他のほとんどすべての銀行が債権放棄を見合わせたことを知りながら、かつ、代表訴訟のおそれがあるにもかかわらず、本
法人税法上の損失計上についての考え方は、次のとおりである。
債権の切捨てや債権放棄等による法律上の資産価値の消滅の場合、当該切捨てや債権放棄等による損失は確定している必要がある。法人税法22条3項3号の「損失」が法律行為という外部取引によって生じる場合には、同項2号の債務の確定と同様に「確定」を
要するからである。したがって、債権の切捨てや債権放棄がされても、これによる損失がいまだ確定していない場合には、法人税の計算上当該債権放棄による損失を損金に算入することはできない。
次に、当該切捨てや債権放棄等は、原則として回収不能な債権について行われる必要がある。法人税法37条2項は、同法22条3項の「別段の定め」として、「内国法人が各事業年度において支出した寄附金の額・・・の合計額のうち、その内国法人の資本等の金額又は当該事業年度の所得の金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額・・・を超える部分の金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。」と規定しており、回収不能とはいえない債権の切捨てや債権放棄は、原則として同条6項の「経済的な利益・・・の供与」に当たり寄附金に該当するからである。
以上で述べた基本的枠組みを前提にして、金銭債権の資産損失を損金に算入し得る基準を明らかにしたのが、法基通9-6-2、9-6-1、9-4-1である。
“法人税法22条3項は「内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の損金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、次に掲げる額とする。」と規定し、その3号において「当該事業年度の損失の額で資本等取引以外の取引に係るもの」と規定する。法人が有する金銭債権という資産について、その資産価値が失われた場合には、いわゆる資産損失として、その失われた事業年度において右に掲げた法人税法22条3項3号の「当該事業年度の損失」に該当するのが原則である。”
“ところで、右に述べた金銭債権の資産価値が失われる場合には、会社更生法等の法的負債整理等による債権の切捨てや債権放棄等により、債権そのものが法律上、客観的に消滅し、その資産価値が消滅する場合のほか、法律上債権が存続しているが、その回収が事実上不能となり、資産価値が事実上消滅するという場合がある。各場合における法人税法上の損失計上についての考え方は、次のとおりである。まず、事実上の資産価値の消滅の場合は、これによる損失は、法人税の計算上、その全額の回収が事実上不能であることが客観的に確定した事業年度の損金に算入することができる。”
“他方、債権の切捨てや債権放棄等による法律上の資産価値の消滅の場合にも、当該切捨てや債権放棄等による損失は確定している必要がある。法人税法22条3項3号の「損失」が法律行為という外部取引によって生じる場合には、同項2号の債務の確定と同様に「確定」を要するからである。したがって、債権の切捨てや債権放棄がされても、これによる損失がいまだ確定していない場合には、法人税の計算上当該債権放棄による損失を損金に算入することはできない。”
“次に、当該切捨てや債権放棄等は、原則として回収不能な債権について行われる必要がある。法人税法37条2項は、同法22条3項の「別段の定め」として、「内国法人が各事業年度において支出した寄附金の額・・・の合計額のうち、その内国法人の資本等の金額又は当該事業年度の所得の金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額・・・を超える部分の金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。」と規定しており、回収不能とはいえない債権の切捨てや債権放棄は、原則として同条6項の「経済的な利益・・・の供与」に当たり寄附金に該当するからである。もっとも、当該切捨てや債権放棄等が回収不能部分のみについて行われた場合は経済的利益の供与があったとはいえないから、寄附金には該当せず、その額を損金に算入することができる。”
“また、当該切捨てや債権放棄等が回収不能とはいえない債権について行われた場合にも、当該経済的な利益の供与につき経済取引として十分に首肯し得る合理的理由があるときは任意の利益処分とはいえないから、利益処分性に着目した寄附金制度の趣旨に照らし寄附金には該当せず、その額を損金に算入することができる。”
“事実上の回収不能によって税務上貸倒損失が認められるためには、債務者の資産状況、支払能力、債権者の回収努力の有無、担保の設定状況等、諸般の事情を総合的に勘案し、その全額が回収できないことが客観的に確定した場合でなければならず、法基通9-6-2が「法人の有する貸金等につき、その債務者の資産状況、支払能力等からみてその全額が回収できないことが明らかになった場合には、その明らかになった事業年度において貸倒れとして損金経理をすることができる。」と定めているのも、このことを明らかにしたものである。”
“そして、債務者の資産状況、支払能力等から当該債権の回収が事実上不可能であることが客観的に明らかになる場合としては、強制執行、破産手続、会社更生、整理といった回収不能を推定し得る法律的措置が採られた場合及びこれに準じるような場合、すなわち債務者の死亡や所在不明又は事業閉鎖というような回収不能の事実が不可逆的で、一義的に明白な場合に限られると解すべきである。そして、一般に更正処分取消訴訟における課税要件事実の存否等については、課税庁側が主張・立証責任を負うべきところ、貸倒損失については、これを基礎付ける具体的事実関係を原告において主張・立証しない限り、その不存在が事実上推定されると解すべきである。”
本件事業年度終了時である平成8年3月31日において、Bの借入金等の返済のための資産が約1兆円残されていた。この金額は借入金総額の約40パーセントにも上るのであり、このようなBの財務状況では、本件債権が事実上の貸倒れであったということは到底認められない。
“本件事業年度終了時である平成8年3月31日において、Bの借入金等の返済のための資産が約1兆円残されていた。この金額は借入金総額の約40パーセントにも上るのであり、このようなBの財務状況では、本件債権が事実上の貸倒れであったということは到底認められない。また、同月29日の本件解除条件付債権放棄は、政府の住専処理策が実現しなければ放棄されないことになるところ、同処理策が実現するか否かについては全く予断を許さない状況にあり、同処理策が実現せず、法的整理手続に移行した場合には、債権者平等の原則による配当を受ける可能性が残されていたのであって、結局、本件債権は、本件事業年度においてその全額の回収が不能であることが客観的に確定したとは到底いえず、本件事業年度において原告に本件債権に係る事実上の回収不能による損失が生じたとはいえない。”
原告の主張は、まず事実上回収不能であったという結論を出発点として主張を構成していて、本件新事業計画には、再建的側面と整理的側面を併せ有していたものであるという根拠のない主張をしたり、本件スキームの「層状構造」、「基層」部分の固定といった独自の概念を持ち出さざるを得なかったのであり、このような、無理な理屈を幾重にも構築しなければならないこと自体、本件債権が事実上回収不能ではないことの証左といえる。
そもそも事実上の貸倒れが客観的に認められるということは、誰の目から見ても事実上の貸倒れであることが明白でなければならず、そうすると、政府の住専処理策という一個の事象に対して、その事実認識及び事実評価が人によって異なるということ自体が、「誰の目から見ても」事実上の貸倒れであることが明白であるとはいえないからである。
“原告の主張は、まず事実上回収不能であったという結論を出発点として主張を構成しているといわざるを得ず、それだからこそ、原告は本件新事業計画には、再建的側面と整理的側面を併せ有していたものであるという根拠のない主張をしたり、本件スキームの「層状構造」、「基層」部分の固定といった独自の概念を持ち出さざるを得なかったのであり、このような、無理な理屈を幾重にも構築しなければならないこと自体、本件債権が事実上回収不能ではないことの証左といえる。”
“仮に一歩譲って、本件債権を取り巻く事実関係についての原告の認識が原告の主張どおりであるとしても、やはり本件債権が客観的に事実上回収不能であったと認めることはできないのである。なぜならば、そもそも事実上の貸倒れが客観的に認められるということは、誰の目から見ても事実上の貸倒れであることが明白でなければならず、そうすると、政府の住専処理策という一個の事象に対して、その事実認識及び事実評価が人によって異なるということ自体が、「誰の目から見ても」事実上の貸倒れであることが明白であるとはいえないからである。”
“そして、「誰の目から見ても」事実上の貸倒れであることが明白であるかどうかの判断、特に本件について言えば、住専処理策の実現が確実だと原告が信じていたことをもって本件債権を取り巻く政府の住専処理策をめぐる事実関係が判断されるのではないことは当然であり、あくまで、同処理策をめぐる事実関係の評価は、当時の社会的・政治的情勢に照らして客観的に判断されるべきものだからである。”
法基通9-6-1(4)は、経済的に無価値となった債権を法律的にも消滅させる場合であるから、債権放棄による損失を損金に算入するためには当該債権放棄が私法上の効果を生じていることが必要である。
ところが、本件約定書が作成された平成8年3月29日においては、政府の住専処理策が実現するか否かについては全く予断を許さない状況にあり、その確定を見ることなく、債権放棄のみについて法的な効果を先に生じさせる合理的な理由はない。したがって、本件債権が本件事業年度において法律上消滅したことにより原告に損失が生じたとはいえない。
債権放棄の場合における右の経済的効果とは当該債権の回収可能性の喪失にほかならない。ところが、本件解除条件付債権放棄の前後で原告が本件債権を回収できる場合、時期及び方法には全く変化が生じておらず、本件解除条件付債権放棄は原告に何らの経済的効果も生じさせていない。このことは、当事者である原告及びBが行為時において本件債権の回収可能性の喪失という債権放棄本来の経済的効果の実現を欲していないことにほかならず、本件解除条件を文字通り解除条件と解することは極めて不合理といわざるを得ない。
“法基通9-6-1(4)は、経済的に無価値となった債権を法律的にも消滅させる場合であるから、債権放棄による損失を損金に算入するためには当該債権放棄が私法上の効果を生じていることが必要である。
“また、解除条件という附款が停止条件という附款と異なる本質は、後に行為の法律効果が失われるとしても、行為時において一応法律効果を生じさせる点にあるのであり、かつ、その法律効果は当事者が欲した経済的効果の実現に法が助力するためのものである。債権放棄の場合における右の経済的効果とは当該債権の回収可能性の喪失にほかならない。ところが、前記(一)(6)のとおり、本件解除条件付債権放棄の前後で原告が本件債権を回収できる場合、時期及び方法には全く変化が生じておらず、本件解除条件付債権放棄は原告に何らの経済的効果も生じさせていない。このことは、当事者である原告及びBが行為時において本件債権の回収可能性の喪失という債権放棄本来の経済的効果の実現を欲していないことにほかならず、本件解除条件を文字通り解除条件と解することは極めて不合理といわざるを得ない。”
原告は、平成8年3月末当時、政府の住専処理策の帰すうが明らかになるまでは本件債権を現実に行使することができず、これが実現しないで法的整理手続に移行したときには本件債権を回収することができ、これが実現した場合は本件債権を放棄すべきことが予定されていたのである。その原告が、同じ政府の住専処理策が実現しないという反対事実を解除条件として本件債権を放棄することは、もともと一定の事実が生じたときに限り行使できる債権について、当該一定の事実が生じるか否か未定の間に、当該事実が生じないことを解除条件として放棄する場合と同じように、極めて技巧的かつ無意味な行為である。
“原告が、右のとおり回収可能性の喪失という債権放棄本来の経済的効果を欲していないにもかかわらず、本件解除条件付債権放棄をしたのは、ひとえに本件債権の償却に備えて計上した多額の株式売却益に対する課税負担を回避するためであったと推認できるものである。この課税負担の軽減を図るという目的は、真実は契約書に記載された法律効果を生じさせる意思がないことを推認させるものである。さらに、本件解除条件を文字通り解除条件と解することは極めて不自然でもある。
すなわち、原告は、平成8年3月末当時、政府の住専処理策の帰すうが明らかになるまでは本件債権を現実に行使することができず、これが実現しないで法的整理手続に移行したときには本件債権を回収することができ、これが実現した場合は本件債権を放棄すべきことが予定されていたのである。その原告が、同じ政府の住専処理策が実現しないという反対事実を解除条件として本件債権を放棄することは、もともと一定の事実が生じたときに限り行使できる債権について、当該一定の事実が生じるか否か未定の間に、当該事実が生じないことを解除条件として放棄する場合(例えば、停止条件付権利を当該停止条件の成就を解除条件として放棄する場合や、弁済期到来前の解除条件付権利を当該解除条件の不成就を解除条件として放棄する場合)と同じように、極めて技巧的かつ無意味な行為であって、せいぜい当該債権の性質を確認する意味しか有していない。にもかかわらず、これを真正な解除条件のごとく解するのは極めて不自然というべきである。”
東京高裁/両者の主張
納税者の主張
“被控訴人は、Bの設立母体であるのみならず、資本、資金及び人的関係のあらゆる観点においてBと密接な関係にあって、その経営に深く関与し、B設立以来、非母体行のBに対する融資を保証してきたものであり、この保証は、昭和55年以降、行政指導によって集合債権譲渡担保方式に順次切り替えられたが、被控訴人は、その協定幹事行として、他の債権者のために担保権の管理をなすべき立場に就いていたものであり、非母体行は、Bへの与信は被控訴人の信用に支えられたものとして、その取引を拡大してきたところである。このような経緯に鑑みると、被控訴人と非母体行との間においては、当時から既に被控訴人のBに対する貸出債権が非母体行の同社に対する貸出債権より弁済順序の点で劣後するとの了解がされていたというべきである。”
Bにおいては、その設立から平成8年3月29日に被控訴人が本件債権を放棄するまでの間に、実質的な債務超過の状態が長期間継続し、その経営破綻に伴って保有資産の実質価値が著しく毀損されて減少していたものであり、そのような中で被控訴人を含む母体行のBに対する債権は非母体行の債権に対して弁済順序において劣後することが段階的に顕在化したものであって、本件債権は、平成8年3月末までの間に、関係金融機関の合意又は社会通念により、弁済順序において最劣後のものとなっていたのであり、当時のBの資産価値をどのように高く見積もったとしても、本件債権の全額が回収不能の状態にあったことは明らかである。また、住専問題は、当時、政治問題化して世間の注目を集め、母体行としての責任を厳しく問われていたのであるから、被控訴人が本件債権を行使することは、社会全体を敵に回すに等しく、社会的存在としての銀行にとってこの上なく有害な行為というほかなかったというべきであるから、平成8年3月末までに本件債権を回収することは事実上不可能になっていたものというべきであって、本件債権は、本件事業年度において、社会通念上回収不能の状態にあったものというべきである。
“Bを含む住専各社の財務・経営状態は、平成4年以降、いわゆるバブル経済の崩壊により急激に悪化したため、Bの責任母体行である被控訴人は、同年5月、Bの事業計画(以下「第1次再建計画」という。)を立案し、農協系統金融機関らに対して、融資残高の維持を要請したところ、農協系統金融機関は、融資残高の維持に応じる条件として、①母体行がBを支援することを表明すること、②農協系統金融機関の債権(系統債権)の優先弁済性を確保するために系統債権を全額有担保化することを要求したため、被控訴人は
“ところが、地価の下落に伴い、住専各社の財務状況の悪化は一層顕著となったため、大蔵省の要請により、平成5年12月27日、Bの財務状況を再建するための新事業計画(以下「本件新事業計画」という。)が策定されたが、同計画では、高利優先弁済を前提として、関係金融機関のBに対する債権の金利は、農協系統金融機関のそれが4.5パーセント、その他の非母体行(以下「一般行」という。)のそれが2.5パーセント、被控訴人ら母体行のそれが0パーセントと定められ、その結果、担保協定に基づく集合債権
“しかしながら、平成7年8月に実施された住専各社に対する大蔵省の立入調査によって、住専各社の破綻が明らかとなったため、被控訴人は、平成7年9月22日、Bの母体行を招集して同社を整理する方針を確認し、また、被控訴人らBの母体行は、平成7年9月以降、Bの破綻処理問題について農協系統金融機関と協議を始めたが、Bを整理する段階でも母体行の債権を最劣後に置き、農協系統金融機関の債権を最優先とすることについては、何らの異論もなかった。”
“住専各社全体をみると、住専各社の母体行の債権(3兆5000億円)のみならず、農協系統金融機関以外の一般行の債権(3兆8000億円)の全額(合計7兆3000億円)を劣後させても、農協系統金融機関の債権に合計約2000億円もの元本ロスが生じることが確認されたため、関係機関の間でこれを誰がどのように負担するかという点を巡って協議が進められていたところ、大蔵省は、平成7年12月17日、住専各社に生じる約7兆5000億円の損失のうち第Ⅳ分類(大蔵省の金融検査における資産査定の分類基準上、回収不可能又は無価値と判定される資産に分類される債権)に該当する約6兆3000億円の損失をいわゆる1次ロスとして切り分け、このような1次ロスについて、母体行は債権全額を、農協系統金融機関以外の一般行は債権の一部をそれぞれ放棄し、農協系統金融機関は、貸付債権全額の返済を前提として、住専各社の資産を引き継ぐ組織(住専処理機構)に約5300億円を贈与すること、政府が住専処理のために6800億円の公的資金を支出することなどを内容とする住専処理計画を発表し、被控訴人は、翌18日に、これに同意することを大蔵省に伝え、農協系統金融機関を含め、すべての関係金融機関がこれに同意した結果、母体行債権の最劣後性を前提とした母体行債権の全額放棄を基底とする1次ロスに係る全ての関係者間の合意が成立し、これに基づいて、内閣は、翌19日、損失の処理、関係金融機関に対する要請、公的関与及び債権回収の促進について所要の法的措置を講ずることによって、破綻した住専各社の処理を進めることを内容とする「住専問題の具体的な処理策について」と題する閣議決定(本件閣議決定)を行った。”
“被控訴人は、Bが整理されることになったことを受け、平成7年12月29日までに本件新事業計画で余裕資産による弁済が第2順位で保証されていた再建のための新規融資金(母体ニューマネー)をBから回収し、Bに対する貸金残元本が3760億5500万円となった。”
“大蔵省は、引き続き、残る第Ⅲ分類債権(最終の回収又は価値について重大な懸念が存し、したがって、損失の発生が見込まれるが、その損失額の確定し得ない資産に分類される債権)から生ずる損失見込額1兆2000億円のいわゆる2次ロスの処理について関係金融機関と協議を重ねた結果、これについては、農協系統金融機関も含めた金融機関が拠出した基金の運用益等によって処理されることとされ、内閣は、関係金融機関の合意を踏まえ、平成8年1月30日、住専処理方策を具体化する旨の「住専処理方策の具体化」と題する閣議了解(以下「本件閣議了解」という。)を行った。”
“被控訴人は、平成8年3月21日、Bの農協系統金融機関以外の一般の金融機関全てに対し、母体行債権の全額放棄を基底とし、本件閣議決定を前提とした負担見込額を書面により通知し、異議のある場合は被控訴人に申し出るよう明確に求めたが、これに対して異議申出期限である同月25日までに何らの異議も出されなかったもので、これによって、すべての関係金融機関からBの破綻処理に係る具体的な損失負担割合についての同意が得られ、被控訴人のBに対する本件債権の全額が回収不可能であることもまた最終的に確認され合意された。そしてこの合意に基づき債務者であるBから債権放棄の要請がなされて、そのころには平成8年度予算及び住専処理法の成立は確実な状況にあったことも踏まえ、同月29日にはBの母体行の間において母体行債権の全額放棄を内容とする出資母体間協定が締結され、被控訴人は、Bと本件約定書を取り交して、全ての担保権を無条件で放棄するとともに、本件債権放棄を行ったものである。”
“以上のように、Bにおいては、その設立から平成8年3月29日に被控訴人が本件債権を放棄するまでの間に、実質的な債務超過の状態が長期間継続し、その経営破綻に伴って保有資産の実質価値が著しく毀損されて減少していたものであり、そのような中で被控訴人を含む母体行のBに対する債権は非母体行の債権に対して弁済順序において劣後することが段階的に顕在化したものであって、本件債権は、平成8年3月末までの間に、関係金融機関の合意又は社会通念により、弁済順序において最劣後のものとなっていたのであり、当時のBの資産価値をどのように高く見積もったとしても、本件債権の全額が回収不能の状態にあったことは明らかである。また、住専問題は、当時、政治問題化して世間の注目を集め、母体行としての責任を厳しく問われていたのであるから、被控訴人が本件債権を行使することは、社会全体を敵に回すに等しく、社会的存在としての銀行にとってこの上なく有害な行為というほかなかったというべきであるから、平成8年3月末までに本件債権を回収することは事実上不可能になっていたものというべきであって、本件債権は、本件事業年度において、社会通念上回収不能の状態にあったものというべきである。したがって、基本通達9-6-2により、本件債権の全額について貸倒れとして損金経理をすることが認められるべきである。”
本件債権放棄には解除条件が付されているところ、法人税法22条3項3号の「損失」については、その確定は必要ではなく、また、そもそも債権放棄の効力は、意思表示の時点で発生するのであるから、改めて確定を要するものとする理由も見当たらない。その上、既に平成8年3月末までには住専処理法及び住専処理を前提とする予算の成立は既定の方針となっており、解除条件の不成就は確実であったもので、その後、確定申告期限である平成8年7月1日までに住専処理を前提とする平成8年度予算と住専処理法が成立し、Bの営業譲渡及び解散が決議されたことを考え併せると、本件債権放棄の効力は、平成8年3月期において私法上も税法上も完全に生じていたというべきである。
“被控訴人は、平成8年3月29日、本件債権放棄を行ったが、Bは、平成5年3月期以降平成8年3月期に至るまで相当の期間大幅な債務超過状態を継続させていたのであるから、基本通達9-6-1(四)によっても、本件債権の全額が貸倒れとして損金の額に算入されるべきである。
基本通達9-6-2とは別途に、基本通達9-6-1(四)が設けられた趣旨は、「一定の客観的事実の存在」と「書面による債務免除の意思表示」をもって、当該債権の経済的価値の精査をすることなく貸倒れを認める点にあるというべきであるから、基本通達9-6-1(四)の適用に当たっては、基本通達9-6-2と同様な意味での「回収不能」な債権である必要はなく、本件債権の全額が貸倒れと認められるべきである。
また、本件債権放棄には解除条件が付されているところ、法人税法22条3項3号の「損失」については、同項2号に定める場合(同号においては「債務の確定」を必要とする。)とは異なって、その確定は必要ではなく、また、そもそも債権放棄の効力は、意思表示の時点で発生するのであるから、改めて確定を要するものとする理由も見当たらない。その上、既に平成8年3月末までには住専処理法及び住専処理を前提とする予算の成立は既定の方針となっており、解除条件の不成就は確実であったもので、その後、確定申告期限である平成8年7月1日までに住専処理を前提とする平成8年度予算と住専処理法が成立し、Bの営業譲渡及び解散が決議
Bは、被控訴人の「子会社等」に該当し、本件債権放棄は、このような子会社等の解散・整理に際してされたものである。そして、被控訴人をはじめとした住専各社の母体行は、平成8年3月当時、住専処理が円滑にいかなかった場合に生じる金融システムの混乱による損失を被るおそれにさらされていたところ、本件債権放棄は、本件閣議決定に従ったBの処理を円滑に進め金融システムの混乱を回避し、母体行としての責任を果たし、母体行に対する世論からの非難が沸騰することを避けるべく実行されたものであって、より大きな損失を避けるためにやむを得ず行われたものである。
“Bは、被控訴人との関係で基本通達9-4-1所定の「子会社等」に該当し、本件債権放棄は、このような子会社等の解散・整理に際してされたものである。そして、被控訴人をはじめとした住専各社の母体行は、平成8年3月当時、住専処理が円滑にいかなかった場合に生じる金融システムの混乱ないし崩壊による莫大な損失、母体行の債権全額を超える追加負担要求による損失を被るおそれにさらされていたところ、本件債権放棄は、本件閣議決定に従ったBの処理を円滑に進め金融システムの混乱ないし崩壊を回避し、母体行としての責任を果たすことによって、母体行に対する世論からの非難が沸騰することを避け、追加負担を強いられることを避
加えて、本件債権放棄は、被控訴人にとって「事実上高度の強制的効果」を有する本件閣議決定及び免許事業に対する監督権を背景とした大蔵省からの強い指導が介在した上で行われたものであって、被控訴人にとっては、やむを得ざるものだったから、基本通達9-4-1によっても、本件債権の全額が貸倒れとして損金の額に算入することが認められるべきである。”
“平成8年3月期において被控訴人と同様に住専向け債権を放棄した株式会社〈D〉銀行については、基本通達9-4-1が適用されることを否定されなかったものであり、また、株式会社〈b〉等の事案において、解除条件付きで債権放棄をした事業年度において損金算入を認めているのであるから、本件債権放棄について損金算入を認めないことは、合理的理由なく特定の納税者についてのみ不利な取扱いをするものであって、課税の公平性の原則からいって、許されない。”
国税庁の主張
“事実上の回収不能によって税務上貸倒損失が認められるためには、債務者の資産状況、支払能力、債権者の回収努力の有無、担保の設定状況等、諸般の事情を総合的に勘案し、その全額が回収できないことが客観的に確定した場合でなければならず、具体的には、強制執行、破産手続、会社更生、整理といった回収不能を推定し得る法律的措置が採られた場合及びこれに準じるような場合、すなわち債務者の死亡や所在不明又は事業閉鎖というような回収不能の事実が不可逆的で、一義的に明白な場合に限られると解すべき
本件約定書が作成された平成8年3月29日においては、政府の住専処理計画が実現するか否かについては全く予断を許さない状況にあって、その確定を見ることなく、債権放棄のみについて法的な効果を先に生じさせる合理的な理由はなかったのであるから、解除条件が付された本件債権放棄を行った被控訴人の真の意思は、政府の住専処理計画の実現に必要な予算や法律の成立を見るまでは債権放棄の効果を生じさせないというものであったと解するのが相当である。
“基本通達9-6-1(昭和55年12月25日直法2-15)は、「法人の有する売掛金、貸付金その他の債権(以下この節において「貸金等」という。)について次に掲げる事実が発生した場合には、その貸金等の額のうち次に掲げる金額は、その事実の発生した日の属する事業年度において貸倒れとして損金の額に算入する。」と定め、同(四)は、「債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、その貸金等の弁済を受けることができないと認められる場合において、その債務者に対し書面により明らかにされた債務免除額」を掲げているところ、これは、経済的に無価値となった債権を法律的にも消滅させる場合について定めたものであるから、債権放棄による損失を損金に算入するためには、当該債権放棄が私法上の効果を生じていることが必要である。”
“ところが、本件約定書が作成された平成8年3月29日においては、政府の住専処理計画が実現するか否かについては全く予断を許さない状況にあって、その確定を見ることなく、債権放棄のみについて法的な効果を先に生じさせる合理的な理由はなかったのであるから、解除条件が付された本件債権放棄を行った被控訴人の真の意思は、政府の住専処理計画の実現に必要な予算や法律の成立を見るまでは債権放棄の効果を生じさせないというものであったと解するのが相当であり、それにもかかわらず、被控訴人が、本件債権放棄をしたのは、ひとえに本件債権の償却に備えて計上した多額の株式売却益に対する課税負担を回避するためであったと推認することができ、本件債権放棄は、本件事業年度において債権放棄としての私法上の効果を生じておらず、被控訴人に損失が生じたとはいえないから、基本通達9-6-1(四)所定の債権放棄等による貸倒れには該当しない。”
債権放棄による損失が、法人税法22条3項3号の「当該事業年度の損失」に該当するためには、その私法上の効果が発生し、かつ、これによる損失が確定していることを要するものである。本件事業年度においては、解除条件付きの本件債権放棄の私法上の効果は発生しておらず、また、これによる損失が確定したとも認められないから、解除条件付きの本件債権放棄は、基本通達9-4-1の該当性を論ずる前提を欠いている。
“基本通達9-4-1(昭和55年5月15日直法2-8)は、「法人がその子会社等の解散、経営権の譲渡等に伴い当該子会社等のために債務の引受その他の損失の負担をし、又は当該子会社等に対する債権の放棄をした場合においても、その負担又は放棄をしなければ今後より大きな損失を蒙ることになることが社会通念上明らかであると認められるためやむを得ずその負担又は放棄をするに至った等そのことについて相当な理由があると認められるときは、その負担又は放棄をしたことにより生ずる損失の額は、寄附金の額に該当しないものとする。」と定めるところ、債権放棄による損失が、法人税法22条3項3号の「当該事業年度の損失」に該当するためには、その私法上の効果が発生し、かつ、これによる損失が確定していることを要するものであり、本件事業年度においては、解除条件付きの本件債権放棄の私法上の効果は発生しておらず、また、これによる損失が確定したとも認められないから、解除条件付きの本件債権放棄は、基本通達9-4-1の該当性を論ずる前提を欠いている。”
“また、法人税法37条1項は「各事業年度において寄附金を支出した場合」と規定し、現金主義に依拠しているところ、「寄附金を支出」した場合であっても、それが条件付きであるような場合は、現金主義の下では寄附金には該当しないと解され、いわんや解除条件の付された本件債権放棄のように何ら経済的効果を及ぼさないものについては、利益操作を排除するなどの目的で現金主義を採用した法人税法の趣旨に照らし、「支出」したと認める余地さえない。したがって、基本通達9-4-1によって、本件債権を損金の額に算入することはできない。”
最高裁/両者の主張
納税者
追加主張無し
国税庁
追加主張無し
両者の主張まとめ
- ■国税庁
- ■金銭債権の資産価値が失われる場合には、会社更生法等の法的負債整 理等による債権の切捨てや債権放棄等により、債権そのものが法律上、客観的に消滅し、その資産価値が消滅する場合のほか、法律上債権が存続してい るが、その回収が事実上不能となり、資産価値が事実上消滅するという場合 がある。事実上の資産価値の消滅の場合は、これによる損失は、法人税の計算上、その全額の回収が事実上不能であることが、客観的に確定した事業年度の損金に算入することができる。 他方、債権の切捨てや債権の放棄等による法律上の資産価値の消滅の場合 にも、当該切捨てや債権放棄等による損失は確定している必要がある。
■平成8年3月31日において、JHL社には資産が約1兆円残されていたのであり、政府の住専処理策が実現せず、法的整理手続に移行した場合には、債権者平等の原則による配当を受ける可能性が残されていたのであって、 結局、本件債権は本件事業年度においてその全額が回収不能であることが客 観的に確定したとは到底いえない。
■本件解除条件付債権放棄を行った原告の真の意思は、政府の住専処理策の実現に必要な予算や法律の成立を見るまでは債権放棄の効果を生じさせないというものであったと解するのが相当であり、本件解除条件付債権放棄は、 本件事業年度において私法上の効果を生じていない。 仮に本件解除条件付債権放棄によって本債権が法律上は解除条件付きで消 滅したとしても、いまだこれによる損失が確定したとはいえず、法人税法22 条3項3号にいう「当該事業年度の損失」が生じたとはいえない。
■政府の住専処理策は、法基通9-6-1(3)にいう 「合理的な基準」 に該当せず、それについての「合意」は、「基本的な枠組み」に対する「おおむね」の合意にすぎないもので同通達にいう関係者の「協議決定」と同視することはできない。
■本件解除条件付債権放棄は、私法上の効果が発生しておらず、法基通 9-4-1にいう「経済的利益の供与」が不存在であり、平成8年3月31日 当時は、政府の住専処理策が実現するか否か判断を許さない状況にあったことから、同通達に定める「相当な理由」を認める余地もない。 - ■納税者
- ■平成8年3月期に原告が本件貸出金償却を行い、本件債権の全額を 「損失」として計上したことは、商法上、「企業会計の専門家の通説を含む企 業関係者の社会通念」に照らして本件債権の取立不能を合理的に判断したも のであり、また、企業会計上も適正なものである。 そして、法人税法22条は、「別段の定め」がない限り、損失の額を公正処 理基準に従って計算すべきものとしているところ、被告は、同条にいう具体 的な「別段の定め」を何ら主張し得なかったのであるから、公正処理基準に 基づいて計上された本件債権に係る損失の全額が「損金」として取扱われる べきことは同条に照らして明らかと言わざるを得ない。
■本件債権は平成8年3月末の段階において回収不能な債権となっていたのであって、法基通9-6-2に照らしても,全額について「貸倒れ」が 認められるべきである。より具体的には、本件債権は平成8年3月期において、①合意により又は②社会通念上、弁済順序において「最劣後」のものとなっていたのであって、当時のJHL社の資産価値をどのように高く見積もるとしても、本件債権の全額が回収不能の状態にあったのである。
■本件閣議決定によって定められた損失負担の割合は、大蔵省及び農林水産省という行政機関たる「第三者」のあっせん・仲介によって合意され成 立したものであるから、法基通9-6-1(3)にいう「協議決定」にあたり、 その内容も住専設立以来の経緯を反映している点で同通達にいう「合理的な 基準」に該当するから同通達によって本件債権の全額について「貸倒れ」が 認められるべきである。
■JHL社は平成5年3月期以降、同8年3月期に至るまで相当の期間 大幅な債務超過状態を継続し、遂に事業を閉鎖したのであり、本件債権の全 額について「書面による債務免除」が行われている以上、法基通9-6-1 (4)に照らしても、本件債権の全額について「貸倒れ」が認められるべきで ある。 また、私法上、解除条件付債権放棄(債務免除)の効力が意思表示の時点 で生じることは疑う余地がない。
■本件債権放棄は、本件閣議決定及び大蔵省からの強い指導に従って行われたものであり、原告にとっても、①金融システムの混乱の回避や、②母体行に対するさらなる追加負担要求により被る損失を避けるべく実行されたものであって、まさに法基通9-4-1に例示されている「より大きな損失を避けるためにやむを得ず」行ったものに他ならないのである。
関連する条文
法人税法
22条(益金と損金)
内国法人の各事業年度の所得の金額は、当該事業年度の益金の額から当該事業年度の損金の額を控除した金額とする。
同条③
内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の損金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、次に掲げる額とする。
一 当該事業年度の収益に係る売上原価、完成工事原価その他これらに準ずる原価の額
二 前号に掲げるもののほか、当該事業年度の販売費、一般管理費その他の費用(償却費以外の費用で当該事業年度終了の日までに債務の確定しないものを除く。)の額
三 当該事業年度の損失の額で資本等取引以外の取引に係るもの
同条④
第二項に規定する当該事業年度の収益の額及び前項各号に掲げる額は、別段の定めがあるものを除き、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従つて計算されるものとする。
37条(寄附金の損金不算入)
内国法人が各事業年度において支出した寄附金の額(次項の規定の適用を受ける寄附金の額を除く。)の合計額のうち、その内国法人の当該事業年度終了の時の資本金の額及び資本準備金の額の合計額若しくは出資金の額又は当該事業年度の所得の金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額を超える部分の金額は、当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
同条②
内国法人が各事業年度において当該内国法人との間に完全支配関係(法人による完全支配関係に限る。)がある他の内国法人に対して支出した寄附金の額(第二十五条の二(受贈益)の規定の適用がないものとした場合に当該他の内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入される同条第二項に規定する受贈益の額に対応するものに限る。)は、当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
法人税法基本通達
9-6-1(金銭債権の全部又は一部の切捨てをした場合の貸倒れ)
法人の有する金銭債権について次に掲げる事実が発生した場合には、その金銭債権の額のうち次に掲げる金額は、その事実の発生した日の属する事業年度において貸倒れとして損金の額に算入する。(昭55年直法2-15「十五」、平10年課法2-7「十三」、平11年課法2-9「十四」、平12年課法2-19 「十四」、平16年課法2-14「十一」、平17年課法2-14「十二」、平19年課法2-3「二十五」、平22年課法2-1「二十一」により改正)
(1) 更生計画認可の決定又は再生計画認可の決定があった場合において、これらの決定により切り捨てられることとなった部分の金額
(2) 特別清算に係る協定の認可の決定があった場合において、この決定により切り捨てられることとなった部分の金額
(3) 法令の規定による整理手続によらない関係者の協議決定で次に掲げるものにより切り捨てられることとなった部分の金額
イ 債権者集会の協議決定で合理的な基準により債務者の負債整理を定めているもの
ロ 行政機関又は金融機関その他の第三者のあっせんによる当事者間の協議により締結された契約でその内容がイに準ずるもの
(4) 債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、その金銭債権の弁済を受けることができないと認められる場合において、その債務者に対し書面により明らかにされた債務免除額
9-6-2(回収不能の金銭債権の貸倒れ)
法人の有する金銭債権につき、その債務者の資産状況、支払能力等からみてその全額が回収できないことが明らかになった場合には、その明らかになった事業年度において貸倒れとして損金経理をすることができる。この場合において、当該金銭債権について担保物があるときは、その担保物を処分した後でなければ貸倒れとして損金経理をすることはできないものとする。(昭55年直法2-15「十五」、平10年課法2-7「十三」により改正)(注) 保証債務は、現実にこれを履行した後でなければ貸倒れの対象にすることはできないことに留意する。
9-6-3 (一定期間取引停止後弁済がない場合等の貸倒れ)
債務者について次に掲げる事実が発生した場合には、その債務者に対して有する売掛債権(売掛金、未収請負金その他これらに準ずる債権をいい、貸付金その他これに準ずる債権を含まない。以下9-6-3において同じ。)について法人が当該売掛債権の額から備忘価額を控除した残額を貸倒れとして損金経理をしたときは、これを認める。(昭46年直審(法)20「6」、昭55年直法2-15「十五」により改正)
(1) 債務者との取引を停止した時(最後の弁済期又は最後の弁済の時が当該停止をした時以後である場合には、これらのうち最も遅い時)以後1年以上経過した場合(当該売掛債権について担保物のある場合を除く。)
(2) 法人が同一地域の債務者について有する当該売掛債権の総額がその取立てのために要する旅費その他の費用に満たない場合において、当該債務者に対し支払を督促したにもかかわらず弁済がないとき
(注) (1)の取引の停止は、継続的な取引を行っていた債務者につきその資産状況、支払能力等が悪化したためその後の取引を停止するに至った場合をいうのであるから、例えば不動産取引のようにたまたま取引を行った債務者に対して有する当該取引に係る売掛債権については、この取扱いの適用はない。
9-4-1(子会社等を整理する場合の損失負担等)
法人がその子会社等の解散、経営権の譲渡等に伴い当該子会社等のために債務の引受けその他の損失負担又は債権放棄等(以下9-4-1において「損失負担等」という。)をした場合において、その損失負担等をしなければ今後より大きな損失を蒙ることになることが社会通念上明らかであると認められるためやむを得ずその損失負担等をするに至った等そのことについて相当な理由があると認められるときは、その損失負担等により供与する経済的利益の額は、寄附金の額に該当しないものとする。(昭55年直法2-8「三十三」により追加、平10年課法2-6により改正)
(注) 子会社等には、当該法人と資本関係を有する者のほか、取引関係、人的関係、資金関係等において事業関連性を有する者が含まれる。
東京地裁/平成13年3月2日判決(藤山雅行裁判長)/(全部取り消し)(納税者勝訴)(被告控訴)
発起人が引き受けた80万株の内訳は、本件母体5社がそれぞれ15万9000株(引受価額各7950万円)、壬が3000株(引受価額150万円)、癸及び〈I〉がそれぞれ1000株(引受価額各50万円)である。
Bは、右のとおり住専の一社として設立されたものであり、広義での貸金業を営むことを目的とするものであるが、その設立当時には貸金業の規制等に関する法律は制定されておらず、出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律(昭和58年法律第32号による改正前のもの)7条及び8条により大蔵大臣の監督を受けており、貸金業の規制等に関する法律制定後も同法の規制の対象とはならず(同法2条1項5号、同法施行令1条4号)、同法附則9条により、従来どおり大蔵大臣の監督を受けることとされ、一般の貸金業者とは異なった取扱いを受けている。”

ただし、本件母体五社と関係の深い会社を含めた原告グループ(原告、V株式会社、W株式会社、Y証券株式会社、Z証券株式会社、a証券株式会社、b証券株式会社、c証券株式会社及びd証券株式会社)、E銀行グループ(E銀行、e株式会社、f株式会社及びg証券株式会社)、F証券グループ(F証券、h株式会社、i株式会社及びj証券株式会社)、G証券グループ(G証券、l株式会社、m証券株式会社、n証券株式会社及びo証券株式会社)及びH証券グループ(H証券、p株式会社、q証券株式会社及びr証券株式会社)のBに対する出資比率(百分率)は、以下のとおりであった。”

Bに対しては、本件母体五社がそれぞれ役員及び従業員を派遣していた。
Bの従業員数は、男子が16名ないし249名(平均約174.4名)、女子が11名ないし236名(平均約162.7名)、総従業員数が27名ないし465名(平均約337.1名)であったところ、本件母体五社は、Bに対し、設立時から解散に至るまで、15名ないし52名の男子従業員を出向させており、その内訳は、原告が、4名ないし30名(平均約13.2名)、E銀が5名ないし13名(平均約9名)、F証券が2名ないし6名(平均約4.6名)、G証券は1名ないし5名(ただし、平成7年9月以降はなし。平均約3.6名)、H証券が1名ないし6名(平均約4.1名)となっていた。”
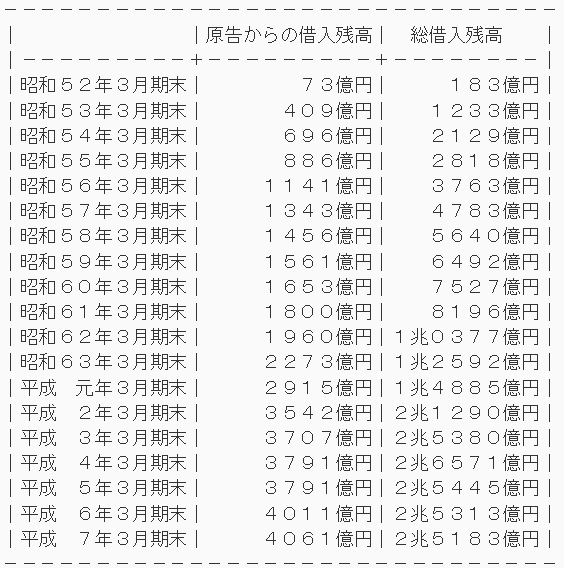
“Bは、設立初年度である昭和52年3月末現在において、生命保険会社15社(合計約25億円)、損害保険会社19社(合計約10億円)及び信託銀行2行(合計約3億円)から、総額約38億円の融資を受け、その後も母体行以外の金融機関からの借入れを拡大していった。
右のような非母体金融機関からのBへの融資については、融資開始当初から、融資が系統によるものであるか系統以外の非母体金融機関(以下、当該住専との関係で「一般行」という。)であるかを問わず、Bの母体行である原告及びE銀行が原則として各50パーセントの分担率により、一律にその返済を保証していた。”
“なお、昭和57年法律第77号による改正前の農業協同組合法10条8項及び9項(現行の10条19項及び22項)は、農業協同組合及び農業協同組合連合会に対して、原則として組合員以外に対する資金の貸付を組合員に対する貸付の5分の1以内に限定しつつ、「銀行その他の金融機関に対する資金の貸付」等については例外的に組合員のためにする事業の遂行を妨げない限度において右の規制を適用しないこととしていたが、住専は、昭和55年に右にいう「その他の金融機関」に指定され、これにより、R農業協同組合連合会等による住専に対する貸付が右の規制の適用を受けず原則として自由に行えることとなった〔昭和55年10月16日大蔵省銀行局長通達(蔵銀第2533号)、同日農林水産省経済局長通達(農経A第1435号)〕。
また、平成4年法律第87号による改正前の農業協同組合法10条の5(現行の11条の7)及び「農業協同組合及び農業協同組合連合会の共済事業に係る財産の運用方法を定める省令」3条は、T農業協同組合連合会及びS農業協同組合連合会の財産の運用方法を原則として金融機関に対する貸付等に限定しつつ、金融機関等以外の法人に対する貸付については農林水産大臣が指定する債権を担保とするものや金融機関によって保証されることとなっているもの等に限り例外的に認めることとしていたが、昭和56年に、右の規制の例外として認められる農林水産大臣が指定する債権を担保とする金融機関等以外の法人に対する貸付として、貸付対象法人が締結した金銭消費貸借契約に基づく住宅ローン債権を担保とする住専に対する貸付が指定され、これにより、住専に対する貸付については、その住宅ローン債権を担保とする限り、金融機関による保証なしでも自由に行えることとなった〔昭和56年12月28日農林水産省事務次官依命通達(農経A第1508号)、同日同省経済局長通達(農経A第1511号)〕。
このような規制の緩和に伴い、系統のBに対する融資も順調に拡大していくこととなった。”
右通達は、「金融機関の債務保証のあり方については、従来より、その適正を期するよう指導してきたところであるが、最近、一部の金融機関において、安易な債務保証を行った結果、経営の健全性を著しく損ねた事例が見受けられた。」「ついては、このような事例にもかえりみ、この際、債務保証のあり方について、下記の点に一段と配慮され万全を期されたい。」とした上で、「1 債務保証を行うに際しては、債務者に対する事前審査を十分に行い、いやしくも債務保証が安易に流れることのないよう配慮すること。」、「2 債務保証については、その量が過大になることのないように配慮し、例えば、預金・貸出金等との適正な均衡を保持するよう努めること。」、「3 他の金融機関の保証を得て貸出金を実行する場合にも、通常の貸出金を実行する場合に準じた審査、管理体制を保持するよう配意すること。」とした。”

集合債権譲渡担保の準共有持分権保有方式の契約は、昭和55年2月29日、まず、母体行である原告及びE銀行を含むBに対して融資をしている金融機関(ただし、T農業協同組合連合会及びS農業協同組合連合会を除く。)68社(以下「原協定参加者」という。)とBとの間で、Bが原協定参加者に対して現在並びに将来負担する一切の債務の担保として、Bが現に有し並びに将来取得する住宅ローン債権並びにこれに付帯する一切の債権を原協定参加者に対して譲渡し、原協定参加者が右の集合債権譲渡担保を準共有によって取得するとの契約(以下「第一次債権譲渡担保契約」という。)を原告が原協定参加者を代理する形で締結し、次に、原告を除く原協定参加者の代理人であるE銀行、協定幹事である原告及びBの三者間で、第一次債権譲渡担保契約により取得した集合債権譲渡担保を原協定参加者の間で準共有する旨を定める「担保に関する協定書」をそれぞれ締結することによって実現された(以下、この「担保に関する協定書」を「第一次担保協定」といい、第一次債権譲渡担保契約及び第一次担保協定により形成された集合債権譲渡担保の準共有持分権を取得するというスキームを「第一次担保協定スキーム」という。)。”
“これ以降の原協定参加者からのBに対する融資に関しては、集合債権譲渡担保の準共有持分権保有方式が適用されることとなり、それ以前の母体行の保証の下で行われた個別の貸出については、そのそれぞれの満期到来とともに順次いったん弁済がされた結果、母体行による保証は順次解消され、昭和62年3月ころまでには、原協定参加者のBに対する融資に係る母体行による保証は集合債権譲渡担保の準共有持分権保有方式へと切り替わり、消滅した。なお、第一次担保協定スキームが成立した後、前記(一)のとおり、昭和56年にT農業協同組合連合会及びS農業協同組合連合会についても住専に対して住宅ローン債権を担保として行う貸付が認められたことから、T農業協同組合連合会及び各S農業協同組合連合会が順次これに加入したほか、いくつかの金融機関が第一次担保協定スキームに加わった。”
“その後、第一次担保協定スキームへの追加的参加者が増加したことから、平成2年11月30日に、母体行である原告及びE銀行を含むBに対して融資をしている金融機関168社(以下「第二次協定参加者」という。)とBとの間で、原告が第二次協定参加者を代理する形で、第一次債権譲渡担保契約とほぼ同内容の契約(以下「第二次債権譲渡担保契約」という。)が締結され、さらに、同日、原告を除く第二次協定参加者の代理人であるE銀行、協定幹事である原告及びBの三者間において、第一次担保協定とほぼ同内容の「担保に関する協定書」が締結された(以下、この「担保に関する協定書」を「第二次担保協定」といい、第二次債権譲渡担保契約と第二次担保協定により形成された集合債権譲渡担保の準共有持分権を取得するというスキームを「第二次担保協定スキーム」という。)。さらにその後、平成3年3月18日、Bに対して新たに融資をすることとなった非母体金融機関28社が第二次担保協定スキームに追加的に加入した。”
その結果、貸付資金の調達を銀行等の民間金融機関からの借入れに依存するとともに営業店舗数も限られていた住専各社は、金利及び営業力の両面において競争力を欠くに至り、優良顧客を借入金利がより低い住宅金融公庫や都銀等に奪われた。その結果、住専八社の個人向住宅信用供与残高(住専各社の合計額)は、昭和60年度まで拡大を続け3兆5073億円(銀行等を含めた全体に占める割合5.2パーセント)にまで達していたが、昭和61年度から平成6年度にかけて、3兆0577億円(同4.2パーセント)、2兆7026億円(同3.4パーセント)、2兆5042億円(同2.8パーセント)、2兆6433億円(同2.7パーセント)、2兆8429億円(同2.6パーセント)、2兆8440億円(同2.4パーセント)、2兆6990億円(同2.2パーセント)、2兆5551億円(同1.9パーセント)、2兆4025億円(同1.7パーセント)へと、低下に転じた。”
“このような状況から、住専各社は、不動産会社等の事業者向け融資を拡大し始め、昭和50年度には29億円、昭和55年度には1804億円であった住専八社の事業向け融資残高は、昭和60年度には1兆8662億円、昭和61年度には2兆9549億円、昭和62年度には4兆2358億円、昭和63年度には5兆3619億円、平成元年度には8兆1183億円、平成2年度には10兆2336億円、平成3年度には10兆1456億円へと増加した。”
“このように、平成2年度末には、事業者向け融資の残高が前年度末に比べて2兆円余りも増加しているが、このころは地価が全国的にみてピークに達しようとしている時期に当たる。
大蔵省銀行局においては、それ以前にも金融機関に対して投機的土地取引等に係る融資を厳に排除するよう求めていたが、同年3月27日付けで各金融機関代表者に宛てて「土地関連融資の抑制について」と題する局長通達(蔵銀第555号)を発し、当面、不動産業向け貸出については、その増勢を総貸出の増勢以下に抑制することを目途とすること、及び不動産業、建設業及びノンバンクの三業種に対する融資の実行状況を報告することを傘下の金融機関に周知徹底するように求めた。このいわゆる総量規制によって、一般金融機関については不動産業向け融資の増加が抑制されたが、右通達の対象外であった住専は引き続き事業者向け融資を拡大していたのである。また、系統の住専向け融資額は、平成2年3月末に2兆9025億円であったものが、平成3年3月末には4兆8597億円と大幅に増加しており、これらは住専の事業者向け融資の原資に充てられたこととなる。”
“その後、いわゆるバブル経済が崩壊し、株価が下落するとともに地価が下落し、地価は平成3年を頂点に大幅に下落(例えば、平成4年ないし6年の地価下落率は、東京都区部の住宅地においてそれぞれ13.3パーセント、22.2パーセント、14.6パーセントであり、東京都区部の商業地においてそれぞれ8.7パーセント、22.5パーセント、23.7パーセントであった。)した。
右のバブル経済崩壊による地価の下落は、不動産担保融資を主体としていた住専各社の経営に深刻な影響を与え、特に急激に拡大していた事業者向け融資債権の不良債権化をもたらし、平成3年度以降、住専各社の財務状況は急激に悪化することとなった。
“Bにおいても、他の住専各社と同様、都銀等が個人向けローンに力を入れるようになり、優良顧客を住宅金融公庫や都銀等に奪われたため、不動産会社等の事業者向け融資を拡大し始めた。具体的には、Bの個人住宅向け融資残高は、昭和55年度末に3450億円、昭和60年度末に5658億円、昭和61年度末に4992億円、昭和62年度末に4400億円、昭和63年度末に4569億円、平成元年度末に5402億円、平成2年度末に6444億円、平成3年度末に7150億円、平成4年度末に7325億円、平成5年度末に7095億円、平成6年度末に6624億円であって、民間金融機関全体及び公的機関の合計残高が昭和55年度に45兆1512億円から一貫して増加し、平成6年度には141兆8245億円に達していることと比較して伸び悩んでいた。”
“また、Bは、昭和62年10月8日に貸出業務に関する専決権限規定を改定し、住宅ローン以外の事業ローンについて、それまで1年超の中長期ローンの与信残高基準を営業所長1500万円以下、部店長及び特定営業所長2000万円以下、業務部担当役員3000万円以下、常務会3000万円超とし、1年以内の短期ローンの与信残高基準を部店長及び特定営業所長5000万円以下、業務部担当役員1億円以下、常務会1億円超・新規取引先としていたものを、中長期・短期の区分を撤廃し、不動産会社に対するローンの与信残高基準は部店長1億円以下、部店担当役員2億円以下、常務会2億円超・新規取引先とし、不動産会社以外に対するローンの与信残高基準は部店長5000万円以下、部店担当役員1億円以下、常務会1億円超・新規取引先とした。”
“さらに、平成元年11月1日にも同様の改定を行い、法人貸出については、一般事業法人と不動産会社を分け、一般事業法人に対する融資の与信残高基準を部店長1億円以下、部店担当役員2億円以下、常務会2億円超とし、不動産会社については、さらに拠点会社、戦略会社、育成会社、その他の不動産会社に分類した上で、貸出残高が100億円を超えることなどから取引防衛上特別対策が必要な取引先である拠点会社(平成元年12月22日に21社が認定され、平成2年5月1日に更新されて22社となった。)及び貸出残高が50億円を超えることなどから残高の維持拡大を図るべき取引先である拠点会社(平成元年12月22日に52社が認定され、平成2年5月1日に更新されて43社となった。)については、それぞれ承諾額基準を一般事業法人よりも大幅に緩和した。”
“その結果、Bの事業向け融資残高は、昭和55年度末に4億円であったものが昭和60年度末に1288億円、昭和61年度末に3555億円、昭和62年度末に6313億円、昭和63年度末に8640億円、平成元年度末に1兆3285億円、平成2年度末に1兆6533億円へと増加した。”
“その後のいわゆるバブル経済の崩壊により、Bの平成3年11月末の時点での要管理債権は総額1兆2482億円であり、総貸出債権2兆4028億円の約52.0パーセントを占めることとなった。
また、平成4年8月31日現在をもって調査した大蔵省銀行局の第一次立入調査の結果、総貸付金残高2兆3638億円のうち分類額(不良債権額)は1兆2694億円で分類率53.7パーセントであることが明らかとなった。”
“なお、大蔵省銀行局長からBに対して発せられた第一次立入調査の調査報告書によると、貸付金の分類率(不良債権率)が高率となったのは、Bが業務の多角化を図るため、地場不動産業者等と合弁会社(5社)を設立するなど、不動産業者に積極的に資金を融資したが、バブル崩壊により購入物件が販売不振に陥ったこと及び借入過多により債務者の資金繰りがつかなくなったこと等が原因と考えられるとされている。平成2年度には35億6800万円あったBの税引前当期利益が平成3年度には5億2400万円へと減少し、さらに、平成4年度、平成5年度には、それぞれ150億2700万円、71億3000万円の税引前当期損失を計上するに至った。”
“Bにおける第一次再建計画の策定(1) 主要勘定残高を次のとおり推移させ、資産の圧縮を行う。
(2) 本件母体五社及び非母体金融機関に次のとおり支援を要請する。
イ 非母体金融機関に、第一次再建計画の計画期間中の融資残高維持

ア 管理回収業務及び不動産売却あっせん業務の強化並びに取引先不
“第一次再建計画を策定する前後から、住専問題の深刻度が徐々に認識され、一般行及び系統からのBに対する融資の回収ないし保全に向けた動きがみられた。
系統は、福井県R農業協同組合連合会が平成4年5月19日にBに対する融資の5月分の借替えについて難色を示し、千葉県R農業協同組合連合会は同日にBの支援の主体は原告になることを前提として原告が支援する旨の文書を要求し、東京都R農業協同組合連合会は同月20日に融資残高の維持については承諾できるとしたものの残り40億円ある第二次担保協定スキームに係る譲渡担保の対象外とされている短期貸付金を期限時に同譲渡担保の対象となる中期貸付金に転換してほしい旨要請し、T農業協同組合連合会は同月25日に①第一次再建計画の期間中母体による支援のみで金利減免等はそれ以外の金融機関に及ぼさないこと、②計画通り行った場合の借入金圧縮方法は母体以外を圧縮対象として、例えばシェア割等で行うこと、③第二次担保協定スキームに係る譲渡担保について担保割れが生じた場合は母体行が一部を放棄して担保割れとならないようにすることを確認するように要請するなどBに対する融資について回収ないし保全措置を求める姿勢をとった。”
このとき、Q金庫側は、面談内容を書面にするように求めたが、原告側がこれを拒否し、Q金庫側が、代替案として、Bとの間で書面にすると提案したところ、原告側はBとQ金庫の関係で行うことであればBの〈J〉社長と相談されたいと答えたため、Bは、Q金庫に対し、同年8月5日付けで、「今般、貴金庫から改めて、弊社に対する母体支援についてお問い合わせをいただきましたが、先に弊社母体A銀行が母体として弊社を支援する立場を改めて表明しましたように、弊社は、A銀行をはじめ母体各社から母体としての責任あるご支援についてご同意をいただいており、現に実施もされております。今後諸般の事情により母体以外の金融機関のご支援をいただかなければならないような事態に至った場合でも、お取り引き金融機関それぞれの立場を良く認識し、誠意を持ってご相談しながら対応する所存でございますので何卒よろしくお願い申し上げます。」などとする書簡を差し出した。”
“Bは、第一次再建計画において、右(二)(2)のとおり本件母体五社に対する支援を要請することとしていた。そこで、原告は、Bの第一次再建計画の推進を支援するために、独自に①緊急融資枠1000億円の設定、②住宅抵当証券取得限度枠400億円の設定、③公定歩合(3.25パーセント)までの金利の減免からなる対応策を策定した上、さらに内部において支援策を作成してBに示し、Bは、これに基づいて、同年8月、原告とともにBの母体銀行であったE銀行との間で、①本件母体五社がBの第一次再建計画の円滑な遂行を図るため人的支援、担保物件流動化のための協力を行い、また、非母体金融機関からの借入金の残高を維持するために必要な協力を行うことを主な内容とする覚書を調印すること、②平成4年上期の金利について公定歩合(年3.25パーセント)まで減免し、同期中に実質26億円の支援を行うこと、③つなぎ資金として700億円を限度に融資を行うこと、④債権譲渡担保の対象となっているBに対する長期貸付の一部を債権譲渡担保の対象とならない短期貸付に振り替えることの四点について交渉を行った。”
“これに対して、E銀行は、当時、自社の直系ノンバンク三社に対する支援に精力を傾注している最中であり、Bの内容は直系ノンバンクよりも悪いと見受けられるのに母体行であるとして無制限の支援を求められるとE銀行自体がもたないとして、支援の内容について何らかの歯止めが必要であるとの考えを示し、右②について平成4年上期についてのみ公定歩合までの金利軽減を実施する、右③について平成4年下期で100億円を限度に協力をする、右④の短期貸付への振替えには長期貸付のうち弁済期を迎えたものについて応ずるとしたものの、右①の覚書の締結については、自社関連ノンバンク三社について他の金融機関に対して金利減免を要請していることと矛盾するおそれがあるとして、覚書の締結を拒絶した。”
“さらに、本件母体二行は、平成4年3月から平成5年4月にかけて、系統がBに対して有する貸付期間1年以内の短期貸付金(第二次担保協定スキームに係る譲渡担保の対象外とされているもの)を同1年超の中長期債権(第二次担保協定スキームに係る譲渡担保の対象とされているもの)に振り替えると同時に、それと入れ替える形で、本件母体二行が有する中長期債権を短期債権に振り替えることを行い、平成4年3月末に系統が有していた707億8100万円の短期債権は、平成5年4月末までにすべて中長期債権に振り替えられた。”
“第一次再建計画の策定以後、不動産市況が一向に回復しなかったことなどから、住専各社の経営環境はより一層悪化し、すでに平成4年6月にはIが新たな再建計画を母体行に示すなど、住専各社は、新たな再建計画の策定を模索し始め、(一)のとおり、Iがまず第二次再建計画を策定し、これをモデルとして他の住専各社においても同様の第二次再建計画(Bにおける本件新事業計画)が策定されるに至った。”
“なお、住専各社の第二次再建計画の策定が模索され始めたころである平成4年8月30日に、当時の〈u〉総理大臣は、自由民主党のセミナーで講演し、金融機関が中心となって設立する担保不動産の買い上げ会社構想について、必要であれば公的援助をすることにやぶさかでないと発言し、これが報道されたところ、当時の〈P〉経団連会長から、「銀行がやったことのつけを公的資金で助けるのですか。これについては銀行以外の製造業などの産業界に強い不満があります。」との発言があるなど産業界等から強い反発があり、このときの公的資金導入の議論は立ち消えに終わった。”
“Iの平成4年度の最終赤字はこれまでの見込みの200億円から350億円程度に拡大する見通しであるとの報道が平成4年10月14日にされたが、住専各社においては非母体金融機関、とりわけ系統からの借入の割合が大きいことから(甲23の1ないし3)、従前の再建計画のような母体行のみの金利減免によっては負担軽減の程度が低く、もはや経営の再建ができなくなるとして、大蔵省は、平成4年12月7日に、Bを含む住専七社の代表者を呼び、Iを先頭バッターにして各住専で新たな再建計画を立案しなければならない旨指導をした。しかし、非母体金融機関にも負担を求める案を母体行のみで取りまとめるのは難しいことから、結局、大蔵省が再建計画の骨格を示し関係金融機関の協力を得ることとなり、系統との関係ではその監督官庁である農林水産省を通じ、各金融機関の金利を母体行は0パーセント、一般行は2.5パーセント、系統は4.5パーセントに減免するとの案を提示するなどして折衝した。”
“この案は、金利減免によって住専七社に年間約4210億円の支援を行おうとするものであって、母体行のみならず、一般行及び系統(系統の金利減免額は年間約840億円に達する。)にも住専救済のための負担の分担を求めるものであるが、少なくとも当時まで金融業界においては、ノンバンクの破綻処理に当たっては設立母体となった金融機関が体力の許す限り支援し、他の債権者には極力負担を求めないというのが常識とされていたことに加え、系統としては、第一次再建計画に応じて残高を維持する際に、母体行が責任を持って再建を行い、系統にはそれ以上の負担を求めないことが約されたものと理解していたことから、農林水産省とともに厳しく反発した。このように交渉は難航したが、系統も、最終的には母体行が責任を持って再建計画に対応することが明確になり、債権の元本が回収できるならば、金融システム安定の観点から再建計画に協力し、金利減免に応ずるとの態度をとった。”
“その結果、大蔵省と農林水産省は、乙銀行局長と丙経済局長との間で、平成5年2月3日、住専各社の再建支援について以下のアないしウのとおりそれぞれ誠意を持って当事者間の協議が円滑に行われるよう対処していくものとする覚書(大蔵・農水覚書)を締結した。このうち、ア①かっこ書の趣旨は、系統の債権の元本を保証しようというものであることについては、両省共通の認識であった。
ア 母体金融機関に次の点を文書により確約させること。
“Iの第二次再建計画は、大蔵省案に従って、平成5年2月24日及び同月26日に開催された同社の母体行会議において、母体行間の合意が成立したが、その概要は以下のとおりである。
原告は、平成5年6月30日、Iの一般行として、Iの第二次再建計画の一般行に係る支援内容に対して同意し、そのころ、Iは、ほぼすべての金融機関からの同意を取り付けて、Iの第二次再建計画が実施されるに至った。”
“大蔵省は、平成4年10月にBに対し第一次立入調査を行ったが、原告も、B作成の平成4年11月12日付けの「当社の現状と今後の課題(ディスカッション・ペーパー)」と題する報告書の提出を受け、Bの財務内容の解明を開始した(甲109)。右報告書は、平成4年9月末現在で、総与信残高2兆5776億円の約65パーセントに及ぶ1兆6854億円が要管理債権であり、約52パーセントに及ぶ1兆3560億円が問題債権であるとし、また、同年7月末において資産合計2兆5318億円のうち評価損が6641億円発生しているとし、今後の課題として、落とし所を踏まえた母体での対応方針を策定する時期にあり、マル秘計画策定に着手の要があるとしている。”
“前記(一)(1)のとおり、大蔵省は、平成4年12月7日に、住専各社の代表者を呼び、Iを先頭バッターにして各住専で新たな再建計画を立案しなければならないと指導したが、その翌日である同月8日には、原告に対しても、Bの第二次再建計画を立案するように求めた。原告は、右のような報告書や前記3(一)、(二)記載の第一次立入調査の結果を踏まえ、Bの再建計画の策定を模索した。原告の〈O〉常務及び当時原告の住専問題を担当していた〈H〉常務(以下「〈H〉取締役」という。)は、大蔵省銀行局の戊審議官からの呼び出しを受けて、平成5年2月4日に戊審議官を訪ねたが、その際、戊審議官は、金利減免によるBの支援について系統を交渉のテーブルにつけるためには、①母体行の責任を明確にした文書を作成すること、②系統への優先弁済を認めることの二点が条件になっていると述べ、さらに、大蔵省としては、金利減免の内容を母体行0パーセント、一般行2.5パーセント、系統4.5パーセントで10年間の固定金利としたいと述べた。”
“これに対し、原告は、母体行の責任を明確にした文書を作成することについては、原告が有する貸出残高の範囲を超えて系統の債権の肩代りまで必要となる完全母体行責任につながりかねないとの懸念があったことから難色を示したが、大蔵省は、系統に右の金利減免による住専の支援策を飲ませるための政治的配慮として理解してほしいと説明した。
原告は、母体行として金利を0パーセントに減免すること及び系統に対して優先的に弁済を行うことについては承諾することとしたが、母体行の責任を明確にする文書の作成については、完全母体行責任につながる懸念が消えなかったことから、大蔵省とさらに協議を進めたものの、大蔵省の担当官から、「債権に対する母体行の系統への誠意という意味では、母体行の支援内容確認文書を出すことが必要になる。正式に署名したものではなく、ゴム印を押したものでも構わない。」と言われ、最終的に、本件母体五社の母体会議による承認を経てIの第二次再建計画とほぼ同内容の本件新事業計画(Bに係る第二次再建計画)の内容を固めた後の同年5月25日に、本件母体五社間で母体支援に関する「B株式会社支援について(確認)」と題する確認書を取り交わした上で、同日付けで大蔵省銀行局に対し、「B株式会社の再建計画について」と題するE銀行と連名の念書を差し入れ、本件証券母体三社も同日付けで同旨の念書を同省証券局に対し差し入れた。
本件母体五社間で取り交わされた右の確認書は、①本件母体二行は、Bの本件新事業計画に沿って、平成5年4月1日に遡ってBに対する貸出金の金利を10年間免除すること、Bが計画する第三者割当増資に応じ、それぞれ30億円を上限として増資の払込みに応ずること、本件新事業計画遂行上必要な資金について、本件母体二行合計600億円を上限として新規貸出を行う(母体ニューマネー)こと、②本件証券母体三社は、Bの本件新事業計画に沿って、Bが計画する第三者割当増資に応じ、それぞれ30億円を上限として増資の払込みに応ずること、Bが同社の営業貸付金の担保として徴求している不動産を本件証券母体三社若しくは本件証券母体三社のグループ関連会社を通じ、厳正かつ中立的な評価に基づく価格で、それぞれ70億円買い受けること、この場合、本件証券母体三社若しくは本件証券母体三社のグループ関連会社は、不動産買受資金をBより長期貸出最優遇金利にて借り受けるものとすること、本件新事業計画遂行上必要な資金について本件証券母体三社若しくは本件証券母体三社のグループ関連会社は合計200億円を限度として新規貸出を行うこと、右の新規貸出のおのおのの負担割合は、各母体グループがそれぞれ均等に負担するものとすることについて、本件母体五社間で合意に達したことを書面で確認するものである〔なお、その後、平成5年8月18日に、本件母体五社とBとにおいて、金利を免除する貸付金の範囲を特定するなど、支援内容をより明確化した「協調融資に関する協定書」、「支援に関する協定書」及び「支援に関する協定書に関する特約」が締結された〕。”
本件新事業計画は、計画期間を平成5年4月から平成15年3月までの10年間とし、その間本件母体五社及び非母体金融機関の支援を受けて経営の再建に取り組むというものである。本件新事業計画の概要、本件母体五社の支援内容及び非母体金融機関への依頼事項は以下のとおりである。

(3) 非母体金融機関への依頼事項
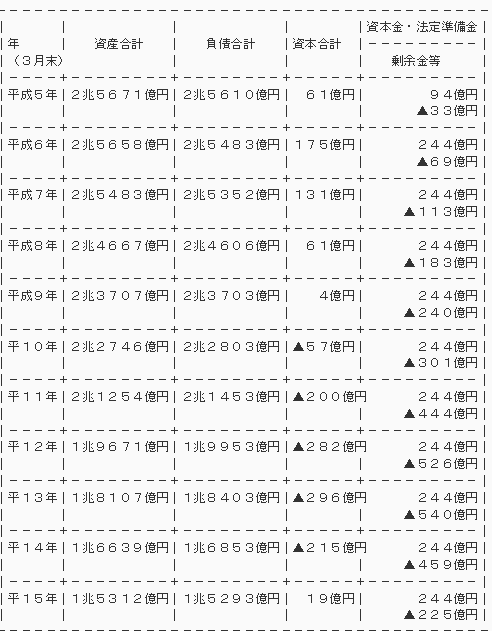
“本件新事業計画については、原告やBはもとより、系統及び一般行の間では、系統及び一般行が金利減免に応ずる代わりに、母体行は、事実上、自己の債権の最劣後化を認め、かつ系統の債権の元本金額の返済を保証したものと理解されていたが、系統及び一般行は、この点をより明確なものにするため、本件新事業計画策定の前後において、次のような動きに出た。まず、系統を構成するQ金庫、T農業協同組合連合会、静岡県R農業協同組合連合会などは、原告に対して、原告が責任を持ってBの再建を支援することを明確にする書面の提出を求め、原告は、これに応じて、Q金庫及び静岡県R農業協同組合連合会については平成5年6月1日付けで、また、T農業協同組合連合会については同月7日付けで、原告が本件母体五社とともに本件新事業計画に沿った支援を行うことを伝え、新事業計画に対する協力を要請する書面を提出した。”
“また、Bは、Q金庫からの要請に従って、同月29日、Bの本件新事業計画については、本件母体五社の了承を得ていること、本件母体五社は当局に対して「全関係金融機関一致しての支援を踏まえた上で、金融システム安定化の観点から再建計画に沿って責任を持って対処して参る所存」である旨の文書を提出していることなどを確認する文書を提出した。
他方、一般行としての立場にある損害保険会社協調融資団の幹事である〈Q〉保険会社は、同年11月12日に、Bに対して文書を提出し、金融機関の一員として、金融システムの維持の観点から本件新事業計画に協力することとしたこと、新事業計画は、同じ非母体金融機関としての立場にある系統との関係から公平を欠く内容であることを指摘した上で、本件新事業計画の内容は、損害保険業界としては受入れ可能な最大限の支援であって、B及び母体においては、最大限の努力により経営再建を行い、本件新事業計画以上の支援負担を要請することのないようにお願いしたいとした。”
“また、同様に、一般行としての立場にあるt銀行は、同年12月27日に本件新事業計画に係る同意書を提出する際に、Bの再建については、本来母体各社が責任を持って対処すべきものであり、Bの経営に関与していないt銀行としては、新事業計画に係る同意の要請を受ける立場にはないが、金融システムの維持という社会的な要請から、すべての取引金融機関の同意を前提に協力することとしたこと、本件新事業計画は母体各社の責任の下で遂行されるべきものであるから、将来にわたりt銀行は、元本の償却をはじめ追加的な負担には応じられないことを書面をもって通知した。”
“Bの財務状況本件新事業計画は、Bが新規に獲得できる正常債権の金利水準が本件新事業計画策定当時の水準である6.50パーセント(長期プライムレートの5.2パーセントとスプレッド1.3パーセントの合計)であること及び不動産市況が、本件新事業計画策定当時が底値で、当初3年間は回復せず、4年目から緩やかな回復基調にある(4年目以降年3パーセントの上昇を想定)ことを前提としていた。しかし、平成5年版土地白書(平成5年6月15日発行。)は地価はなお高い水準にあるとし、政府自体が地価をさらに引き下げる必要があるとの認識を示していたし、現実にも、例えば、東京圏の住宅地、商業地の地価の推移は、平成5年にマイナス14.6パーセント(住宅地)、マイナス19.0パーセント(商業地)、平成6年に7.8パーセント(住宅地)、マイナス18.3パーセント(商業地)、平成7年にマイナス2.9パーセント(住宅地)、マイナス15.4パーセント(商業地)とそれぞれ下落しているように、不動産市況は依然として大幅な下落を続けていることに加え、金利水準も低利で推移し、本件新事業計画の前提は客観的な情勢に合致しなかった。”
“貸借対照表の欠損金は、平成5年3月末において33億0800万円であったものが、平成6年3月末には104億6000万円、平成7年3月末には187億0100万円へと増加し、平成5年度に本件新事業計画に従って増資をしたにもかかわらず、資本合計は平成6年3月末に139億3600万円、平成7年3月末に56億9500万円であり、平成6年3月末、平成7年3月末の当期損失がそれぞれ71億5100万円、82億4000万円であることから、資本欠損に陥るおそれがあった(甲6の39)。平成6年度末にu信用組合とv信用組合が破綻し、平成7年夏にはU信用金庫やw銀行の破綻が表面化し、内外から日本の金融システムに対する不安が非常に高まった。”
“平成7年8月には、住専各社に対して大蔵省の立入調査(以下「第二次立入調査」という。)が行われ、その結果、平成7年6月30日を調査基準時とするBの資産残高は2兆5151億円で、分類額(不良債権額)は1兆8532億円、分類率は73.7パーセントに達し、そのうち第Ⅱ分類は2991億円、第Ⅲ分類は1953億円、第Ⅳ分類(含み損益を含む)は1兆3588億円であることが明らかとなった。”
“第二次立入調査は、住専各社に対して行われたが、その結果、住専七社の総資産に占める不良債権の割合が七割を超え、第Ⅲ分類及び第Ⅳ分類の債権の合計額は全体で7兆5000億円になることが判明した。当時、住専七社に対する貸出金残高は、母体行が3兆5000億円、一般行が3兆8000億円であったことから、仮に母体行及び一般行が住専に対して有している債権の全額を放棄したとしても、2000億円分が系統の債権にロスが生ずることが明らかとなった。”

“与党三党は、平成7年6月25日に与党PT(金融・証券プロジェクトチーム)を発足させ、関係金融機関からのヒアリングを行うなどしていたが、与党PTは、その結果に基づき同年9月14日付けで、住専関係各金融機関並びに住専各社は直ちに住専問題解決のための話合いを行い、早急に解決策を取りまとめること及び大蔵省と農林水産省は、右の解決策のとりまとめのために責任ある行動を取ること、との勧告を出した。
また、金融制度調査会金融システム安定化委員会は、同月27日付けの審議経過報告で、住専問題に触れ、住専の問題は、その抱える不良債権が極めて多額であり、また関係する金融機関が多数に上ることから、金融システム全体の安定性に与える影響も大きく、現在の不良債権問題の中で、象徴的かつ緊要な問題となっているとした上で、住専自身及び母体行が主体的役割を果たし、今後の基本的な方針や債権の処理の仕方等につき合意形成を行うことが必要であること、行政当局は当事者間における議論を踏まえつつ、個別住専を超えた全体的枠組みの整備についての検討を並行して進め、適時に当事者間の合意形成を促進する必要があること、住専問題の早急な解決は、国内外から要請されているところであり、本年末までに処理策が策定されるよう、すべての関係者が強い決意をもって取り組むことが必要であることを報告している。”
“さらに、大蔵省も、同日、「金融機関の不良債権の早期処理について」を公表し、住専について、当事者による真剣な取り組みをしょうようするとともに、不良債権等の受け皿となる機関等について検討を行い、年内に処理方策を固めるとした。右のような状況を受けて、本件母体五社は、平成7年9月22日、母体会議を開催し、本件新事業計画と対比する形でBの実態の報告、第二次立入調査の報告がされた後、原告の〈R〉融資第二部長から、Bの進む方向は基本的には整理の方向であるとの認識を示し、意見を求めたところ、E銀行及び本件証券母体三社からは異論がなく、本件母体五社間でBを整理する方針が確認された。同年10月2日には、住専七社及びその母体行は、与党PTに対して、住専の再建を断念し、整理・清算する方針を伝えた。”
“本件母体五社で確認された整理の方針に従って、平成7年9月27日以降同年11月にかけて、Bの整理に向けての系統との協議が五回にわたって開催された。同年9月27日の第一回目の協議は、大蔵省銀行局中小金融課金融会社室(以下「金融会社室」という。)からの要請に基づいて開催されたもので、系統との協議については、全般的に金融会社室との事前・事後のすりあわせの下に行われた。第一回の協議は、同月25日及び同月26日の金融会社室との事前折衝を経て行われた。第一回の協議には、原告、E銀行及びBが参加し、系統側は、Q金庫、T共済農業協同組合連合会及び静岡県・北海道・東京都・兵庫県の各R農業協同組合連合会が参加した。第一回の協議においては、Bの〈J〉社長がBの現状等を説明し、系統の債権の担保となっているBの営業貸付金の状態が極めて悪化しており、系統の債権全額の弁済さえ危ぶまれる状況にあることを説明し、原告の〈H〉取締役が、Bは整理するとの結論になる旨を伝えた。これに対して、系統側は、すぐには了承せず、Bの実態に関する個別質疑や責任分担に踏み込んだ議論は次回以降に持ち越しとなった。”
“平成7年10月13日、同月31日及び同年11月16日に、第二回ないし第四回の協議が行われ、第一回と同様、B、本件母体二行及びQ金庫・静岡県R農業協同組合連合会をはじめとする中核的な系統関係者が参加し、第二回及び第三回協議には全国R農業協同組合連合会協会、第四回には愛知県R農業協同組合連合会も参加した。第二回の協議において、全国R農業協同組合連合会協会の〈S〉専務理事と静岡県R農業協同組合連合会の〈T〉専務理事から、新事業計画成立時に、原告とBとの関係は単なる株主と子会社ではないことを原告自身も認め、母体責任を確認したので系統側はBの再建に協力したという経緯があるのだから、母体行としての認識をきちんともってもらいたい旨の発言がなされ、第三回の協議において、右の〈T〉専務理事が、同年9月末に原告が母体ニューマネーを回収したことに関連して、Bを整理することになった場合でも、従前の系統への優先弁済は存続しているはずである旨の発言がなされ、また、第四回の協議においても、Q金庫の〈R〉副理事長が、住専の経営悪化の原因について考えると責任は住専と母体に極めて重いものがあると発言するなど、系統との協議においては、原告の母体行としての責任を追及する発言がみられた。”
“貸借対照表の欠損金は、平成5年3月末において33億0800万円であったものが、平成6年3月末には104億6000万円、平成7年3月末には187億0100万円へと増加し、平成5年度に本件新事業計画に従って増資をしたにもかかわらず、資本合計は平成6年3月末に139億3600万円、平成7年3月末に56億9500万円であり、平成6年3月末、平成7年3月末の当期損失がそれぞれ71億5100万円、82億4000万円であることから、資本欠損に陥るおそれがあった(甲6の39)。平成6年度末にu信用組合とv信用組合が破綻し、平成7年夏にはU信用金庫やw銀行の破綻が表面化し、内外から日本の金融システムに対する不安が非常に高まった。”
“平成7年8月には、住専各社に対して大蔵省の立入調査(以下「第二次立入調査」という。)が行われ、その結果、平成7年6月30日を調査基準時とするBの資産残高は2兆5151億円で、分類額(不良債権額)は1兆8532億円、分類率は73.7パーセントに達し、そのうち第Ⅱ分類は2991億円、第Ⅲ分類は1953億円、第Ⅳ分類(含み損益を含む)は1兆3588億円であることが明らかとなった。
第二次立入調査は、住専各社に対して行われたが、その結果、住専七社の総資産に占める不良債権の割合が七割を超え、第Ⅲ分類及び第Ⅳ分類の債権の合計額は全体で7兆5000億円になることが判明した。当時、住専七社に対する貸出金残高は、母体行が3兆5000億円、一般行が3兆8000億円であったことから、仮に母体行及び一般行が住専に対して有している債権の全額を放棄したとしても、2000億円分が系統の債権にロスが生ずることが明らかとなった。”
“与党三党は、平成7年6月25日に与党PT(金融・証券プロジェクトチーム)を発足させ、関係金融機関からのヒアリングを行うなどしていたが、与党PTは、その結果に基づき同年9月14日付けで、住専関係各金融機関並びに住専各社は直ちに住専問題解決のための話合いを行い、早急に解決策を取りまとめること及び大蔵省と農林水産省は、右の解決策のとりまとめのために責任ある行動を取ること、との勧告を出した。
また、金融制度調査会金融システム安定化委員会は、同月27日付けの審議経過報告で、住専問題に触れ、住専の問題は、その抱える不良債権が極めて多額であり、また関係する金融機関が多数に上ることから、金融システム全体の安定性に与える影響も大きく、現在の不良債権問題の中で、象徴的かつ緊要な問題となっているとした上で、住専自身及び母体行が主体的役割を果たし、今後の基本的な方針や債権の処理の仕方等につき合意形成を行うことが必要であること、行政当局は当事者間における議論を踏まえつつ、個別住専を超えた全体的枠組みの整備についての検討を並行して進め、適時に当事者間の合意形成を促進する必要があること、住専問題の早急な解決は、国内外から要請されているところであり、本年末までに処理策が策定されるよう、すべての関係者が強い決意をもって取り組むことが必要であることを報告している。”
“さらに、大蔵省も、同日、「金融機関の不良債権の早期処理について」を公表し、住専について、当事者による真剣な取り組みをしょうようするとともに、不良債権等の受け皿となる機関等について検討を行い、年内に処理方策を固めるとした。右のような状況を受けて、本件母体五社は、平成7年9月22日、母体会議を開催し、本件新事業計画と対比する形でBの実態の報告、第二次立入調査の報告がされた後、原告の〈R〉融資第二部長から、Bの進む方向は基本的には整理の方向であるとの認識を示し、意見を求めたところ、E銀行及び本件証券母体三社からは異論がなく、本件母体五社間でBを整理する方針が確認された。同年10月2日には、住専七社及びその母体行は、与党PTに対して、住専の再建を断念し、整理・清算する方針を伝えた。”
“本件母体五社で確認された整理の方針に従って、平成7年9月27日以降同年11月にかけて、Bの整理に向けての系統との協議が五回にわたって開催された。同年9月27日の第一回目の協議は、大蔵省銀行局中小金融課金融会社室(以下「金融会社室」という。)からの要請に基づいて開催されたもので、系統との協議については、全般的に金融会社室との事前・事後のすりあわせの下に行われた。第一回の協議は、同月25日及び同月26日の金融会社室との事前折衝を経て行われた。第一回の協議には、原告、E銀行及びBが参加し、系統側は、Q金庫、T共済農業協同組合連合会及び静岡県・北海道・東京都・兵庫県の各R農業協同組合連合会が参加した。第一回の協議においては、Bの〈J〉社長がBの現状等を説明し、系統の債権の担保となっているBの営業貸付金の状態が極めて悪化しており、系統の債権全額の弁済さえ危ぶまれる状況にあることを説明し、原告の〈H〉取締役が、Bは整理するとの結論になる旨を伝えた。これに対して、系統側は、すぐには了承せず、Bの実態に関する個別質疑や責任分担に踏み込んだ議論は次回以降に持ち越しとなった。”
“平成7年10月13日、同月31日及び同年11月16日に、第二回ないし第四回の協議が行われ、第一回と同様、B、本件母体二行及びQ金庫・静岡県R農業協同組合連合会をはじめとする中核的な系統関係者が参加し、第二回及び第三回協議には全国R農業協同組合連合会協会、第四回には愛知県R農業協同組合連合会も参加した。第二回の協議において、全国R農業協同組合連合会協会の〈S〉専務理事と静岡県R農業協同組合連合会の〈T〉専務理事から、新事業計画成立時に、原告とBとの関係は単なる株主と子会社ではないことを原告自身も認め、母体責任を確認したので系統側はBの再建に協力したという経緯があるのだから、母体行としての認識をきちんともってもらいたい旨の発言がなされ、第三回の協議において、右の〈T〉専務理事が、同年9月末に原告が母体ニューマネーを回収したことに関連して、Bを整理することになった場合でも、従前の系統への優先弁済は存続しているはずである旨の発言がなされ、また、第四回の協議においても、Q金庫の〈R〉副理事長が、住専の経営悪化の原因について考えると責任は住専と母体に極めて重いものがあると発言するなど、系統との協議においては、原告の母体行としての責任を追及する発言がみられた。”
“なお、原告側は、右の第二回の協議の〈S〉専務理事と〈T〉専務理事の発言に対しては、原告はB設立当時の発起人にも入っており、単なる一株主というつもりは全くなく、原告の責任が重いことはそのとおりである旨回答し、また、右の第三回の協議の〈T〉専務理事の発言に対しては、Bの新事業計画成立時からの経緯等を十分に踏まえて対処したい旨回答するなど、原告がBの整理に係る損失の負担についてプロラタ負担によるべきであると主張することはなかった。”
“同年11月22日には第五回の協議が行われたが、それに先立つ同月20日に金融会社室と原告との事前相談において、金融会社室側から、これからの整理に伴う負担議論等に進んでほしい旨の要請がされ、併せて、プロラタ負担としたいなどと持出すことは避けるようにとの要請がされた。第五回の協議において、原告の〈H〉取締役は、大蔵省から早く整理の方法の協議を進めるように促されていると前置きした上で、整理に伴う損失分担については、商法の枠組みの中で、関係者間の議論を踏まえた合理的な方法をとりたい旨を述べた。”
“これに対し、系統側は、Bの設立や本件新事業計画の成立の経緯、また、前記5(二)の原告らが大蔵・農水覚書に従って大蔵省に念書を差し出した事実などを持ち出して、系統の債権から生ずる元本ロス部分について、母体側が責任を持つ完全母体行責任による処理を強く主張した。しかし、原告は、株式会社としてできる限界があり、貸出金の全額を棒引きすることまでは認めるが、そこまでが限界であって、それ以上の負担をすることは商法上許される範囲を超えるとして、系統の右の要求を拒否した。右のとおり、完全母体行責任を前提とした系統の債権の全額弁済を主張する系統とあくまでも商法の枠内での損失分担であり、貸出金の全額の放棄が限度であると主張する原告との間の溝は埋まらず、系統との協議は物別れに終わった。”

“このように、原告らと系統との交渉は平行線をたどったところ、平成7年11月29日に、大蔵省の〈U〉銀行局長(以下「〈U〉銀行局長」という。)が各住専の母体行の役員を集め、「本件は当事者の持っている道具だけでは解決できない問題だと考えており、明日以降、みなさんの意向をお聞きして、大蔵省としての案をまとめたい。」として、大蔵省として、住専処理について関係当事者の仲介を行い、公的資金の導入を含む抜本的な住専処理のスキームを策定する意思があることを示唆するとともに、政府予算案の内示がある同年12月20日を住専処理案のとりまとめのリミットとして提示した。同年12月1日には、与党PTを引き継いだ与党政策調整会議によって、①処理案の対象はできる限り住専七社一括とすること、②処理すべきロスについては、この際、果断に対処することとし、残余の資産等については受け皿となる機構を設立し対処すること、③日銀融資、政府保証等を活用すること、ただし、これらは直接的にも間接的にも国民の負担となるものであって、まず国民の理解が前提で、当事者間で最大の努力が払われた後の手段であり、したがって、真にやむを得ないものに限られるべきであって、透明性の確保、種々の責任の明確化が必要であること、④ロスの負担割合を決める場合は、日本の金融が国際的に位置付けられていることに配慮したものであること、住専設立から今日の破綻に至った経緯を充分踏まえたものであること、それぞれの当事者が有する経営状況、対応力等を考慮したものであることの三点が考慮されなければならないことをガイドラインとし、大蔵省及び農林水産省が直ちに処理案の作成に取りかかることを要請するとする内容の「住専問題の処理について」と題するガイドラインが提示された。”
“これを受けて、大蔵省は、住専の母体に対するヒアリングを行ったが、原告は、〈U〉副頭取において、貸出残高までの負担が商法上許される限界であることを伝えた。同月4日に各住専の母体が集まって〈U〉銀行局長との面談に関する情報交換が行われたが、原告以外の各住専の母体も、貸出残高全額までの負担が限界であるとの認識を有していることが確認された。”
“住専の母体である関係金融機関の右のような意向を受けて、大蔵省は、農林水産省との間で、住専処理案の取りまとめに入り、まず、住専各社の有する第Ⅳ分類債権相当額の6兆2700億円ないしこれに欠損金1400億円を加えた6兆4100億円を一次ロスとした上で、母体行が有する債権の全額3兆5000億円を放棄して、残額の2兆8000億円を一般行と系統がプロラタで負担する方式を検討したが、これによると、系統の負担は約1兆円以上となり、5000億円が系統の負担の限界であるとする農林水産省との間で議論が平行線をたどった。”
“平成7年12月8日には、当時の〈d〉大蔵大臣と〈e〉農林水産大臣との間の協議が行われたが、系統の負担する金額について打開策を見いだすことはできなかった。また、同月12日及び13日には、大蔵省から原告に対して、大蔵省と農林水産省との折衝の進捗状況にかんがみて、母体行が貸出債権の全額を放棄する修正母体責任に加えて、何らかの責任を負うべきであるとする国会議員からの要求が強いので、原告から国会議員に対して母体行の考えを直接伝えるように指示がされ、原告は、〈U〉副頭取を中心にこれに対応した。
その後、同月16、17日に〈U〉銀行局長は各住専の母体の経営者を召集し、原告については同月17日の夕方に〈U〉銀行局長と原告の〈A〉頭取とのトップ会談が設定された。原告は、右のトップ会談に先立ち、既に16日に会談を済ませた銀行等から情報を得て、大蔵省から提示される処理案に対して事前に内部で対応を検討した結果、貸出残高全額までの負担であれば受諾するもののそれ以上の負担については受諾できないことを再度確認した。また、原告が各住専の他の母体行の動向を調査したところ、母体行債権の全額放棄が法的にも負担の限界であるとのスタンスで一致していた。同月17日の〈U〉銀行局長と〈A〉頭取との会談では、〈U〉銀行局長が、系統は本件新事業計画等の各住専の第二次再建計画の合意等の従前の経緯を根拠に責任は母体にあると強く主張しているため住専処理策のとりまとめが難航していると述べた上で、損失負担について、①一次ロス(第Ⅳ分類資産6兆3000億円)については、母体行債権3兆5000億円の全額放棄、一般行による1兆7000億円の債権放棄に加えて、残りの1兆1000億円を系統の負担とする(ただし、系統についてはどうなるか流動的である。)、②第Ⅲ分類資産に係る損失1兆2400億円(二次ロス)については、母体が中心となって管理・運営する受け皿会社で処理するとの大蔵省案を提示した。”
“これに対し、原告側は、右②の1兆2400億円については実質的に母体の負担となるものであって承諾できないと伝えたところ、〈U〉銀行局長は、一次ロスの6兆3000億円を出発点にした母体行3兆5000億円、一般行1兆7000億円の負担については、翌日の同月18日までに判断してほしい旨、二次ロスの1兆2400億円についてはその後でもよい旨述べた。原告は、同月18日に、右①の一次ロスの処理については大蔵省案に同意するが、これによってプロラタでの負担2兆1000億円より1兆4000億円も多く負担して母体責任を果たしているので、それを超える提案は同意できないとの回答をした。住専各社の母体行も、おおむね、右の一次ロスの処理について大蔵省案を受け入れるとの姿勢を示した。”
“与党三党と政府の首脳(自由民主党総裁、同党幹事長、同党政務調査会長、社会党委員長、同党書記長、同党政策審議会長、新党さきがけ代表兼大蔵大臣、同党代表幹事、同党政策調査会長、内閣官房長官、農林水産大臣)は、平成7年12月19日、住専の具体的な処理方策について、①住専処理機構は、住専の資産等を引き継ぐこととし、回収不能な不良債権に係る損失見込額(七社合計で約6兆2700億円)、欠損見込額(約1400億円)について処理すること、②関係金融機関に対し、次のとおり対応することを要請すること、すなわち、母体行は債権の全額(3兆5000億円)を放棄し、また、住専処理機構への出資及び低利融資を行うこと、一般行は債権のうち1兆7000億円を放棄し、また、住専処理機構への低利融資を行うこと、系統は貸付債権の全額返済を前提として、住専処理機構に対する約5300億円の贈与及び住専処理機構への低利融資の協力を行うこと、③政府は、預金保険機構に住専勘定を設け、平成8年度当初予算において、同勘定に対して6800億円を支出し、同勘定は、住専処理機構に対し、同年度以降回収可能性の精査、整理状況を踏まえて支出を行うこと、④預金保険機構住専勘定は、住専処理機構において住専から引き継いだ資産に係る損失が生じた場合、その一部を補てんし、政府は同勘定に損失が生じた場合に適切な財政措置を講ずること、⑤政府は、平成8年度当初予算において、預金保険機構に対し、同機構の運営を強化するために50億円の出資を行うこと、⑥〈V〉銀行に対し、預金保険機構への出資及び同機構住専勘定への資金供与を行うよう要請すること、⑦以上について、所要の法的措置を講ずるとともに、関係機関による調整が行われ、適切な整理計画が策定された住専から速やかに住専処理機構に対し資産等の譲渡を行い、その処理を着実に進めていくこととすることなどについて、政府・与党が一体となって取り組むことを確認した。”

“右の確認において、住専処理の全体のスキーム、損失負担等を決定するに当たっては、次の点が守られなければならないとして、透明性の確保、大蔵省・〈V〉銀行の金融政策上の責任の明確化、住専各社の責任の明確化、銀行等の責任の明確化、系統の今後などについて言及され、銀行等の責任の明確化については、住専の母体行はその債権を放棄するとはいえ、その設立、経営の責任は引き続き将来にわたって大きいものがあること、迂回融資、紹介融資のうち銀行が不正に関与したものなど金融機関の本来の責任を回避したケース等あらゆる経営責任の追及を行うこととされている。”
“内閣は、平成7年12月19日、住専をめぐる問題は、金融機関の不良債権問題における象徴的かつ喫緊の課題であり、我が国金融システムの安定性とそれに対する内外からの信頼を確保し、預金者保護に資するとともに我が国経済を本格的な回復軌道に乗せるためにも、その早期解決が是非とも必要であるとし、そのため、住専問題に係る透明性の確保、種々の責任の明確化等を図りつつ、次のとおり、具体的な方策を講ずるものとするとの閣議決定(本件閣議決定)を行い、翌日に予定されていた翌年度予算の大蔵原案の内示前にこの問題に一応の決着をつけた。
(1)処理の損失住専処理機構を設立し、住専の資産等を引き継ぐこととし、回収不能な不良債権に係る損失見込額(七社計で約6兆2700億円)及び欠損見込額(約1400億円)について処理する。
(2)関係金融機関に対する要請関係金融機関に対し、次により対応することを要請する。ア母体行は、住専に対する債権約3兆5000億円の全額を放棄する。また、住専処理機構への出資及び低利融資を行う。イ一般行は、住専に対する債権のうち約1兆7000億円を放棄する。また、住専処理機構への低利融資を行う。ウ系統は、貸付債権の全額返済を前提として、住専処理機構に対する約5300億円の贈与及び住専処理機構への低利融資の協力を行う。
(3)公的関与ア政府は、預金保険機構に住専勘定を設け、平成8年度当初予算において、同勘定に対して6800億円を支出する。同勘定は、住専処理機構に対し、同年度以降、同機構の保有する債権の回収可能性の精査及び整理状況を踏まえて支出を行う。イ預金保険機構住専勘定は、住専処理機構において住専から引き継いだ資産に係る損失が生じた場合、その一部を補てんする。また、政府は、同勘定に損失が生じた場合に、適切な財政措置を講ずる。ウ政府は、平成8年度当初予算において、預金保険機構に対し、同機構の運営を強化するために、50億円の追加出資を行う。エ〈V〉銀行に対し、預金保険機構への出資及び同機構住専勘定への資金供与を行うよう要請する。
(4)債権回収の促進住専処理機構は、預金保険機構の指揮の下、法律家、不動産取引の専門家等の参加、協力を得て、法的手段等を活用しつつ、債権の回収を強力に行う。両機構は、法務・検察当局及び警察当局と緊密な連携を図る。
(5)以上について、所要の法的措置を講ずるとともに、関係機関による調整が行われ、適切な処理計画が策定された住専から、速やかに住専処理機構に対し資産等の譲渡を行い、その処理を着実に進めていくこととする。なお、金融制度調査会は、平成7年12月22日に、金融システム安定化のための諸施策と題する答申を行い、住専問題について、「公的資金の導入も含めた臨時異例の措置が政府において決断されたこともやむを得ないと考えるが、これらの措置の具体的運営に当たっては、公的資金が導入されていることを十分踏まえて、最大限の透明性が確保され、できる限りの早期の回収が図られるべきである。」とした上で、国民の理解を得るためには、種々の責任の明確化について厳正な取組みを行うことが不可欠であるとして、住専の母体行の責任については、「住専の設立やその経営に関与してきており、これまでの経営の過程での責任について明確化する必要がある。」とし、さらに、「今般の処理方策が今後適正に実行されることにつき、注視することとしたい。」としている。
本件閣議決定がされた平成7年12月19日時点では、本件新事業計画に従って原告からBに貸し付けられた母体ニューマネーのうち50億円が回収されていなかったが、原告は、これを同月29日に全額回収した。”
“一次ロスの処理については処理方策がまとまり、本件閣議決定に至ったが、二次ロス1兆2400億円の負担については、依然として処理方策がまとまっていなかった。二次ロスについて、原告らは、住専処理のために貸出残高を超える負担をすることは株主に対する説明ができず、到底承諾できないと大蔵省に対して伝えていたところ、大蔵省は、平成7年12月末ころ、受け皿会社で生ずる二次ロスについて、直接母体が負担するのではなく、関連金融機関のすべてが協調して出資する基金を設立してその運用資金で賄う案を立案し、各住専の母体行との協議を開始した。原告については、平成8年1月11日に〈H〉取締役らが大蔵省を訪問して、同省の〈f〉審議官及び〈g〉参事官から、二次ロスの処理スキームについての説明を受けた。
大蔵省側は、金融機関拠出基金について、同基金を預金保険機構の中に設置すること、その目的は、住専にかかわる債権の回収を円滑に進め、金融システムの安定に資することとし、法律に明記すること、その法的な性格は任意拠出とするが、これは法律によって基金への拠出を義務付けることは難しいからであること、基金の総額は1兆円を限度とすること、基金の拠出者は住専に対して出資していた預金金融機関等とし、生命保険会社や証券会社も含まれるが今のところ系統は入らないとしていること、基金から住専処理機構へ1000億円を出資し、残りは基金に留め置き、その運用益を処理機構に繰入れることなどを説明した。”
“また、住専処理機構について、その法的性格は、債権回収のフレキシビリティを考えて株式会社とすること、資本金は2000億円とし、預金保険機構100パーセント出資の子会社とすること、住専処理機構の資金計画などについて説明した。同月16日には、大蔵省の〈U〉銀行局長が原告を訪問し、〈U〉副頭取に対し、同月20日に大蔵大臣がG7へ出席するが、外国の住専問題に対する関心は高く、外国に対して住専処理策が実現することをきちんと説明するためにも、大蔵大臣の出発する前に住専問題についての見通しをもっていたいと述べて、同月19日までに二次ロス処理案への了解がほしいと要請した。”
“原告は、Bの母体行会議を召集し、大蔵省から提示された二次ロス処理案への対応策を協議し、さらに他の住専の母体行とも情報を交換しながら、最終的な回答案を詰めた。その結果、同月18日付けで、①金融機関拠出基金について、預金保険法において同基金設置の趣旨(金融システムの維持)を明記し、法律により拠出を義務付けること、拠出は母体に限定せず幅広く民間金融機関の参加とすること、及び相当額の系統金融機関の拠出を加えること、②住専処理機構への母体低利貸付について、母体は債権を全額放棄することを理由に、住専処理機構への貸付は系統と一般行が残高に応じて行うべきものであり、仮に系統が3分の1(約2兆2000億円)を超える貸付を行えず、民間金融機関が不足分を貸し付ける場合は、同貸付が系統の不足分である旨を明らかにすること、不足額の貸出については、コマーシャルベースのバンキングの視点から安全性・収益性に問題がないことが必要であり、その証左なき場合は政府保証等の措置を講ずること、金利・返済等の貸付条件は民間・系統とも同一とすることなどの条件が満たされることが二次ロス処理案を前進させるための前提条件であって、これは法的な問題であるので厳格に受け止めてもらいたい旨の回答案を作成し、同日、〈f〉審議官に対して説明をした。”
“また、住専の主要母体行は、同月17日、大蔵省が提示した二次ロス処理策を受け入れるためには、①二次損失は系統が負担すべきであるが、系統の救済のために設立母体が支援するということを政府が公式に認めること、②今後設立する住専処理機構が住専の資産を買取るのに必要な資金6兆5000億円のうち、系統以外の金融機関に求められた低利融資約4兆4000億円は、元利の全額返済を政府が保証すること、③預金保険機構内に新設する住専勘定に設立母体が出資を要請された最大1兆円については、法的に義務付けることとの三点を条件とすることを固めた。”
“大蔵省は、平成8年1月24日、原告に対し、「(案)」と題する文書によって、大蔵省の二次ロス処理の修正案を提示した(甲193)。その内容は、以下のとおりである。すなわち、まず、基金への拠出の明確化として、①住専処理に関する法律により、預金保険機構の中に「金融安定化拠出基金」(仮称)を設立すること、②基金の目的(住専の債権債務の処理を促進し、金融システムの安定化に資する)を法律で明記すること、③基金の拠出対象者は住専に出融資している金融機関等(生命保険会社及び証券会社を含む。)とすること、④拠出方法については、預金保険機構の運営委員会において決定すること、⑤大蔵大臣による拠出の要請をすることとされていた。また、住専処理機構の将来発生し得る損失に関する措置として、①住専処理機構が住専により引き継いだ資産については、今後の経済や地価の動向によっては、将来損失が生ずる可能性が残されているところ、この損失懸念に対しては、まずもって、法律上認められているあらゆる回収手段等を迅速かつ的確に用いることにより債権回収等に全力を挙げること、②そのような回収努力にもかかわらず、万一将来損失が生じた場合、国はその損失の2分の1を補てんすること、③他方、残る2分の1については、まず、民間金融機関の拠出による金融安定化拠出基金の運用益及び稼働資産からの収益等によって賄い、さらに損失が生じても民間金融機関の住専処理機構に対する融資が毀損しないよう、必要に応じて預金保険機構の一般勘定からの支援の下で同機構による保証を行うことを検討することとされていた。さらに、系統との融資条件の同一化として、Q金庫の融資に関しては、金利・返済条件につき母体行及び一般行と同一化が図られるように要請するとされ、また、融資額の配分についても、各住専口勘定ごとに母体・系統・一般金融機関からおおむね3分の1ずつ融資するとの原則が示された。原告は、右の修正案を検討した結果、平成8年1月25日に、右修正案に同意することを伝えた。また、そのころ、原告以外の関係金融機関も右の修正案の基本的な枠組みについて同意した。”
“政府・与党は、右の修正案を二次ロスの処理策として採用することを最終的に決定し、同月30日に、住専問題の処理については、平成7年12月19日の閣議決定に則り、さらにその処理方策を具体化するものとするとの閣議了解(本件閣議了解)がされた。本件閣議了解で了解された方針は以下のとおりである。
(1)現下の喫緊の課題である住専問題の早期解決を図るため、住専七社は整理されることとなり、さらに、新たに設立される住専処理機構が住専七社から債権等を買取り、強力に回収を行いながら処分していくこととされている。
(2)その際、住専処理機構は、住専七社の債権等を買取るための資金を調達することが必要となる。このため、母体行、一般行、系統が同機構に対し所要資金を融資することが求められている。
(3)本問題の処理に当たっては、債権回収と責任追求に最大限の努力を払う必要がある。まず、預金保険機構と住専処理機構が一体となって強力な体制をもったものにすべきである。政府と両機構は、法律上認められるあらゆる回収手段を迅速かつ的確に展開して、住専から引き継いだ資産にかかわる損失を生じさせないよう全力を挙げる。
ア回収が順調に進み益金が生じた場合は、その成果を還元する。
イ万一、損失が生じた場合には、本件閣議決定の趣旨に従って、政府・民間の共同の責任で処理することとし、政府の負担は2分の1とする。
ウ民間金融機関の負担については、預金保険機構内に新たに設置される基金(約1兆円を目途)の運用益の活用、同機構による保証等により対応する。
(4)本件閣議決定及び本件閣議了解によって、金融秩序維持安定のための住専処理方策が具体化されることになる。今後、国民の最大の関心事である種々の責任を明確にするため、全力を挙げて取り組むこととする。政府は、平成8年2月9日に、本件閣議決定及び本件閣議了解の内容を実現すべく、住専の整理に伴う住専処理法案を国会に提出した。”
“既に述べた政府の住専処理方策とは別に、当時最大野党であった新進党は、平成7年10月17日に、住専問題の解決に向けてとする住専処理に関する新進党案を発表した。右の新進党案は、住専問題解決の前提として、住専問題の本質と責任の所在を明確化しなければならないとして、①住専設立と住宅金融政策上の位置付け、②住専の設立に関する母体行、金融当局の関与及びその後の母体行の関わり、③住専がなぜ巨額の不良債権をかかえるに至ったのか、その経緯と母体行の関与と住専の経営実態、④住専再建計画の経緯と責任の所在の四点を明らかにすべきであるとした上で、以下の五つの観点から、問題解決の処方箋を作成することを提起するとしている。”
“すなわち、第一の観点は、経営悪化の主因は、何ら業務調整もしないまま住専の本来業務である個人住宅ローンに親会社である母体行が本格進出し、市場のパイを圧迫したことにあるという点、また、住専の債権には母体行の紹介や移し替えなどがあったとの事実も指摘されており、発生面において不透明であり、これらの点から母体行の責任を見逃すことはできないという点である。
第二の観点は、母体行と住専は出資の関係においてのみ論じられるのではなく、母体行業務の附随・関連業務を行う、実質的な子会社であり、単に形式的比率のみで責任分担を論じられるものではないという点、また、設立の経緯(出資など)のみならず、経営面においても役員・主要幹部職員などの派遣などを含めて深く関与してきており、親子会社の関係は明白であって、出資者たる母体行が親会社として子会社の経営を支配してきており、出資者は負担能力の限界まで責任を負うべきであるとの点である。
第三の観点は、住専は預金の取扱いをする金融機関ではないが、短資会社と同様、大蔵省直轄の金融機関として位置付けられ、系統の融資の取扱いも通達上金融機関として位置付けられていることから、住専との取引はいわば金融機関の信用力を担保とするインターバンク取引であって、一般の事業会社に対する貸付と同列に論ずるわけにはいかないという点である。
第四の観点は、住専の再建計画において、母体行は責任を負うことを明確にしており、再建計画時に約されたことが、整理時に反故にされることは信義誠実原則に反し、我が国の金融システムの根幹をなしている「信用取引」を崩壊させることになりかねないものであって、住専が再建であれ、整理であれ、母体行責任が減じるものではないとの点である。そして、第五の観点は、住専問題は、その対応・処理の方法などを含めて、我が国金融システムの安定化に向けて、内外の注目を浴びているところ、このような中で、住専の許認可、指導、さらに再建計画を含めて行政は深く関与してきており、我が国の金融システムの安定化に向けて、行政はその責任を痛感しなければならず、その観点から最大限の努力を行うことは当然であるとの点である。”
“右のような各観点を踏まえて、新進党案は、解決に向けての望ましいスキームとして、母体行が全責任を負う「完全母体行主義」か、若しくは母体行が債権を全額放棄し、不良債権を圧縮、残った資産を受け皿会社に移行し、同会社に母体行が出資・贈与・低利融資、非母体行は元本が保証されることを前提として贈与と低利融資で協力を行う方式を採用することが至当であるとしている。
また、新進党案は、公的資金の導入問題については、金融システム安定化委員会において大方がその必要性を認めているようであるが、国民的理解を得るためには、公開性と透明性を担保する観点から、住専の実態解明とこの問題の経緯並びに責任のあり方についての筋の通った説明が行われる必要があること、また、導入の検討に際しては、預金者保護や納税者の利益保護など公益的な判断に基づかなければならないことを指摘している。その後、新進党は、本件閣議決定及び本件閣議了解がされた後である平成8年2月27日に、「住専問題に関する基本方針」と題する住専処理に関する対案を発表したが、その内容は、①平成8年度予算案に計上している6850億円の住専関係予算を削除する、②住専問題の解決については、市場原理に基づく自己責任の大原則により国民に開かれた状況の中で行う、③国家行政組織法3条による行政委員会として不良債権処理公社(日本版RTC)を設立して、金融機関等の破産・更生手続の申立権を付与するとともに、管財人の機能並びに刑事訴追権を付与し、刑事・民事上の責任追及及び債権回収に全力を挙げる環境を整備する、④母体行は住専の経営破綻に至った経緯にかんがみ、最大限の責任を果たすべきである、⑤系統の再建・改革については、国が別途全面的に支援する、⑥国民の預貯金については、国がすべてを保証するというものであった。”

“新進党は、同年3月4日、住専関係予算6850億円が計上されている平成8年度予算案の審議に応じないという方針を決定し、同党議員が予算委員会の会場の第一委員室に座り込みを開始した。
また、新進党は、同月13日には、右の「住専問題に関する基本方針」を具体的に展開する「住専問題に関する具体的方針」を発表した。その内容は、①住専は民間会社であり、かつ預貯金を受け入れている金融機関でもないから、その経営破綻の処理について税金を投入すべきではない、②密室の合意を前提に住専処理機構に税金を投入して住専の損失を補てんするという政府の処理策は合理性を欠くから、予算案に計上している6850億円の住専関連予算は削除する、③住専各社の経営破綻の処理は、法的処理により、公正・透明なルールの下に行うこととする、④法的処理の方法としては、会社更生法の適用によることとし、管財人の強力な権限の下に、住専各社の経営破綻に母体行が重大な責任を負っている経緯を十分に踏まえた実質的公平の実現を図る、⑤巨額な不良債権を抱える住専等の管財人の業務を集中的かつ効率的に遂行するため、特殊法人として更生申立権を有する「不良債権処理公社(日本版RTC=整理信託公社)」(仮称)を設立し、不良債権の回収と責任の追及を徹底的に実施する、また、その過程で明らかになった犯罪行為は告発することを義務付ける、⑥金融システムの安定性を保ちつつ、不良債権の法的処理を行うため、当面、預金保険機構・貯金保険機構による預貯金の完全な支払保証を実施するとともに、そのための必要資金は政府保証を付して日銀から融資する、⑦協同組合であるために内部留保の乏しい系統及びその傘下の系統組織の経営に配慮し、当面、Q金庫に対して政府保証を付した日銀融資を行うとともに、系統のあり方の見直しや系統組織の抜本的改革を進めるというものであった。”
“なお、この点について、被告は、最大野党の認識も政府の住専処理策が実現されない場合には、処理策が白紙に戻され、法的整理手続で債権者平等の原則に基づく整理手続が行われるべきものと考えていたことがうかがわれると主張し、甲第221号証を引用する。
しかしながら、甲第221号証によると、新進党が発表した「住専問題に関する具体的方針」では、「法的処理の方法としては、会社更生法の適用によることとし、管財人の強力な権限の下に、住専各社の経営破綻に母体行が重大な責任を負っている経緯を十分に踏まえた実質的公平の実現を図る。」とされ、新進党の〈h〉議員が記者会見で「会社更生法に基づき、設立母体や経営者責任が問われたケースは存在するし、実質的平等の原則に照らせば、母体行に重い責任をとってもらえる」と説明したことが認められ、新進党は、会社更生法などの法的処理によって住専処理を行うとしながらも、法的処理において母体行の責任を追及する姿勢を明確にしていたのであって、被告が主張するように、法的整理手続で母体も含め債権者平等の原則に基づく整理手続が行われると考えていたなどとは到底いうことができない。”
“また、当時、新進党政権準備委員会の〈i〉副委員長(明日の内閣副総理)は、雑誌のインタビューに対し、「母体行は文字どおり母体です。しかも、融資先の紹介などをやって、そういう先に限って質が悪い。その責任を考えれば、3兆5000億円の債権放棄だけでは済まされません。」と述べている(甲220)。その後、同月25日に、当時の〈j〉衆議院議長の下で、与党三党、新進党及び日本共産党(以下「共産党」という。)による五党党首会談が開催され、翌26日から国会を正常化することで合意し、新進党は、同月25日の夜に、同月4日から続けてきた座り込みを解除した。”
“共産党の〈k〉委員長(当時)は、平成7年10月25日ないし同月27日にわたって開催された、同党の第四回中央委員会総会の幹部会報告として、「今問題となっている住宅金融専門会社(いわゆる住専)にしても、そのほとんどは大銀行が設立し、資金も人事も経営も銀行がにぎり、銀行の別働隊として、自分では規制があるためにやるわけにゆかない不動産融資を、銀行にかわってやらせたものであります。しかもその大銀行自身は、バブルの時期に大もうけをかさねたうえ、バブル崩壊後もばく大な利益をあげつづけているのです。こういう乱脈経営の結末は、母体である大銀行自身の手で解決するというのが当然のことであって、しかも銀行はそれだけの能力を持っています。」と報告した。”
“また、共産党の〈m〉書記局長(当時)は、平成8年1月31日の衆議院予算委員会で、住専各社の母体行が第一次再建計画から約1兆円の融資を引き上げているとした上で、「あなた方は母体行は責任は果たしたと言われるけれども、3兆5000億円の債権放棄では済まない。私は、少なくとも4兆5000億円まで払ったっていいじゃないか、足らない分があったら国民の血税に頼るのではなくて銀行に払わせたらいい。これが国民の声ですよ。これは政策判断の問題です。どうですか。」と述べている。”
“同書記局長は、雑誌のインタビューに対しても、「住専を設立したのも、暴走させたのも、破綻させたのも銀行です。足りない分は母体行が責任を持って負担するべきです。3兆5000億円の債権放棄で、責任を果たしたとは思いません。母体行は住専と一緒になって乱脈融資をした当事者です。債権者のような顔をしていますが、本当は住専と一緒に債務者の側にあるべきなんですよ。」と述べている。
さらに、共産党国会議員団は、平成8年2月27日に、「住専不良債権処理への血税導入の撤回と、国民本位の財政再建に向けた抜本的な予算組み替えを要求する」と題する書面をもって与党三党に申し入れた。その内容は多岐にわたるが、住専処理関係については、「住専問題で最大の責任を負うべきは、住専を作り、別働隊として活用して大もうけしたうえ、リスクの高い融資先を「紹介融資」として住専に押しつけ、あげくのはてには住専を農林系金融機関に押しつけてみずからは撤退をはかった母体行であることは、衆目の一致するところである。母体行が現存の債権額3兆5000億円を放棄するだけで責任を逃れようとするのは、断じて許されるものではない。」としている。”
“国会においても、右(二)記載の共産党の〈m〉書記局長の発言にあるほか、平成8年2月14日及び同月26日に開催された衆議院予算委員会において、いずれも、〈n〉総理大臣が、法律上問題のあるような紹介融資については、住専処理機構から損害賠償請求を行うことも考えるべきである旨の答弁をするなど(甲472、473)、住専の母体行の責任を追及する動きがあった。”
“平成8年2月15日に開催された衆議院予算委員会には、Q金庫の〈W〉理事長(以下「〈W〉理事長」という。)、全国銀行協会連合会会長であったy銀行の〈X〉頭取(以下「〈X〉頭取」という。)、Jの〈Y〉代表取締役、原告の〈A〉頭取などが参考人として招致された。〈W〉理事長は、冒頭の意見陳述において、住専問題の本質は住専の経営問題であって、住専の経営に責任のある住専経営者及びその経営に深く携わってきた母体行が最大限の責任と負担をもって処理すべきであるとし、とりわけ母体行は、住専を自己の子会社として設立し、その経営に人員を派遣するなど深く住専の経営に参画してきたので、日本の金融の慣行、商慣行等からみても住専に対する親会社としての母体行の責任は厳然として存在すると述べ、母体行の責任に言及するとともに、系統が母体であるOについては系統の責任において対処していることを指摘した。”
“また、質問に答える中で、〈W〉理事長は、母体行の方から法的整理ということであれば、当然私たちもこれに応訴していくとし、右のような母体行と住専の関係に加えて、母体行が住専の事業を浸食したことや紹介融資を行ったことからすると、母体行の責任は単に貸出債権を放棄しているということでは済まない、債権者平等の原則というのは実質的な債権者平等の原則であり、出資者や経営者の債権は一般債権者に比して劣後するから、母体行の3兆5000億円の債権は劣後債権であって、破産あるいは清算の場合は回収不能のものであるとの意見を述べた〔なお、同理事長は、平成8年4月22日の参議院予算委員会においても、母体行の住専に対する経営責任からすると平等弁済は社会正義に反するとの発言をしている〕。”
“〈Z〉委員から〈X〉頭取に対して、公的資金に相当する6850億円を銀行協会から政府に対し提供するような考えがないかとの質問がされ(乙5)、〈P〉委員から〈X〉頭取に対して、紹介融資問題が母体行の大変な責任であって、それが回り回って国民の税金としてとられるところに国民の怒りがあるとの指摘がされるなど、〈X〉頭取、〈A〉頭取に対する質問において、母体行が、貸出債権の全額放棄以上の責任を負うべきであるとの追及が厳しく行われた。〈A〉頭取は、質問に答えて、「母体行としては、3兆5000億円という母体行全額の放棄をいたします。それからその上に、一般行としてもまた債権放棄いたしまして、その上に、住専の処理機構に低利融資をいたします。」と述べ、また、商法上の株式会社として許される範囲のぎりぎりまでの負担をしていると説明した。”
“〈a〉新聞が、平成7年11月1日に、修正母体行責任を妥当としつつ、住専処理に関する損失負担は、過去の再建計画時の経緯や紹介融資の実態などを踏まえ、母体行への傾斜負担は避けられないとする社説を掲載し、〈q〉新聞が、平成8年2月2日に、母体行が債権の全額を放棄し、残りの損失はほかの貸し手がそれぞれの融資比率に応じて負担するという修正母体行主義を基本にしつつ、紹介融資に伴う損失は、右の債権放棄とは別に母体行の責任で処理するという試案を示す社説を掲載し、また、経済雑誌である〈r〉(平成8年3月12日号)に、母体行は、母体行としての債権3兆5000億円の全額の放棄に加えて、紹介融資によって不良債権化したものの負担も負うべきであるとする論文を掲載するなど、平成7年末から平成8年初頭にかけて、マスコミは、住専問題について、母体行の責任を厳しく追及していた。”
“また、住専問題に関する処理に税金を投入することに反対し、その負担は母体行の責任で行うことを求めるなどの請願が多数存在し、z証券研究所主任研究員のエコノミストが、母体行には道義的責任があり、債権全額放棄以上の負担を強いられ、株主代表訴訟を起こされても仕方がないと述べるなど、国民の世論にも、住専問題の解決について、債権放棄以上に母体行の責任を求める意見が多く存在した。”
“右のような状況を受けて、与党も、母体行の責任を追及する姿勢を示し、平成8年3月4日には、住専処理追加措置の第一段(原案)を決め、母体行について、さらなる寄与を求めるとした。
(一)本件事業年度におけるBの財務状況
(1)本件事業年度上半期(平成7年4月1日から平成7年9月30日まで)の財務状況
Bは、本件事業年度上半期において、本件新事業計画の3年目を迎え、引き続き本件新事業計画に従って、住宅ローン営業基盤の維持・不良債権の回収・経費の圧縮等の努力を行ったが、本件新事業計画策定時の予想を超える不動産不況の長期化、金利低下による利息収入の減少等により厳しい経営が続いた。この結果、平成7年9月末の貸付金残高は、前期末比0.7パーセント減の2兆2387億円となり、総資産は前期末比21.1パーセント減の1兆9977億円となった。また、損益面については、金利低下等による貸付金利息の減少から、営業収益は472億円と前年同期比1.8パーセントの減収となる一方、営業費用は本件新事業計画に従って借入金利息を減免されているが、334億円の貸倒引当金の組入れを行ったことから796億円となり、これにより経常損失は323億円となった。さらに、特別損失として4521億円の貸倒引当金の積み増しを行った結果、中間純損失は4844億円の計上を余儀なくされ、債務超過に転じた。Bの平成7年9月末現在の貸借対照表は次のとおりであり、4788億0300万円の資本欠損が生じている(なお、▲は資本欠損を示す。)。”
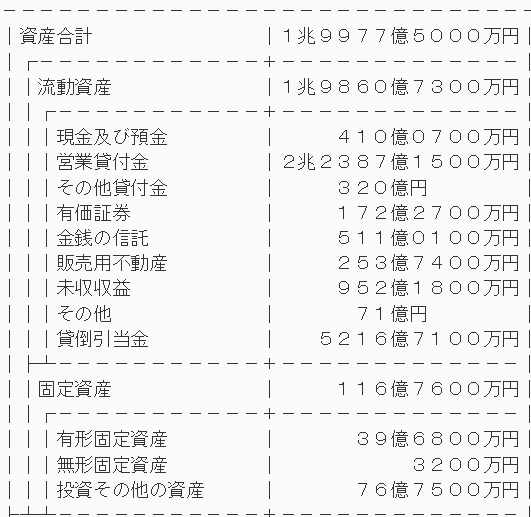
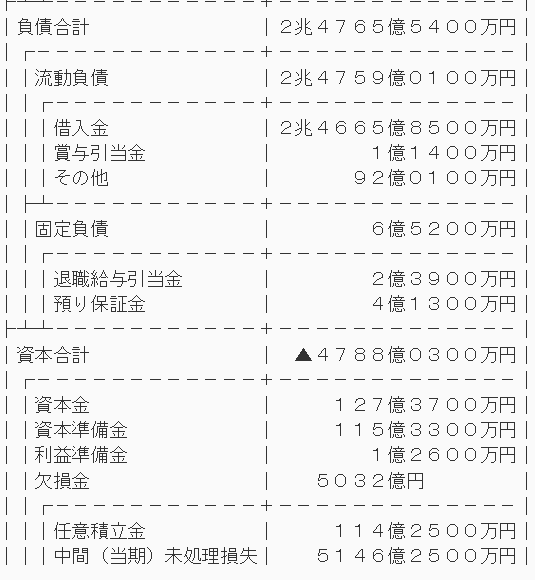
これに伴って、本件事業年度の期末貸付金残高は2兆1669億円となり、期末総資産は前期比1兆4492億円減の1兆0817億円となった。損益面については、延滞債権の増加及び金利低下等による貸付金利息の減少から、営業収益は、807億円と前期比14.1パーセントの減収となり、一方、営業費用は、本件事業計画に従って借入金利を減免されたが、有価証券関係費用297億円及び債権償却費304億円を計上した結果1447億円となり、経常損失は638億円となった。
そして、政府の住専処理案に沿った借入債務の免除益等の特別利益3762億円及び貸倒引当金繰入額等の特別損失1兆3241億円を計上した結果、当期純損失は1兆0117億円となった。Bの平成8年3月末現在の貸借対照表は次のとおりであり、1兆0060億9200万円の資本欠損が生じている(なお、▲は資本欠損を示す。)。

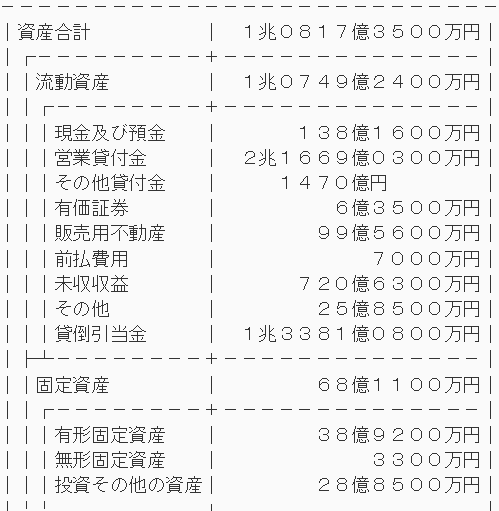

“なお、本件事業年度において、本件債権放棄がされたことから、Bは、本件事業年度において、3760億5500万円の債務免除益を計上している。
原告の内部では、早い段階から本件新事業計画は単なる時間稼ぎにすぎず、Bはやがて資金繰りが行き詰まって破綻に至るものとの見通しが支配的であって、そのような事態への対応が検討されており、平成6年11月21日には総合企画部において「住専問題の現状と今後の対応について」と題する書面を作成し、Bは整理せざるを得ないとの見方も示されていた。さらに、前記6(二)のとおり、大蔵省による第二次立入調査の結果から本件新事業計画の破綻が外部的にも明らかになり、平成7年9月には、前記6(三)のとおり、政府・与党からも早期に住専処理策を策定するように求められた上、前記(一)(1)のとおり、Bの平成7年度上半期の財務状況が非常に厳しいものであった。
このような事態にかんがみ、原告においては、Bに対する債権を平成8年3月期決算において全額貸倒れ処理するほかないと決断し、同年11月27日、自社の中間決算報告の記者会見においてこの方針を公表するとともに、赤字の額をできるだけ圧縮するため、同月以降含み益を実現する目的での株式売却を行い、その利益の額は平成8年3月までの間に合計4603億円に達した。”
“平成8年2月以降、大蔵省の主催で住専処理案の実行に伴う事務的・細目的事項の詰めを行う母体行代表者会議が行われ、同年3月21日には、Bの母体である本件母体五社が本件閣議決定及び本件閣議了解で示された政府処理案に沿ったBの具体的処理案を検討し、平成8年3月期末を迎えるに当たって、同期末時点での関係金融機関の債権額及び政府処理案に基づく債権放棄予定額を計算し、これを案内する内容の「B株式会社の損失処理に関するご連絡」と題する書面(本件損失に関する連絡)をBのすべての一般行に送付した。
本件損失に関する連絡には、これに意見等がある場合には、同月25日までに連絡してほしい旨の記載がされていたが、一般行から特段の意見は表明されなかった。Bは、同月26日、臨時取締役会を開催し、会社再建を断念し政府案に沿った諸手続を進めること、本件母体二行及び一般行に対して債権放棄の要請を行うことを決定した。
そして、同日、原告に対し、「お願い書」と題する書面を発し、Bの同日開催の取締役会において再建を断念せざるを得ないという結論に達したこと、今後本件閣議決定及び本件閣議了解により決定された住専処理策に従ってBを整理・解散する方向で準備を進めていくことを説明した上で、原告に対し、政府処理案に従ったB債務の全額を免除することを要請した。
また、一般行に対しても、B債務の一部を免除することを要請した。本件母体五社は、同月29日、①母体各社は、本件閣議決定及び本件閣議了解で示された政府案に基づき、Bの営業譲渡及び解散を行うために必要な手続を進めるものとし、その実施細目については、B及び母体各社で誠意を持って協議するものとすること、②母体各社は、右の手続の一環として、Bの取引金融機関の債権放棄額を確認し、原告及びE銀行は、Bの営業譲渡の日までに債権放棄額に対応する貸出債権を全額放棄するものとすることを確認し、同日付けの書面を作成した。”
“原告は、同日、取締役会を開催し、B向けの母体行債権の全額を債権放棄することを決議し、同日付けで、Bとの間で、債権放棄約定書を締結し、本件債権放棄をした。右の債権放棄約定書は、同約定書添付の別表記載の貸付債権(元本合計金3760億5500万円)及びこれに付帯する利息債権を含む一切の権利を対象債権として、原告が、右対象債権を、同日付けでBの「営業譲渡の実行及び解散の登記」が平成8年12月末日までに行われないことを解除条件として、放棄することとし、Bはこれを承諾すること(第2条)、原告は、右の債権放棄に伴い、対象債権に付帯する一切の担保権及び保証債権が消滅することを確認すること(第3条第1項)、第3条第1項の他、原告がBに対して根抵当権、根質権、包括的な譲渡担保権、根保証債権等、対象債権を担保する包括的な物的・人的担保権を有する場合、原告は、このすべてを同日放棄することとし、Bはこれを承諾すること(第3条第2項)、原告とBは、第2条の解除条件が成就した場合、その解除の効果は平成8年12月末日の経過をもって発生することを確認すること(第4条)等を内容とするものである。
なお、この会議の際に配付された資料中には、本件事業年度末に債権放棄をする合理性について、「仮に政府案の不成立により法的整理となっても、平等弁済の主張は社会的責任不履行による信用失墜を招きかねず、何れにしても債権放棄は不可避」と記載され、また、第4条の解除条件について、「実際上想定し難い破産の場合(プロラタ配当)との比較において、本行に損害を与えたとの代表訴訟上の主張誘発を防止する効果」があるとの説明がされていた。また、原告とBは、同日、右の債権放棄約定書第2条について、①営業譲渡の実行とは、営業譲渡契約において定められる営業譲渡日に行われる資産譲渡等を意味する、②平成8年12月末日までにBの営業譲渡の実行又は解散の登記のいずれか一方しか行われない場合には、解除条件は成就したものとするとの覚書を締結した。”
“原告が本件母体五社の幹事としてBの一般行に送付した本件損失に関する連絡によると、Bの処理スキームは以下のとおりであった。
すなわち、Bは、正常資産と不良資産のうち回収が見込まれる資産を住専処理機構に譲渡し、損失及び欠損が生ずる見込みである不良資産は、母体行、一般行及び系統の負担によって処理するとされている。具体的には、不良資産のうちの損失見込額1兆3588億円及び欠損見込額187億円の合計1兆3775億円について、本件母体二行がBに対する債権を全額放棄することによって5370億円を負担し、一般行はBに対して有している債権の合計9264億円のうち4999億円を債権放棄することによって同額を負担し、系統が3407億円を贈与することによって同額を負担することとされている。一般行がBに対して有している債権の合計9264億円のうち、債権放棄する4999億円を除いた4265億円及び系統がBに対して有している9933億円は返済されることとされている。不良資産からの回収見込額は4944億円とされていたが、不良資産は将来的にさらに劣化する懸念があることから、住専処理機構に対する最終資産譲渡額には不確定要素があり、一般行の債権放棄額は、本件損失に関する連絡が送付された平成8年3月21日時点では変動する可能性があった。右の処理スキームによると、正常資産及び不良資産のうち回収が見込まれるものの合計額は、1兆2103億円であり、実質的に一般行及び系統に返済される合計額(一般行及び系統がBに対して有する債権から、一般行の債権放棄額及び系統の贈与額を除いたもの)は、1兆0791億円ということになる。
前記第二の一4記載のとおり、住専処理に係る公的資金6850億円を盛り込んだ平成8年度予算案が、平成8年4月11日に衆議院本会議で、同年5月10日に参議院本会議でそれぞれ可決され、また、同年6月18日には、住専処理法が成立し、同月21日施行された。これを受けて、Bは、同月26日、株主総会における特別決議により、解散及び営業譲渡に関する定款一部変更の決議をし、同年8月31日に、Pとの間で営業譲渡契約を締結した上で、同年9月1日解散した。”
“本件債権を全額回収不能と評価することの可否
本件においては、原告が、本件債権相当額を本件事業年度において損金の額に算入して本件確定申告をしたのに対し、被告は、第一に、本件債権は平成8年3月末時点においてその全額が回収不能とは認められないこと、第二に、本件債権放棄に解除条件が付されているから本件事業年度に本件債権放棄が確定しているとは認められないことを理由として本件債権相当額を本件事業年度の損金の額に算入することはできないとしている。”
“この二つの理由は、双方ともに正当なものと認められてはじめて被告の本件再更正処分が維持できるという関係にある。すなわち、本件債権相当額を本件事業年度において損金の額に算入することができるかどうかは、まず第一に、本件債権が、本件事業年度の終了する平成8年3月末時点までにその全額が回収不能となっていたかどうかに係るのであって、この点が肯定できれば、本件債権放棄の有無及びその効力を問わず、本件債権相当額を損金に算入することができるというべきであるから、第一の理由が否定されれば、第二の理由の成否にかかわらず、本件再更正処分は違法なものというほかないのである。”

“したがって、本件においては、まず、本件債権が平成8年3月末時点までにその全額が回収不能と認められるかどうかを検討し、これが認められない場合にのみ、本件債権放棄の効力との関係で、本件債権相当額が損金に算入されるかどうかを検討すれば足りることとなる。そこで、以下、本件債権が全額回収不能となっていたか否かを検討する。”
“法人の各事業年度の所得の金額は、当該事業年度の益金の額から当該事業年度の損金の額を控除した金額とするものとされ(法人税法22条1項)、損金に該当するものは、①当該事業年度の収益に係る売上原価、完成工事原価その他これらに準ずる原価の額、②右①に掲げるもののほか、当該事業年度の販売費、一般管理費その他の費用の額、③当該事業年度の損失の額で資本等取引以外の取引に係るものであり(同条3項)、その額は一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従って計算されるものと規定されている(同条4項)。したがって、法人の有する金銭債権が回収不能になったことによる損失の額は、各事業年度の所得の計算上損金の額に算入されることとなる(法人税法22条3項3号)が、法人税法33条2項が、金銭債権について評価損の計上を禁止していることにかんがみると、金銭債権が回収不能になったことによって損金の額に算入することができるのは、金銭債権の全額が回収不能である場合に限られるものと解される。法基通9-6-2もこのことを明らかにしているものと解される。”
“ここでいう債権の全額が回収不能か否かについては、法人税法が法人の合理的な経済活動によってもたらされる利益に着目して法人税を課していることからすると(法人税法4条)、合理的な経済活動に関する社会通念に照らして判断するのが相当である。被告は、回収不能というためには、債務者の資産状況、支払能力等から当該債権の回収が事実上不可能であることが客観的に明らかでなければならないとし、具体的には、強制執行、破産手続、会社更生、整理といった回収不能を推定し得る法律的措置が採られた場合及びこれに準じるような場合、すなわち債務者の死亡や所在不明又は事業閉鎖というような回収不能の事実が不可逆的で、一義的に明白な場合に限られると主張する。
確かに、被告主張のような場合が回収不能に当たることは明らかであるが、このような場合に該当しない限り、必ず強制執行等の法的措置を講じて回収不能か否かを明らかにすることを要求することは、納税者に対して無益な費用と時間を費やさせるものであって経済的にみて非合理的な活動を強いるものと評価せざるを得ない場合もあると考えられる。”
“すなわち、法的措置を講ずれば、ある程度の回収を図れる可能性がないとはいえない場合においても、債務者の負債及び資産状況、事業の性質、債権者と債務者との関係、債権者が置かれている経済的状況、強制執行が可能な債務名義が既に取得されているか否か、これを取得していない場合には、債務者が債権の存在を認めているか否かなど債務名義取得の可能性の程度やその取得に要する費用と時間、強制執行が奏功する可能性とその程度、法的措置をとることに対する債務者等の利害関係人からの対抗手段等の発生が予想されるリスクとの対比等諸般の事情を総合的に考慮し、法的措置を講ずることが、有害又は無益であって経済的にみて非合理的で行うに値しない行為であると評価できる場合には、もはや当該債権は経済的に無価値となり、社会通念上当該債権の回収が不能であると評価すべきである。”
“これを本件についてみるに、以下のとおり、本件債権は、平成8年3月末までには社会通念上回収不能の状態にあったものというべきである。
前記一10(四)のとおり、平成8年3月21日に発送された本件損失に関する連絡記載のBの処理スキームにおいて、正常資産及び不良資産のうち回収が見込まれるものの合計額は1兆2103億円とされ、一般行及び系統がBに対して有している債権の9264億円及び9933億円の合計1兆9197億円をはるかに下回っており、当時の不動産市況及び一般に破綻した会社の資産は破綻時の評価額からさらに劣化しがちであることからすると、平成8年3月末時点はもとより、将来的にも、本件母体二行がBに対する債権を全額放棄したとしても、一般行及び系統の債権の全額を返済することは不可能であったことも明らかである。”
“住専問題の処理に当たっては、前記一6(三)、7のとおり、平成7年10月2日ころまでには、住専七社のいずれについても整理・清算する方針がまとまったものの、住専処理によって生ずる損失を住専の債権者である母体行、一般行及び系統でどのように負担するかをめぐってそれぞれの意見が対立し、特に、系統は、母体行が住専処理の損失をすべて負担するという完全母体行責任を主張し、母体行が住専に対して融資している債権の放棄を行うことを限度とする修正母体行責任を主張する母体行との間で激しく意見が対立していた。
本件新事業計画は、被告の主張するとおり、あくまでも再建に関するものであって整理に関するものではないが、原告は、再建計画に責任をもって対処するとの意思を表明したことによって、系統等との関係で、Bを計画どおりに再建させることができず、系統の債権の元本を同計画に従って返済させることができなかった場合には、そのことに関し信義則上の責任を追及されかねない立場におかれ、系統もこの点を考慮して住専七社全体に対して年間840億円にものぼる金利減免という多額の負担に応じたとみるのが相当であるから、本件新事業計画が失敗に終わった以上、系統が右のように主張することは無理からぬ面があるというべきである。”
“原告も、このような面を考慮し、プロラタ負担によるべきであると主張したり、自己の責任を全く否定するということはせず、株式会社としてできる限界があるとして、完全母体行責任を追及する系統に対し、本件債権の全額放棄以上の責任をくい止めようとしていたにすぎない。
すなわち、原告がBに対して有する債権の全額を放棄せざるを得ないことは、原告はもとより関係者の共通の認識であり、同社の処理を考えるに当たっての当然の前提として、それ以上の負担をいかにくい止めるかということを問題としていたというべきである。”
“また、当時はバブル崩壊後の不良債権の処理が国内外で重要な課題になっていたところ、とりわけ、住専処理の問題は、その損失が巨額に上る上、経営基盤が必ずしも盤石でない系統が住専七社に対して巨額の貸付をし、その処理策いかんによっては日本の金融システムに多大な影響を及ぼすおそれがあったことから、日本経済の行方にとって重大な懸案事項となっており、本件閣議決定及び本件閣議了解において多額の公的資金導入の方針が打ち出されたことから、政治問題化し、公的資金導入の可否をめぐって与野党間に鋭い対立があった。”
“しかし、前記一9のとおり、少なくとも、母体行が住専各社に対して有する債権の全額を放棄すべきことについては、与野党の考え方は一致しており、マスコミの報道及び一般世論もこの点について異論はなかったし、平成8年2月15日に衆議院予算委員会に参考人として招致された原告の〈A〉頭取が、母体行としては3兆5000億円という母体行債権の全額を放棄すると述べたことからすると、原告がBに対する債権を放棄しないことは、社会全体を敵に回すに等しく、社会的存在としての銀行としては自己にとってこの上なく有害な行為というほかない上、代表者の言を翻すことによる社会的信用の失墜という面からも、もはや社会通念上許されない状態になっていたものというべきである。”
“以上のとおり、本件新事業計画の破綻の後、Bの資産は、一般行及び系統の債権についてさえその全額を弁済するには不足していた上、住専処理問題は政治問題化し世間の注目を集めていたところ、原告は、系統から信義則上の責任を追及されかねない立場に陥っており、これを避けるには本件債権を放棄するほかないと認識し、これを公にしていたし、このことは、関係者間の共通の認識であったばかりか、政府与党はもとより、この問題に対して厳しい姿勢で臨んでいた野党やマスコミ及び一般世論においても異論がなかったことからすると、少なくとも、平成8年3月末までの間に、原告は、本件債権を回収することが事実上不可能になっていたものというべきであり、本件債権は、本件事業年度において、社会通念上回収不能の状態にあったものというべきである。
また、仮に政府の住専処理策が成立せずBを破産手続によって処理せざるを得ない事態が予想されたとしても、原告が債権届出をしてその手続に参加することは、法的にみても不可能に近く、法的には可能であったとしても、原告にとって有害かつ無益であって経済的にみて非合理的で行うに値しない行為というほかないから右の判断を左右するものではない。”
“被告は、平成8年3月末の時点においては、政府の住専処理案の成否が未定であり、法的な処理によることになれば原告が本件債権を回収する道も残されていたと主張するが、以下のとおり、被告の主張は採用することができない。”
“被告は、政府の住専処理案の成否は、平成8年3月末には未だ流動的であったと主張し、一般に、ある処理策が決定するまでには、基本的事項から周辺事項へというように各部分ごとに順次定まっていき、周辺事項は基本的事項を前提として決定されていくのが通常であるものの、それが不可分一体の案である以上、全体が決定され実施に移されるまでは基本的事項、周辺事項を含めて案の一部にすぎず、実施に至らなければそれまでに定まった部分を含めて白紙に帰することになるとした上で、政府の住専処理案で提示された損失負担割合はあくまで同処理案の実現を前提とするものであって、同処理案が実現せず法的整理手続に移行した場合には白紙に戻り、債権者平等の原則による配当の可能性が残されていたと主張する。”
“また、政府の住専処理策に係る国会審議において、野党側議員は一貫して公的資金投入についての疑問や強力な批判を繰り返し、平成8年度予算も、問題を住専処理法案の審議に先送りすることにより平成8年5月10日にようやく成立をみたものであること、公的資金投入に対する世論の反対は極めて強かったこと、関係金融機関が政府の住専処理案に必ずしも合意していなかったことなどによると、平成8年3月末において、政府の住専処理策が実現するか否かについては予断を許さない状況にあったと主張し、原告ら母体行が、本件債権のような母体行債権を全額放棄することになるかどうかは流動的であったと主張するようである。”
“確かに、政府の住専処理案が母体行債権の全額放棄、一般行債権の一部放棄、系統債権の全額弁済と系統による贈与、住専処理に伴う損失の公的資金による補てんなどの要素から構成される一つの処理案であって、その一部分でも成立しなければ、処理案が全体として成立しないことは明らかである。”
“しかしながら、母体行債権の全額放棄という点については、前記のとおり、本件新事業計画が失敗に終わった以上、信義則上、いかなる処理がされるとしても当然の前提とされるべきことであったということができるから、同処理案として成立しないからといって、この点までが全くの白紙に戻るということはできない。”
“また、本件においては、右3(三)に記載のとおり、住専処理問題は政治問題化しており、新進党及び共産党は、政府の処理案について、公的資金を導入する点については反対していたものの、住専処理に当たって、母体行の責任を追及しようという点では一致しており、むしろ、政府の住専処理案以上に母体行の責任を強調していたのであるし、マスコミや世論の動向もこれとほとんど同様であり、政府の住専処理案に関する議論の対立点は、公的資金を導入することの是非をめぐるもので、それに関連して、母体行に政府の住専処理案以上の責任を負担させるかどうかにあり、母体行がその債権を全額放棄すべきことには争いがなかった。
これに加え、衆議院予算委員会に参考人として招致された原告の〈A〉頭取が、母体行債権の全額を放棄すると述べたことをも併せて考えると、仮に政府の住専処理案が全体として成立しないとしても、新たな処理案において、母体行債権の全額放棄を盛り込む形で住専処理策が策定されることは確実であったというべきであって、平成8年3月の段階で政府の住専処理案が採用されるかどうかが流動的であったからといって原告が本件債権を回収することが社会通念上不可能であったとの結論に影響があるものとはいえない。”
“被告は、新進党が、住専処理法案の審議に当たり、公的資金の導入に反対し、会社更生法の適用による法的整理を独自の対案として提言していたこと、〈t〉大蔵大臣(以下「〈t〉大蔵大臣」という。)が、平成8年6月13日の衆議院金融問題等に関する特別委員会において、政府の住専処理案が白紙に戻ると法的処理によらざるを得ないが、法的処理を行うとすると債権者が損失を平等に分担することになる旨述べていることから、住専処理法が成立せず、政府の住専処理案が実現されない場合には、破産手続等の法的処理による可能性が高く、そうなると住専に対して融資をしている各金融機関がその債権額に応じて平等の割合で損失の負担をすることとなる可能性が高い旨主張する。”
“しかしながら、新進党は、平成8年3月13日に示した「住専問題に関する具体的方針」において、住専各社の経営破綻の処理は会社更生法の適用による法的処理によることを提案しているものの、同時に、法的処理において住専各社の経営破綻に母体行が重大な責任を負っている経緯を十分に踏まえた実質的公平の実現を図ることを挙げ、また、右に先立ち平成7年10月17日に発表した新進党案では、母体行が全責任を負う「完全母体行責任」又は母体行が債権を全額放棄し、不良債権を圧縮し、残った資産を受け皿会社に移行する方式を採用すべきであるとし、平成8年2月27日に発表した「住専問題に関する基本方針」では、母体行は住専の経営破綻に至った経緯にかんがみ、最大限の責任を果たすべきであるとするなど、一貫して母体行の責任を追及する姿勢を見せており、新進党の案に従って住専処理を法的処理で行うとしても相応の母体行責任を追及することとなり、母体行は、少なくとも、住専に対する母体行債権の全額の放棄を迫られることは必至であったというべきである。”
“また、住専問題に対する国会等の対立点は、6850億円もの公的資金の導入と関連して、修正母体行責任に限定した上で公的資金を導入すべきか、それとも、母体行により多くの責任を負担させるべきかという点にあったというべきであり、右の被告が指摘する〈t〉大蔵大臣の答弁は、政府の住専処理案が成立せず破産処理になると、母体行により多くの責任を負担させることはおろか修正母体行責任すら追及できなくなるとして、政府の住専処理案に反対する野党を牽制するためにされたものにすぎないというべきである。”

“系統の責任を追及するマスコミの論調も存在したが、これも、公的資金の導入との関係で主張されていたものにすぎず、母体行の負担を軽減すべきであるという議論が存在したとの証拠は見当たらない。これらのことからすると、仮に住専処理法案が成立しないにしても、母体行がその債権の回収を図ることを是認するような解決策が策定される可能性は全くなかったというほかない。”
“なお、住専処理法案が成立せず、何らの処理方策も定められなかった場合には、住専各社は破産法に基づいて処理せざるを得ない状態であったが、この処理手続において債権者が自己の債権を回収するには債権届出をしなければならないところ、一般に、破産裁判所においては、破産会社の経営者等破産に至ったことに責任を有する債権者については、債権届出の取下げを求め、又は異議を述べるよう破産管財人に指導しており、破産管財人がこれに応じた行動を取ることにより、右のような債権者の多くが実際上債権届出を取り下げざるを得ない事態に至ることは、当裁判所に顕著な事実であり、あくまで債権届出を取り下げなかったとしても、このような債権者については債権確定訴訟において信義則違反を理由に債権届出自体が認められなかった裁判例も存在するところである。”
“そして、原告については、前記一1のとおり、Bの設立に関与した経緯、独占禁止法で許容される上限までBの株式を保有していたこと、Bに対して役員及び職員を派遣し、また、多額の融資をすることによって、Bの経営に深く関与していたこと、前記一2のとおり、Bの設立当初Bが金融機関から融資を受ける際には原告が保証を行っていたこと、原告がBの債務を保証する方式から集合債権譲渡担保を準共有する方式に変更になった後についても、原告が担保協定スキームの幹事となっていたこと、第一次再建計画、本件新事業計画の策定に前後して、原告が、系統等に対して、Bに対する融資残高を維持するように働きかけ、その過程で原告がBの再建を支援していくとの表明をしたことなどの事実関係からすると、原告は、本件新事業計画を達成できなかったことにつき、系統等から信義則上の責任を追及されかねない立場にあったというべきであるから、Bの破産手続において、原告が債権届出をしてその債権を回収することは、法的にみても不可能に近く、かつ、仮にそれが法的には可能であったとしても、回収に要する時間及び費用は多大なものとなることが予想されるし、その挙に出たことに対する社会全体の批判ばかりか、これによって債権回収額の減少する一般行や系統からの対抗手段としての損害賠償請求訴訟の提起も予想されることからすると、有害かつ無益であって経済的にみて非合理的で行うに値しない行為というほかないから、本件債権はこのような手続を経るまでもなく経済的に無価値になったものというべきである。”
“本件債権については、前記二で説示したとおり、平成8年3月末の時点で既に全額回収不能の状態にあり経済的な価値はなくなっていたと評価すべきであって、債権放棄の有無にかかわらず、その全額を損金に算入できるものというべきであるから、争点2についてはもはや判断を示す必要はないというべきであるが、被告は、全額回収不能と評価し得る場合を厳格に限定する見解を前提として、本件債権が右時点で全額回収不能の状態にあったことを争っているので、念のため、仮に被告の右見解を前提として、本件債権放棄による損金算入が認められるか否かについても判断を示すこととする。”
“債権放棄による損金算入と法人税法の定め法人税法37条は、法人がした無償による経済的利益の供与は、同条6項かっこ書に記載するもののほか、名目のいかんにかかわらず寄付金とし、同条2項にいう損金算入限度額を超える金額は損金に算入しない、としている。
そして、債権放棄は、その理由のいかんを問わず、同条6項かっこ書に記載された費目のいずれかに該当するということは困難であるから、これを債務者に対して無償で経済的利益を与えるものと評価すると、法人税法上、その債権相当額を損金算入限度額を超えて損金に算入することはできないというほかない。”
“しかし、債権放棄は様々な理由によってされるものであって、その中には債務者に経済的利益を与えること自体よりも、それによって自社の利益を図ることを主たる理由としてされる場合もあると考えられる。このことからすると、債権放棄のすべてについて無償のものと評価するのは妥当性を欠くというほかないのであり、債権放棄の理由が、単なる任意の利益処分にとどまらず、経済的にみて合理的であり、税法上これを損金と評価しないことが納税者に対して経済的にみて無益又は有害な行動を強いることとなるなど不合理な結果を招くと認められる場合には、その無償性を否定し、寄付金に該当しないとし得るものというべきである。”
“この点については、被告も前記第二の三1(被告の主張)(一)(6)において任意の利益処分といえない場合には損金に算入することができるとしており、課税庁においては、従来から経済的合理性の認められる一定の場合には債権放棄の寄付金該当性を否定するとの取扱いを行っている(法基通9-4-1)が、この取扱いは、このような解釈を前提としてはじめて法人税法に適合する適法な運用ということができるのである。このように債権放棄による損金算入の可否は、それが法人税法37条にいう無償による経済的利益の供与に該当するか否かという法解釈によるべき問題であり、課税庁の定める通達はこの解釈に適合する限度でのみ適法と評価されるのであるから、法基通所定の事由に該当しないことのみをもってその損金該当性を否定することは許されないのであって、前記のように、債権放棄の理由が経済的にみて合理的であって、これを損金と評価しないことが納税者に対して経済的にみて無益又は有害な行動を強いることとなるなど不合理な結果を招くと認められる場合には、これを損金に算入するというのが法人税法の定めに合致した正しい法解釈というべきである。”
“本件債権放棄の理由原告が本件債権放棄をするに至った理由は、前記認定の事実関係、特に、第一次再建計画及び本件新事業計画をめぐって系統に融資残高の維持を要請し、また、大蔵省に対して念書を差し入れた経緯、B処理に関する系統との協議において、系統側から完全母体行責任による処理を求められ、母体行の責任を追及する動きが非常に厳しかったこと、政府の住専処理方策が策定された経緯、国会等において母体行の責任が追及され、〈A〉頭取が参考人として招致された衆議院予算委員会で、母体行債権の全額を放棄する旨述べていること、原告が、Bに対する債権を平成8年3月期において全額貸し倒れすることを決断し、平成7年11月27日に自社の中間決算報告の記者会見において公表したこと、本件債権放棄を決議した原告の取締役会において配付された資料には、本件事業年度末に債権放棄をする合理性について、「仮に政府案の不成立により法的整理となっても、平等弁済の主張は社会的責任不履行による信用失墜を招きかねず、何れにしても債権放棄は不可避」との説明がされていたことからすると、平成7年9月、新事業計画の失敗が明らかになった時点までには、新事業計画を達成できなかったことにより、母体行としての責任を果たす意味から系統や一般行の受ける損害をできるだけ軽減するために少なくとも自己の債権回収は諦めざるを得ないとの判断に至り、さらに本件債権放棄の時点までには、政府の住専処理スキームに従ってBを処理するのが最善の途であり、仮にこのスキームが成立しない場合にも、破産手続において自己の債権の回収を図ることは、仮にそれが法的に可能であっても、それに要する費用と時間は多大なものとなり、社会全体からの批判を受けるおそれもあったばかりか、系統や一般行という多くの同業者から信義則に反するとの非難を受け、さらには損害賠償請求を誘発し、回収可能額を超える損害を発生させるという結果を招くおそれがあるとの判断の下に、むしろ債権放棄をすることによって、それ以上の責任を追及されることによる負担の増加をできるだけ避けるのが得策であると判断したことによるものと認めるのが相当である。”
“原告が本件債権放棄を行わず、本件債権についてその一部でも回収するような動きに出た場合には、与野党双方及び世論の反発を招き、当時銀行に対する監督権限、免許の取消権限を有していた大蔵大臣ないし大蔵省の方針に反するものであり、また、機関投資家として、原告の金融債を引き受ける立場にある系統の反発を招き、原告が有形・無形の不利益を被るおそれがあることは明らかであって、そのような事態に至れば、銀行業を営む原告に計り知れない打撃を与え、経済的損失もばく大なものに上ることは明らかである。そうすると、右のような理由により本件債権放棄をすることは、経済的にみて合理的であって、これを損金と評価しないことは、納税者に対して、損害を顧ずに債権を行使することを命じているに等しく、経済的にみて無益かつ有害で非合理的な行動を強いる結果を招くことになるというべきである。”
“なお、被告は本件債権放棄の目的が多額の株式売却益に対する課税を回避することにあったと主張しており、確かに本件債権相当額を損金に算入しない場合には右のような課税がされる関係にあったことは明らかである。しかし、前記認定の事実関係によると、原告が多額の株式売却益を発生させたのは、本件債権はもはや回収できず本件事業年度において償却せざるを得ないと判断したことにより、それによって発生する欠損をできるだけ少なくするためにやむを得ず保有株式の含み益を現実化させたものであって、本件債権放棄は償却の一方法として選択されたものであるから、むしろ株式売却益の計上が債権放棄等何らかの方法による本件債権の償却を前提としてされたというべきであり、被告の主張は、このような事実の流れを考慮せず、最終的な時点における両者の関係のみをとらえているというほかない。”
“また、保有株式の含み益は、いわゆるバブル経済崩壊後の厳しい経済状況の下においては、原告にとって経営体力を維持するために非常に貴重なものであって、できる限り現実化させず温存すべきものであるから、これを敢えて現実化させたことは、まず本件債権は回収できず償却せざるを得ないという確固たる判断があり、株式売却益の計上はその判断に従って採られた行動とみるべきものである。これらの点からすると、被告の右主張は採用できない。”
“被告は本件債権放棄に解除条件が付されていることから、これによる損失は確定しておらず損金に算入することができない旨主張する。しかし、損金算入の前提として、損失の確定を要するとしても、そこでいう確定とは、一般に税法上の権利確定主義という用語で言われる際の確定と同義のものと解すべきであって、抽象的な権利義務の発生にとどまらず訴訟において請求又は確認し得る程度に具体的に発生していることを意味するものと解すべきである。このような観点から本件債権放棄をみると、その内容は、前記事実関係からすると、民法127条2項にいう解除条件に当たり、その意思表示後条件成否未定の間も債権放棄の法的効力は発生しており、その効力は、抽象的なものではなく、訴訟においても本件債務の不存在が確認される程度に具体的に発生しているのであるから、損失の発生は確定しているというべきである。”
“被告は、本件債権放棄は、もともと一定の事実が生じたときに限り行使できる債権について、当該一定の事実が生じるか否か未定の間に、当該事実が生じないことを解除条件として債権放棄したに等しく無意味な行為であると主張する。この主張は、原告が本件債権を住専処理策の帰すうが明らかになるまで現実に行使することができないものであったことを前提とするものである。
しかし、原告は、当時本件債権の行使につき、事実上はともかく(事実上の点を考慮すれば、むしろ前記のとおりもはや回収不能の状態にあったというべきである。)、何らの法的制約も受けていなかったのであるから、本件債権放棄の法的効力を考察するに当たっては、被告の右主張はその前提を欠くものというほかない。”
“また、被告は、賃料増額請求との対比から解除条件成否未定の間は法的効力が確定していないと主張しているが、賃料増額請求は賃借人がこれに応じない限り請求がされた時点では具体的な賃料額は定まらず、裁判所の判決確定によってはじめて具体的な賃料額が形成されるのに対し、解除条件付債権放棄は条件成否未定の間も債権放棄の効力は具体的に発生しており、当事者間に争いがあって裁判所がその判断をするとしても、当該判断は既に存在する権利状態を確認するにすぎないものである。このように被告の対比するものは全く性質を異にするものであり、右主張は採用できない。”
“さらに、被告は本件債権は既に利息が免除されていたから解除条件付債権放棄は経済的には停止条件付債権放棄と異ならないと主張するが、停止条件付債権放棄では、条件成否未定の間は債権が依然として存在しこれを行使することができ、例えば、自ら破産申立てをするなどして政府の住専処理スキームを瓦解させることも可能なのに対し、解除条件付債権放棄ではこのような行動に出ることはできず、単に住専処理スキームの成否を静かに見守るしかないという点で大きな違いがあるというほかなく、右主張は取るに足らないものというほかない。
このように本件債権放棄の効力は、既にそれがされた時点において確定的に発生したと認めることができ、しかも、その理由は、経済的にみて合理的であって、これを損金と評価しないことは、納税者に対して経済的にみて無益かつ有害な行動を強いる結果を招くこととなると考えられるから、これを無償による経済的利益の供与として損金算入を否定することはできず、原告は本件債権放棄によってその債権相当額の損失を受けたものと評価すべきである。”
“過少申告加算税賦課決定処分の取消しを求める趣旨について証拠によると、被告は、平成8年8月23日に、法人税額を1251億3721万2200円とし、これにより納付すべき税額を1285億1210万6600円、これに対する過少申告加算税額を191億9263万3500円とする本件更正処分及び本件第一過少申告加算税賦課決定処分をしたこと、平成10年3月31日に、法人税額を1273億1637万8200円とし、これにより納付すべき税額を21億7916万6000円、これに対する過少申告加算税額を3億1919万7000円、重加算税額を311万8500円とする本件再更正処分、本件第二過少申告加算税賦課決定処分及び本件重加算税賦課決定処分をしたことが認められる。”
“本件更正処分は、本件再更正処分に吸収されるが、本件第一過少申告加算税賦課決定処分と本件第二過少申告加算税賦課決定処分は、それぞれ、本件更正処分、本件再更正処分によって納付すべきことになる税額に対応して決定されており、両者は別個の処分というべきである。”
“そうすると、本件において、取消訴訟の対象となる処分は、本件再更正処分、本件第一過少申告加算税賦課決定処分、本件第二過少申告加算税賦課決定処分及び本件重加算税賦課決定処分であるというべきである。原告は、本訴において、被告が平成10年3月31日付けでした原告の平成7年4月1日から平成8年3月31日までの事業年度の法人税の再更正処分のうち欠損金額118億7390万0838円を超える部分並びに過少申告加算税変更賦課決定処分及び重加算税賦課決定処分を取り消すことを求め、過少申告加算税変更賦課決定処分という処分が存在することを前提としているが、かかる処分は存在しないため、請求の趣旨のうち右の部分は取消しを求める処分が存在しないので不適法との疑念が生じないでもない。”
“しかし、原告の平成12年10月31日付けの「求釈明申立に関する回答書」によると、原告が取消しを求めている過少申告加算税賦課決定処分は、本件第一過少申告加算税賦課決定処分及び本件第二過少申告加算税賦課決定処分を合計した195億1183万0500円であることは明らかであって、原告は、右の二つの過少申告加算税賦課決定処分の取消しを求めているものと善解できる。五結論前記二及び三のとおり、本件債権は、平成8年3月末までに社会通念上全額回収不能となっており、仮に回収不能でないとしても、本件債権放棄によってその全額を損金に算入すべきものであるから、法人税の計算において、本件債権相当額3760億5500万円を損金の額に算入した原告の本件確定申告は適法である。”
“右金額を損金の額に算入すると原告の所得金額はマイナスとなることは明らかであるから、右金額を損金の額に算入することができないとしてされた本件再更正処分は、その余の点を判断するまでもなく、違法なものとして取り消しを免れないし、本件再更正処分によって新たに加えられた更正理由を考慮しても、原告には納付すべき税額が発生しないことが明らかであるから、過少申告加算税及び重加算税を賦課されるいわれはなく、結局、本件再更正処分等は、争点3について判断するまでもなく、いずれも取消しを免れない。
よって、原告の本訴請求は理由があるからこれを認容することとし、訴訟費用の負担について、行政事件訴訟法7条、民事訴訟法61条を適用して主文のとおり判決する。”
東京高裁/平成14年3月14日判決(村上敬一裁判長)/(原判決取消し・被控訴人の請求棄却)(被控訴人上告)
“法人税法上、内国法人に対して課される各事業年度の所得に対する法人税の課税標準は、各事業年度の益金の額から損金の額を控除した所得の金額とされているところ(同法21条、22条1項)、同法22条3項は、内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の損金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、①当該事業年度の収益に係る売上原価、完成工事原価その他これらに準ずる原価の額、②当該事業年度の販売費、一般管理費その他の費用(償却費以外の費用で当該事業年度終了の日までに債務の確定しないものを除く。)の額、③当該事業年度の損失の額で資本等取引以外の取引に係るものとし、同条4項は、当該事業年度の収益の額及び損金の額に算入すべき金額は、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従つて計算されるものとする旨を定めている。”
“これは、法人所得の計算が原則として企業利益の算定技術である企業会計に準拠して行われるべきことを意味するものであるが、企業会計の中心をなす企業会計原則(昭和24年7月9日経済安定本部企業会計制度調査会中間報告)や確立した会計慣行は、網羅的とはいえないため、国税庁は、適正な企業会計慣行を尊重しつつ個別的事情に即した弾力的な課税処分を行うための基準として、基本通達〔昭和44年5月1日直審(法)25(例規)〕を定めており、企業会計上も同通達の内容を念頭に置きつつ会計処理がされていることも否定できないところであるから、同通達の内容も、その意味で法人税法22条4項にいう会計処理の基準を補完し、その内容の一部を構成するものと解することができる。”

“そして、同条項が単なる会計処理の基準に従うとはせず、それが一般に公正妥当であることを要するとしている趣旨は、当該会計処理の基準が一般社会通念に照らして公正で妥当であると評価され得るものでなければならないとしたものであるが、法人税法が適正かつ公平な課税の実現を求めていることとも無縁ではなく、法人が行った収益及び損金の額の算入に関する計算が公正妥当と認められる会計処理の基準に従つて行われたか否かは、その結果によって課税の公平を害することになるか否かの見地からも検討されなければならない問題というべきである。”
“金銭債権については、当該債権のうち経済的に無価値となった部分の金額を確定的に捕捉することが困難であるところから、法人税法上は、金銭債権については、評価減を認めないことが原則とされている(同法33条2項)。”
“したがって、不良債権を貸倒れであるとして資産勘定から直接に損失勘定に振り替える直接償却をするためには、全額が回収不能である場合でなければならず、また、同貸倒れによる損金算入の時期を人為的に操作し、課税負担を免れるといった利益操作の具に用いられる余地を防ぐためにも、全額回収不能の事実が債務者の資産状況や支払能力等から客観的に認知し得た時点の事業年度において損金の額に算入すべきものとすることが、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に適合するものというべきであり、基本通達9-6-2も、このことを定めたものということができる。”
“一方、国税庁は、昭和29年7月24日、債権の貸倒れの特例を定めた通達(同日直法-140、乙第62号証)を定め、手形取引停止処分、会社更生手続又は和議の開始の決定があった場合等に、債権金額の50パーセント相当額を「債権償却引当金」として負債の部に計上することができることとして、課税実務上不良債権の間接償却を認める道を開き、昭和39年の通達改正によって、「債権償却引当金」は、「債権償却特別勘定」と改められ〔昭和39年直審(法)89、乙第63号証〕、その後、適用範囲が拡大されて、昭和44年の基本通達にも引き継がれ、これらは、平成10年法律第24号による法人税法の改正によって、個別評価による貸倒引当金の設定制度等(法人税法52条)という形で法制化されたものであり、不良債権の会計処理としては、当該不良債権に係る回収可能性の危機的度合と段階に応じ、未だ回収不能とはいえないが、将来回収不能になることが見込まれる金銭債権については間接償却が行われ、現に回収不能であることが明らかになった不良債権については直接償却が行われるものということができる。”
“また、回収不能とはいえない金銭債権が放棄され、あるいは協議により切り捨てられた場合は、経済的利益の無償供与があったものとして、法人税法上、寄附金に該当するものとして扱われ、算入される損金の額が制限されるが(同法37条2項)、例えば、債権の回収不能部分を特定しその部分の債務を免除し又は債権を放棄した場合、損失を負担しなければより大きな損失を被ることが明らかであるためやむを得ず債権放棄を行う場合、債権者の協議等によって回収不能部分を特定しこれを原則として債権者らの債権額に案分して切り捨てた場合などには、経済取引として十分に肯首し得る合理的理由があるということができるから、そのような場合には、経済的利益の無償供与は、寄附金には当たらないものと解され、基本通達9-6-1(四)、9-4-1、9-6-1(三)もこのことを定めたものということができる。”
“その場合の損金算入時期についても、これを恣意的に早め、あるいはこれを遅らせるなどして、課税を回避するための道具として利用することは、法人税法の企図する公平な所得計算の要請に反し、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に適合するとはいえないのであって、その許されないことは当然である。”
“Bは、被控訴人、株式会社C銀行(以下「E銀行」という。)、F証券株式会社(以下「F証券」という。)、G證券株式会社(以下「G證券」という。)、H證券株式會社(以下「H證券」といい、以上、5社を「本件母体5社」という。)、元大蔵省銀行局長の壬、被控訴人出身の癸及びE銀行出身の〈I〉の合計8名が発起人となり、不動産、不動産に関する権利又は有価証券を担保とする住宅資金貸付等を事業目的として、昭和51年6月23日に設立された株式会社であり、設立に際して発行された株式総数160万株(額面金額500円)のうち、発起人は80万株(本件母体5社は各15万9000株)を、発起人以外の金融機関等43社はその余の80万株をそれぞれ引き受けた。本件母体5社のBに対する出資比率は、B設立時においては、各9.94パーセントであったが、その後の増資を経て、昭和62年10月以降は、各5パーセントとなった。また、本件母体5社は、いずれもBに対し、継続して役員及び従業員を出向させ、日本ハウジングローンの設立から昭和56年6月までは壬が、同月からBの解散までは被控訴人出身者が、代表取締役を務めた。”

“Bは、銀行等の金融機関から融資を受け、それを貸し付けるという営業形態をとっていたところ、被控訴人の貸付高が最も多く、Bの総借入残高及び被控訴人からの借入残高の推移は、それぞれ昭和52年3月期が183億円及び73億円、昭和57年3月期が4783億円及び1343億円、昭和62年3月期が1兆0377億円及び1960億円、平成元年3月期が1兆4885億円及び2915億円、平成2年3月期が2兆1290億円及び3542億円、平成4年3月期が2兆6571億円及び3791億円、平成7年3月期が2兆5183億円及び4061億円であった。
Bの母体行である被控訴人及びE銀行は、非母体行からのBへの融資について、原則として各50パーセントの分担割合で一律にその返済債務を保証していたが、昭和54年5月、大蔵省銀行局長が、一部の金融機関が安易な債務保証を行い、経営の健全性を著しく損ねた事例が見受けられたとして、安易な債務保証をしないように求める通達を発出したことを受け、昭和55年2月、Bと同社に融資している母体行を含めた金融機関との間で、Bが現に保有しあるいは将来取得する住宅ローン債権を同金融機関に譲渡して、同金融機関がこれを準共有する旨の債権譲渡担保契約を締結し、被控訴人及びE銀行による債務保証は、昭和62年3月ころまでに解消された。”
“昭和50年代後半から、都市銀行等が個人向け住宅ローンに力を入れるようになり、個人住宅ローン市場における金融機関相互の競争が激化したため、住専各社は、不動産会社等の事業者向け融資を拡大し、昭和55年度には1804億円であった住専8社(B、I株式会社、株式会社J、株式会社K、地銀L、M株式会社、N株式会社及びO株式会社)の事業向け融資残高は、平成元年度には8兆1183億円、平成3年度には10兆1456億円へと増加した。ところが、いわゆるバブル経済の崩壊により、地価が著しく下落し、不動産担保融資を主体としていた住専各社は、深刻な影響を受け、特に急激に拡大していた事業者向け融資債権の不良債権化をもたらし、平成3年度以降、住専各社の財務状況は急激に悪化した。そこで、大蔵省銀行局は、平成3年8月から平成4年8月にかけて住専各社に対する立入調査を行ったところ、Bを含む住専7社(住専8社のうち住専処理計画の対象とされなかったO株式会社を除いた7社)の不良債権総額は、合計4兆6479億円、不良債権率は約37.8パーセントであることが判明した。”
“Bの事業者向け融資残高は、平成2年度末に1兆6533億円であり、平成3年11月末の時点での要管理債権は、総額1兆2482億円と総貸付金残高2兆4028億円の約52.0パーセントを占めるようになり、また、大蔵省銀行局の上記立入調査によれば、平成4年8月31日時点の総貸付金残高2兆3638億円のうち不良債権額は、1兆2694億円であることが明らかとなった。そして、平成2年度には35億6800万円あったBの税引前当期利益は、平成3年度には5億2400万円へと減少し、さらに、平成4年度には150億2700万円、平成5年度には71億3000万円の各税引前当期損失を計上した。”
“Bは、平成4年1月末に大蔵省から経営再建計画の作成を求められ、同年5月、本件母体5社に再建計画期間である平成8年度までの金利減免と必要資金の追加融資を、非母体行に融資残高維持及び担保条件の現状維持をそれぞれ要請し、資産の圧縮等を目指す第1次再建計画を策定した。そこで、被控訴人は、Bの同再建計画の推進を支援するために、独自に①緊急融資枠1000億円の設定、②住宅抵当証券取得限度枠400億円の設定、③公定歩合(3.25パーセント)までの金利の減免からなる対応策を策定したが、非母体行の中には、Bに対する融資の回収や保全に向けた姿勢を示すところも現れたため、被控訴人及びE銀行は、平成4年3月から平成5年4月にかけて、農協系統金融機関がBに対して有する譲渡担保の対象外とされている貸付期間1年以内の短期貸付金を譲渡担保の対象とされている同1年超の中長期債権に振り替えると同時に、それと入れ替える形で、被控訴人及びE銀行が有する中長期債権を短期債権に振り替える措置を講じ、平成4年3月末に農協系統金融機関が有していた707億8100万円の短期債権は、平成5年4月末までにすべて中長期債権に振り替えられた。”
“しかしながら、その後も不動産市況が一向に回復しなかったことなどから、住専各社の経営環境はより一層悪化し、従前の再建計画のような母体行のみの金利減免によっては、もはや経営の再建ができなくなることが指摘され、大蔵省は、平成4年12月7日、Bを含む住専7社の代表者に対し、新たな再建計画を立案するように指導するとともに、各金融機関の金利を母体行は0パーセント、農協系統金融機関以外の非母体行は2.5パーセント、農協系統金融機関は4.5パーセントに減免するなどの内容を含んだ再建計画の骨格を示したところ、農協系統金融機関は、監督官庁である農林水産省とともにこれに厳しく反発し、調整が続けられた結果、最終的には母体行が責任を持って再建計画に対応することが明確になり、債権の元本が回収できることを条件に、金融システムの安定という観点から再建計画に協力し、金利減免に応ずる意向を示し、一方、大蔵省銀行局長と農林水産省経済局長は、平成5年2月3日、住専7社の再建は母体行が責任をもって対応し、大蔵省は農協系統金融機関にこれ以上の負担をかけないよう責任をもって指導することなどを内容とする覚書き(甲第6号証の11)を交わした。”

“そこで、Bは、平成5年5月25日までに第1次再建計画に代わる新たな再建計画(本件新事業計画)の概要を固めたが、それは、計画期間を同年4月から平成15年3月までの10年間とし、総資産、借入金規模の圧縮を行い、延滞債権の回収に向けた努力をし、経営の合理化を図ること、余裕資金による返済順序は、①住宅ローン債権信託、②母体行からの新規融資金(母体ニューマネー)、③借入有価証券、④農協系統金融機関の順とすること、被控訴人及びE銀行は、計画期間中、既融資金の金利を免除し、新規融資を実施すること、F証券、G證券及びH證券も、計画期間中、新規融資を実施すること、非母体行は、現状の融資金残高を維持し、融資金利は、農協系統金融機関が年4.5パーセント、一般行が年2.5パーセントとすること、Bの自己資本強化のため、本件母体5社は、第三者割当増資を引き受けることなどを基本的な内容とするものであり、これを受けて、Bの本件母体5社は、平成5年5月25日、①被控訴人及びE銀行は、同年4月1日に遡ってBに対する貸出金の金利を10年間免除し、本件新事業計画の遂行上必要な資金として600億円を上限として新規貸出を行い(母体ニューマネー)、第三者割当増資を各30億円ずつ引き受けること、②F証券、G證券及びH證券は、200億円を限度として新規貸出を行い、第三者割当増資を各30億円ずつ引き受けることなどを確認し、その後、Bは、同年12月27日までに非母体行から本件新事業計画への合意を取り付けた。”
“本件新事業計画は、Bが新規に獲得できる正常債権の金利水準が本件新事業計画策定当時の水準である6.50パーセントであること、不動産市況が、本件新事業計画策定当時を底値とし、当初3年間は回復せず、4年目から緩やかな回復基調にある(4年目以降年3パーセントの上昇を想定)ことを前提としていたが、その後も、不動産市況は依然として大幅な下落を続け、金利水準も低利で推移し、本件新事業計画の前提は客観的な情勢に合致しなかった。Bの貸借対照表上の欠損金は、平成5年3月末において33億0800万円であったものが、平成6年3月末には104億6000万円、平成7年3月末には187億0100万円へと増加し、平成5年度に本件新事業計画に従って増資をしたにもかかわらず、資本合計は平成6年3月末に139億3600万円、平成7年3月末に56億9500万円であり、平成6年3月末、平成7年3月末の各期損失がそれぞれ71億5100万円、82億4000万円であったことから、資本欠損に陥るおそれがあった。また、平成6年度末にu信用組合とv信用組合が破綻し、平成7年夏にはU信用金庫や株式会社w銀行の破綻が表面化し、内外から日本の金融システムに対する不安が高まった。”
“大蔵省銀行局は、平成7年8月、住専各社に対して2度目の立入調査を行ったところ、同年6月30日を調査基準時とするBの資産残高は2兆5151億円で、不良債権額(大蔵省の金融検査における資産査定の分類基準上、第Ⅱ分類債権以上のもの)は1兆8532億円に達し、そのうち第Ⅱ分類(債権確保上の諸条件が満足に充たされないため、あるいは信用上疑義が存するなどの理由により、その回収について通常の度合を超える危険を含むと認められる債権及び何らかの理由により銀行資産として好ましくないと判定されるその他の資産に分類される債権)は2991億円、第Ⅲ分類(最終の回収又は価値について重大な懸念が存し、したがって、損失の発生が見込まれるが、その損失額の確定し得ない資産に分類される債権)は1953億円、第Ⅳ分類(回収不可能又は無価値と判定される資産に分類される債権)は1兆3588億円であることが明らかとなった。このような状況を受けて、本件母体5社は、平成7年9月22日、Bを整理する方針を確認した。”
“被控訴人らの母体行は、大蔵省銀行局中小金融課金融会社室(以下「金融会社室」という。)から、Bの整理方法について農協系統金融機関と協議するように要請され、平成7年9月27日から同年11月22日までに5回にわたって協議が行われたが、農協系統金融機関側は、Bを整理することになった場合でも農協系統金融機関への優先弁済の方針は維持されるべきである旨の発言をし、農協系統金融機関の元本損失部分は、母体行側が責任を持つ完全母体行責任による処理を行うように強く求めたが、被控訴人らの母体行は、金融会社室から損失の平等負担を求めるようなことは避けるように要請されていたこともあって、株式会社としてできる限界があり、貸出金の全額を棒引きすることまでが限度であって、それ以上の負担をすることは商法上許される範囲を超えると答えて農協系統金融機関の同要求を拒否し、農協系統金融機関との協議は物別れに終わった。”
“大蔵省銀行局長は、平成7年11月29日、住専7社に対し、大蔵省として、住専処理について関係当事者の仲介を行い、公的資金の導入を含む抜本的な住専処理計画を策定する意思があることを示唆し、政府予算案の内示がある同年12月20日までに住専処理計画の概要をとりまとめるように求めた。一方、当時の政府与党の政策調整会議は、同月1日、大蔵省及び農林水産省に対し、できる限り住専7社を一括して処理するものであること、残余の資産等については受け皿となる組織(後の住宅金融債権管理機構。以下「住専処理機構」という。)を設立して対処すること、日銀融資、政府保証等を活用すること、損失の負担割合を決める場合は、住専設立から今日の破綻に至った経緯を充分踏まえることを骨格とする処理計画の策定を要請した。大蔵省は、住専7社の母体行に対する意見聴取を行ったが、被控訴人は、貸出残高までの負担が商法上許される限度であることを改めて伝え、他の住専7社の母体行も同様の認識を示した。”
“大蔵省は、平成7年12月17日、回収不能な住専7社の不良債権(第Ⅳ分類資産)6兆3000億円を1次ロスとし、このうち3兆5000億円は、住専7社の母体行がその債権全額を放棄し、1兆7000億円は一般行が、1兆1000億円は農協系統金融機関がそれぞれその債権を一部放棄して処理する案を提示し、被控訴人を含む住専7社の母体行は、翌18日、同1次ロスの処理案を受け入れるが、これ以上の負担には応じられない旨の意向を示し、その後、政府と農協系統金融機関との交渉が続けられた結果、与党3党と政府の首脳は、同月19日、住専の具体的な処理方策について、①住専処理機構は、住専の資産等を引き継ぎ、回収不能な不良債権に係る損失見込額(7社合計で約6兆2700億円)、欠損見込額(約1400億円)を処理すること、②関係金融機関に対し、母体行は債権の全額(3兆5000億円)を放棄し、また、住専処理機構への出資及び低利融資を行うこと、一般行は債権のうち1兆7000億円を放棄し、また、住専処理機構への低利融資を行うこと、農協系統金融機関は貸付債権の全額返済を前提として、住専処理機構に対する約5300億円の贈与及び住専処理機構への低利融資の協力を行うことを要請すること、③政府は、預金保険機構に住専勘定を設け、平成8年度当初予算において、同勘定に対して6800億円を支出し、同勘定は、住専処理機構に対し、同年度以降回収可能性の精査、整理状況を踏まえて支出を行うこと、④預金保険機構住専勘定は、住専処理機構において住専から引き継いだ資産に損失が生じた場合、その一部を補てんし、政府は同勘定に損失が生じた場合に適切な財政措置を講ずること、⑤政府は、平成8年度当初予算において、預金保険機構に対し、同機構の運営を強化するために50億円の出資を行うこと、⑥日本銀行に対し、預金保険機構への出資及び同機構住専勘定への資金供与を行うよう要請すること、⑦以上について、所要の法的措置を講ずるとともに、関係機関による調整が行われ、適切な整理計画が策定された住専から速やかに住専処理機構に対し資産等の譲渡を行い、その処理を着実に進めていくこととすることなどを確認した。”
“そこで、内閣は、平成7年12月19日、住専をめぐる問題は、金融機関の不良債権問題における象徴的かつ喫緊の課題であり、我が国金融システムの安定性とそれに対する内外からの信頼を確保し、預金者保護に資するとともに我が国経済を本格的な回復軌道に乗せるためにも、その早期解決が是非とも必要であるとし、そのため、住専問題に係る透明性の確保、種々の責任の明確化等を図りつつ、具体的な方策を講ずるものとするとの閣議決定(本件閣議決定)を行い、翌日に予定されていた平成8年度予算の大蔵原案の内示前にこの問題に一応の決着をつけ、一方、被控訴人は、平成7年12月29日までに本件新事業計画に基づいて新規に融資した貸金(母体ニューマネー)をBから回収した。”
“本件閣議決定の内容は、次のとおりである。
(1)処理の損失住専処理機構を設立し、住専の資産等を引き継ぐこととし、回収不能な不良債権に係る損失見込額(7社計で約6兆2700億円)及び欠損見込額(約1400億円)について処理する。
関係金融機関に対する要請関係金融機関に対し、次により対応することを要請する。
ア母体行は、住専に対する債権約3兆5000億円の全額を放棄する。また、住専処理機構への出資及び低利融資を行う
イ一般行は、住専に対する債権のうち約1兆7000億円を放棄する。また、住専処理機構への低利融資を行う。
ウ農協系統金融機関は、貸付債権の全額返済を前提として、住専処理機構に対する約5300億円の贈与及び住専処理機構への低利融資の協力を行う。
公的関与
ア政府は、預金保険機構に住専勘定を設け、平成8年度当初予算において、同勘定に対して6800億円を支出する。同勘定は、住専処理機構に対し、同年度以降、同機構の保有する債権の回収可能性の精査及び整理状況を踏まえて支出を行う。
イ預金保険機構住専勘定は、住専処理機構において住専から引き継いだ資産に係る損失が生じた場合、その一部を補てんする。また、政府は、同勘定に損失が生じた場合に、適切な財政措置を講ずる。
ウ政府は、平成8年度当初予算において、預金保険機構に対し、同機構の運営を強化するために、50億円の追加出資を行う。
エ日本銀行に対し、預金保険機構への出資及び同機構住専勘定への資金供与を行うよう要請する。
(4)債権回収の促進住専処理機構は、預金保険機構の指揮の下、法律家、不動産取引の専門家等の参加、協力を得て、法的手段等を活用しつつ、債権の回収を強力に行う。両機構は、法務・検察当局及び警察当局と緊密な連携を図る。
(5)以上について、所要の法的措置を講ずるとともに、関係機関による調整が行われ、適切な処理計画が策定された住専から、速やかに住専処理機構に対し資産等の譲渡を行い、その処理を着実に進めていくこととする。”
“その後、住専7社の第Ⅲ分類資産に係る損失(2次ロス)1兆2400億円の負担について、大蔵省側と住専各社の母体行側との間で交渉が進められ、大蔵省は、平成8年1月24日、住専処理に関する法律により、預金保険機構の中に、1兆円を限度とする金融安定化拠出基金を設立し、住専7社に融資している関係金融機関に基金の拠出を求め、同基金の運用益等で賄うことなどを内容とする案を関係金融機関に示したところ、関係金融機関は、翌25日に、これに同意する意向を示したため、内閣は、同月30日、上記2次ロス処理方策を内容とする閣議了解(本件閣議了解)を行い、同年2月9日に、本件閣議決定及び本件閣議了解の内容を実現すべく、住専処理法(特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法)案が国会に提出された。
これに対し、当時最大野党であった新進党は、住専問題に関する処理に税金を投入することに反対する根強い世論があることを踏まえ、本件閣議決定及び本件閣議了解がされた後である平成8年2月27日、平成8年度予算案に計上している6850億円の住専関係予算を削除すること、市場原理に基づく自己責任の大原則により国民に開かれた状況の中で住専問題の解決を行うことなどを内容とする「住専問題に関する基本方針」を発表し、さらに、同年3月4日、住専関係予算6850億円が計上されている平成8年度予算案の審議に応じないという方針を決定して、同党議員が予算委員会の委員室に座り込みを始めたため、国会審議が中断され、同月25日に衆議院議長の下で与野党5党党首会談が開催され、国会の正常化が合意されるまで国会審議が中断した。”

“Bは、本件事業年度上半期において、本件新事業計画の3年目を迎え、本件新事業計画に従って、引き続き住宅ローン営業基盤の維持・不良債権の回収・経費の圧縮等の努力を行っていたが、本件新事業計画策定時の予想を超える不動産不況の長期化、金利低下による利息収入の減少等により厳しい経営が続いた。この結果、平成7年9月末の貸付金残高は、前期末比0.7パーセント減の2兆2387億円となり、総資産は前期末比21.1パーセント減の1兆9977億円となった。
また、損益面については、334億円の貸倒引当金の組入れを行ったことから営業費用が796億円となり、これにより経常損失は323億円となった。さらに、特別損失として4521億円の貸倒引当金の積み増しを行った結果、中間純損失は4844億円の計上を余儀なくされ、Bの平成7年9月末現在の貸借対照表上、4788億0300万円の資本欠損が生ずることになった。”
“被控訴人は、大手銀行21行の中で、住専7社に対する減免予定債権額が6607億円と突出していたにもかかわらず、一般貸倒引当金の残高が極めて不十分であり、住専7社に対する債権についての債権償却特別勘定の設定もしていなかったため、このままでは、平成8年3月期決算において、引当金不足が問題視され、商法285条の4第2項違反の責任を追及される可能性が高まったことから、被控訴人としては、Bに対する本件債権については、平成8年3月期において、貸倒処理による直接償却をするほかないとの判断に至り、同期に合わせて含み益を実現する目的での株式売却を平成7年11月以降積極的に行い、その利益の額は、同月が818億円、同年12月が2072億円、平成8年1月が781億円、同年2月が496億円、同年3月が436億円と合計4603億円に達した。”
“一方、被控訴人は、同社の顧問税理士である庚税理士に対し、本件債権は、全額回収不能といわざるを得ず、全額を貸倒債権として直接償却したいので、事前に国税当局と償却方法について相談してほしい旨を依頼され、庚税理士は、平成8年1月10日、国税庁課税部審理室の乙専門官を訪ねたところ、乙専門官は、基本通達9-6-2の全額回収不能に基づく貸倒償却の方法で税務処理を行うことは到底できないこと、住専7社の母体行が住専に対して債権放棄をすれば、基本通達9-4-1によって、当該債権放棄について寄附金認定を行わず、当該放棄によって生じる損失額について、税務上の損金算入を認めることができることなどを説明をし、庚税理士は、その旨を被控訴人に報告した。
しかしながら、公的資金を導入することについて反対が強く、本件閣議決定及び閣議了解に則った住専処理法案が成立する見通しもない段階において、本件債権を放棄し、その後、結局、これが成立しなかった場合には、株主代表訴訟による責任追及がされるおそれがあったところから、被控訴人内部においては、債権放棄によることは避け、全額回収不能であるとして税務処理したいとして、再度、国税庁と協議を行うべきとの結論に達したため、庚税理士は、同月12日と同月18日の2回にわたり、被控訴人の職員数人と共に再度、乙専門官を訪ねたが、乙専門官の意見は変わらず、庚税理士は、同月18日の際、本件債権の担保権を放棄した上で平成8年3月期に当該債権が全額回収不能になったとして貸倒処理を行う方法の是非についても確認したが、乙専門官は、担保権を放棄しただけでは、本件債権について全額回収不能であるとまではいえないと述べ、基本通達9-4-1による債権放棄以外には損金算入する方法は考えられない旨を述べた。
一方、〈y〉国税庁次長は、同月27日、衆議院予算委員会において、本件閣議決定によって策定された住専処理スキームに基づいて関係者の合意の下に関係金融機関が債権放棄を行えば、税務上も損金の額に算入される性格のものと考えていること、合意に基づいて債権放棄を行うというのであれば、すべての母体行がそろって放棄を行うのが自然の形であるが、個別にどのように判断するかは、申告書の提出を待たざるを得ない旨を答弁した。”
“本件母体5社は、本件閣議決定及び本件閣議了解で示された住専処理計画に沿って、Bの不良資産のうちの損失見込額1兆3588億円及び欠損見込額187億円の合計1兆3775億円について、本件母体2行がBに対する債権を全額放棄することによつて5370億円を負担し、一般行はBに対して有している債権の合計9264億円のうち4999億円を債権放棄することによって同額を負担し、農協系統金融機関は、3407億円を贈与することによって同額を負担することを基本とするBの具体的処理計画案を策定するとともに、平成8年3月期末時点での関係金融機関の債権額及び債権放棄予定額を計算し、被控訴人において、平成8年3月21日、上記内容を記載した「B株式会社の損失処理に関するご連絡」と題する書面(本件損失に関する連絡)をBのすべての一般行に送付した。
上記処理計画案では、Bの正常資産及び不良資産のうち回収が見込まれるものの合計額は、1兆2103億円であり、実質的に一般行及び農協系統金融機関に返済される合計額(一般行及び農協系統金融機関がBに対して有する債権から、一般行の債権放棄額及び農協系統金融機関の贈与額を除いたもの)は、1兆0791億円とされていた。
また、一般行あての上記書面には、同書面内容に意見等がある場合には、同月25日までに連絡するように求める記載がされていたが、一般行から特段の意見は表明されなかった。”
“本件母体5社は、平成8年3月29日、Bの母体行である被控訴人及びE銀行並びに一般行の債権放棄額を確認するとともに、被控訴人及びE銀行は、Bの営業譲渡の日までに同債権放棄額に対応する貸出債権を全額放棄するものとすることを確認する旨の書面を作成した。
また、被控訴人は、同日、取締役会を開催し、B向けの母体行債権の全額を債権放棄することを決議したが、同取締役会では、本件債権を本件事業年度において直接償却する必要性がある理由として、仮に本件事業年度において多額の債権償却特別勘定の設定をすると、前年度にこれをしていなかったことの責任を問われるおそれがある旨が説明されたほか、本件債権放棄に解除条件を付すことにすれば、債権放棄によつて被控訴人に損害を与えたとしてする代表訴訟を防止する効果がある旨が説明された。”
“そこで、被控訴人は、同日、Bとの間で、本件約定書を取り交わし、本件債権放棄をしたが、本件約定書は、同約定書別表記載の貸付債権(元本合計金3760億5500万円の本件債権)及びこれに付帯する利息債権を含む一切の権利を対象債権として、被控訴人が同対象債権をBの「営業譲渡の実行及び解散の登記」が平成8年12月末日までに行われないことを解除条件として本日放棄し、Bはこれを承諾すること(第2条)、被控訴人は、同債権放棄に伴い、対象債権に付帯する一切の担保権及び保証債権が消滅することを確認すること(第3条第1項)、第3条第1項の他、被控訴人がBに対して根抵当権、根質権、包括的な譲渡担保権、根保証債権等、対象債権を担保する包括的な物的・人的担保権を有する場合、被控訴人は、このすべてを本日放棄し、Bはこれを承諾すること(第3条第2項)、被控訴人とBは、第2条の解除条件が成就した場合、その解除の効果は平成8年12月末日の経過をもって発生することを確認すること(第4条)等を内容とするものであった。
また、被控訴人とBは、平成8年3月29日、本件約定書第2条について、①営業譲渡の実行とは、営業譲渡契約において定められる営業譲渡日に行われる資産譲渡等を意味する、②平成8年12月末日までにBの営業譲渡の実行又は解散の登記のいずれか一方しか行われない場合には、解除条件は成就したものとするとの覚書を締結した。また、Bは、本件債権放棄を受け、平成8年3月期の事業年度において、3760億5500万円の債務免除益を計上した。”
“住専処理に係る公的資金6850億円を盛り込んだ平成8年度予算案は、与野党間で直前まで交渉が行われ、与党と新進党との間において、平成8年4月10日、同公的資金については、制度を整備した上で措置する旨の合意が交わされたことを踏まえて、翌11日に衆議院本会議で可決されたものの、住専処理法自体の審議入りの時期は不明で、決着は先送りされた旨の報道もされた。
その後、同予算案は、同年5月10日に参議院本会議で可決されたが、住専処理法自体は、国会会期末前日の同年6月18日にようやく可決されて同月21日施行された。これを受けて、Bは、同月26日、株主総会における特別決議により、解散及び営業譲渡に関する定款の一部変更の決議をし、同年8月31日に、住宅金融債権管理機構との間で営業譲渡契約を締結した上で、同年9月1日解散し、そのころその旨の登記がされた。また、被控訴人は、同年6月26日ころ、本件約定書の5条によりBに返還することとされていた貸付契約証書、約束手形等の関係書類を返還した。”
“一方、預金保険機構は、平成8年8月29日、住専7社の母体行、一般行及び農協系統金融機関に対して、本件閣議決定、本件閣議了解及び住専処理法を前提とした住専処理計画に係る基本協定(住専処理に係る基本協定)を提示し、関係金融機関は、そのころ、預金保険機構に対し、同基本協定書に同意する旨の書面を提出した。
本件債権の本件事業年度における損金算入の適否1平成8年3月末における本件債権の回収不能性(貸倒れ)前記一のとおり、法人税法は、金銭債権については評価減を認めないことを原則としているため、不良債権を貸倒れとして直接償却することができるのは、その全額が回収不能となった場合に限られることになる(全額が回収不能とはいえない場合には、間接償却の方法や債権放棄等による直接償却の方法が別途用意されていることは、前記一のとおりである。)。”
“ここで債権の全額が回収不能であるとは、債務者の実際の資産状況、支払能力等の信用状態から当該債権の資産性が全部失われたことをいい、この場合に限って、所得の計算上、金銭債権の滅失損として、法人税法22条3項の規定により損金の額に算入することができるものである。
そして、貸倒れによる損金は、その損金算入時期を人為的に操作して、課税負担を免れるといった利益操作の具に用いられる余地を防ぐためにも、全額回収不能の事実が債務者の資産状況や支払能力等から客観的に認知し得た時点の事業年度において損金の額に算入すべきであり、それが一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に適合する所以である。”

“これを本件についてみると、前記二で認定した事実によれば、Bの正常資産及び不良資産のうち回収が見込まれるものの合計額は、その当時、少なくとも1兆円は残されていたことが推認され、この金額は、Bの借入金総額の約40パーセントにも上るのであるから、このようなBの客観的な財務状況に鑑みると、平成8年3月末時点において、本件債権が全額回収不能であったといえないことは明らかである。”
“これに対し、被控訴人は、Bの設立時から被控訴人が平成8年3月29日に本件債権を放棄するまでの間に、被控訴人を含む母体行のBに対する債権は、非母体行の債権に対し、その弁済順序において劣後することが段階的に顕在化し、本件債権は、平成8年3月末までの間に、関係金融機関の合意又は社会通念により、弁済順序において最劣後のものとなっていた旨を主張するが、被控訴人は、Bを破綻させ、その結果、我が国の金融システムに対する不安を招いたことにつき、母体行として、社会的、道義的責任を負っていたことは否定できないし、また、Bの健全経営やいわゆるバブル経済崩壊後のBの再建計画に当たって、母体行として責任がある旨を表明したり、不利な返済条件等を受け入れるなどしたことは窺われるものの、本件新事業計画の実施までは、Bを再建することを前提としていたものであって、これをもってBの破綻後の整理条件についてまで被控訴人ら母体行の債権を非母体行の債権に劣後させる旨の合意がされたものとはいえないし、社会的、道義的にみて本件債権を行使し難い状況が生じつつあったとはいえても、法的にみて本件債権が劣後化していたとまでいうことはできない。”
“また、確かに、Bの母体行、一般行及び農協系統金融機関は、本件閣議決定及び閣議了解に基づくBの破綻処理計画に同意したことが認められるものの、その同意は、あくまでも、住専処理法及び住専処理を前提とする予算が成立し、公的資金導入の決定がされることが大前提であったものであって、Bの関係金融機関は、その後、翌事業年度に入ってから、同予算及び住専処理法が成立し、Bがその営業を譲渡したのを受けて、預金保険機構が示した住専処理に係る基本協定に改めて同意していることに照らしても、未だ平成8年3月末時点においては、本件債権が関係金融機関の合意により又は社会通念上弁済順序において法的に最劣後のものとなっていたということはできない。”
“また、被控訴人は、解除条件付きで本件債権放棄をした際、全ての担保権を無条件で放棄したものである旨を主張するが、本件約定書(甲第4号証)の記載によれば、被控訴人は、Bの営業譲渡の実行及び解散の登記が平成8年12月末日までに行われないことを解除条件とする本件債権放棄をするのに伴い、本件債権に附帯する一切の担保権及び保証債権が消滅することを確認したものにすぎない上、被控訴人は、公的資金の導入を前提とする住専処理法が成立する前に本件債権を無条件で放棄したのでは、同法及び住専処理を前提とする予算が成立しなかった場合に、被控訴人の取締役が株主代表訴訟によってその責任を追及されることをおそれ、これを回避するために本件債権放棄に解除条件を付したものと認められるのであるから、被控訴人が本件債権に係る担保権のみを無条件で放棄したものとは到底考えられないのであって、解除条件が成就して本件債権放棄の効力が消滅した場合には、担保権についてもこれを消滅させない趣旨であったものと解されるのであり、そして、当時、住専処理法や住専処理を前提とする予算が成立しないで、解除条件が成就する可能性も相当程度にあったのであるから、上記のように条件付きで担保権を消滅させたとしても、これによって本件債権が同年3月末時点において全額が回収不能になっていたものということはできない。”
“さらに、被控訴人は、本件債権を行使することは、社会全体を敵に回すに等しく、社会的存在としての銀行としてはこの上なく有害な行為であって、本件債権は、本件事業年度において、社会通念上回収不能の状態にあったものである旨を主張するが、そもそも、債権の全額が回収不能であるとは、前記のとおり、債務者の実際の資産状況、支払能力等の信用状態から当該債権の資産性が全部失われたことをいうのであって、責任財産がありながら、債権行使に対する社会的批判等の他事を考慮して債権者が当該債権を行使しないこととしたような場合などは、これに当たるものではない。
翻って考えるに、以上のようにBの母体行としての責任を問われ、また、Bの再建やその後の破綻を前提とした住専処理計画の中において、被控訴人が不利な返済条件や債権放棄等を甘受する意向を表明し、Bに対する担保権の放棄を余儀なくされるに至ったこれら一連の経過は、未だ資産性が全部滅失していない本件債権の行使を差し控えようとするものにほかならないのであって、結局は、被控訴人が平成8年3月29日に明示的に行った解除条件付きの本件債権放棄に集約されるものであり、これを経済的利益の無償供与として損金の額に算入することができるか否かを別途検討する余地はあるとしても、それをもって本件債権が全額回収不能となったということのできないことは明らかである。”
“必ずしも全額回収不能とはいえない金銭債権が放棄された場合でも、債権の回収不能部分が特定されて当該部分の債権が放棄された場合や、損失を負担しなければより大きな損失を被ることが明らかであるためやむを得ず債権放棄を行う場合には、経済取引として十分に肯首し得る合理的な理由があるということができるから、そのような場合には、経済的利益の無償供与は、寄附金には当たらないものと解することができ、基本通達9-6-1(四)、9-4-1も、その趣旨を定めたものということができる。”
“そして、本件においては、前記二のとおり、平成8年3月までにBの債務超過の状態が相当期間継続し、本件債権に回収不能部分があったことが認められ、また、被控訴人は、母体行として、Bと密接な事業関連性を有していたところ、Bの経営が破綻して公的資金を導入した上での整理が予定されていたもので、本件債権を放棄しなければ、さらに大きな損失を被ることになることが明らかであったともいえるから、本件債権放棄が寄附金には当たらないものと解する余地はある。
ところが、本件債権放棄は、Bの営業譲渡の実行及び解散の登記が平成8年12月末日までに行われないことを解除条件としたものであり、その解除条件の不成就が翌事業年度において確定したものであるところ、被控訴人は、本件債権放棄の効力は、このように解除条件が付されていても、債権放棄のされた本件事業年度において効力が生じているのであるから、同年度における損金の額に算入されるべきである旨を主張するものである。”
“しかしながら、前記二で認定した事実によれば、被控訴人は、平成8年3月期決算において引当金不足が問題視されることを危惧して、本件事業年度において本件債権を直接償却するほかないと判断し、これに合わせて保有する株式の含み益を得るため、平成7年11月以降株式売却を積極的に行い、その利益の額は、平成8年3月までに合計4603億円に達し、本件債権の償却を次年度に繰り越すことはもはや事実上不可能な状況に自ら立ち入った一方で、本件事業年度に本件債権を直接償却するために本件債権を平成8年3月末までに放棄した場合には、公的資金の導入を前提とする住専処理法が成立に至らなかった場合に被控訴人の取締役が株主代表訴訟によってその責任を追及されるおそれを払拭できず、解除条件付きの本件債権放棄は、このようなジレンマの中でいわば苦肉の策として考えられたものということができ、被控訴人としては、これによって、本件事業年度に本件債権を直接償却することができ、4603億円もの株式売却益に対する課税負担を回避することができる一方で、仮に住専処理計画が計画通り成立しなかった場合でも、被控訴人の取締役が株主代表訴訟による責任を追及されるおそれも回避できるということを意図して行われたものということができる。”
“そして、このような解除条件の付された債権放棄に基づく損失の損金算入時期を、当該意思表示のされたときの属する事業年度としたときには、本来、無条件の債権放棄ができず、当該事業年度において損金として計上することができない事情があるにもかかわらず、法人側の都合で損金計上時期を人為的に操作することを許容することになるのであって、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に適合するものとはいえない。”

“そして、そもそも、課税は、私法上の法律行為の法的効果自体にではなく、これによってもたらされる経済的効果に着目して行われるものであるから、ある損金をどの事業年度に計上すべきかは、具体的には、収益についてと同様、その実現があった時、すなわち、その損金が確定したときの属する年度に計上すべきものと解すべきところ、解除条件付き債権放棄の私法上の効力は、当該意思表示の時点で生ずるものの、本件におけるような流動的な事実関係に下においては、債権放棄の効力が消滅する可能性も高く、未だ確定したとはいえないのであるから、本件解除条件付きでされた債権放棄に基づいて生ずる損金については、当該条件の不成就が確定したときの属する年度、すなわち、本件事業年度ではなく、住専処理法と住専処理を前提とする予算が成立し、Bの営業が譲渡され、解散の登記がされた翌事業年度の損金として計上すべきものというべきである。”
“被控訴人は、被控訴人と同様に平成8年3月期において住専向け債権を放棄した株式会社〈D〉銀行については、基本通達9-4-1が適用することを否定されなかったものであり、また、株式会社〈b〉等の事案においては、解除条件付きで債権放棄をした事業年度において損金算入を認めているのであるから、本件債権放棄について損金算入を認めないことは、合理的理由なく特定の納税者についてのみ不利な取扱いをするものであって、課税の公平性の原則からいって、許されない旨を主張するが、仮に類似事案において損金算入が認められた例があるとしても、控訴人が被控訴人を殊更恣意的に不公平に扱おうとしたと認めるに足りる事情は認められないのであるから、それだけでは本件再更正処分等の違法性を基礎付けるものとはいえない。”
“債権者の協議等によって、回収不能部分を特定しこれを原則として債権者らの債権額に案分して切り捨てた場合は、経済取引として十分に肯首し得る合理的な理由があるということができ、そのような場合には、当該経済的利益の無償供与は、寄附金には当たらないものと解することができ、基本通達9-6-1(三)も、このことを定めたものということができる。”
“本件閣議決定及び閣議了解に基づく住専処理計画は、政府が斡旋し、Bの関係金融機関が協議して決定したものというべきであるが、同住専処理計画は、被控訴人ら母体行の社会的、道義的責任を重視して、その債権を全額放棄させ、農協系統金融機関については、他の一般行よりも優遇した内容となっているのであるから、その内容からして被控訴人の経済的利益の無償供与性を否定することは困難であり、そればかりか、確かに前記認定事実によれば、Bの母体行、一般行及び農協系統金融機関は、本件事業年度中に、本件閣議決定及び閣議了解に基づく住専処理計画に同意していたことが認められるものの、その同意は、あくまでも、住専処理法及び住専処理に係る予算が成立して、公的資金が導入されることを大前提とするものであったのであり、Bの関係金融機関は、その後、翌事業年度に入ってから、住専処理法等が成立し、Bがその営業を譲渡したのを受けて、預金保険機構が示した住専処理に係る基本協定に同意したのであるから、行政機関等の斡旋による当事者の協議が成立したのは、翌事業年度においてであったというべきであり、いずれにしても、本件事業年度における損金算入を認めることはできない。”
“以上のとおり、本件債権は、平成8年3月末当時、全額回収不能であったものとはいえず、また、本件債権放棄や関係者の協議決定によっても、本件事業年度において本件債権を損金に算入することは許されず、他に本件事業年度において本件債権について損金算入を認めるべき理由もないから、被控訴人が本件確定申告において本件債権の額に相当する3760億5500万円を損金に算入したことには、否認すべき理由があるというべきである。”
“国税通則法65条4項所定の「正当な理由」の存否被控訴人は、本件債権放棄は、本件閣議決定という政府の方針に沿ったもので、大蔵省の担当者も、本件債権の放棄を率先して行うように指導しており、また、国税庁の担当者から本件債権を放棄すれば、その全額を損金の額に算入することができ、債権放棄に解除条件が付いていても税務上有効である旨の指導を受け、被控訴人はこれに従ったものであるから、被控訴人が本件債権の全額を損金の額に算入して本件確定申告を行ったことについて国税通則法65条4項にいう「正当な理由」が認められ、控訴人による本件の過少申告加算税の賦課決定処分は取り消されるべきである旨を主張する。”
“しかしながら、前記二で認定した事実によれば、本件事業年度において本件債権を貸倒れとして損金の額に算入することができるか否かについて、被控訴人は、国税庁の乙専門官に相談をし、同専門官がこれに対応したもので、同専門官は、全額回収不能であるとして債権放棄をしないで本件事業年度において損金として処理したいという被控訴人の意向に対して明確にこれを否定し、債権放棄をした上で基本通達9-4-1によって損金処理する以外には方法がないと指導していたものであり、一方、被控訴人が乙専門官との交渉を依頼した庚税理士の陳述書(甲第326号証)中には、乙専門官が、庚税理士に対し、解除条件が付されていても税務処理に差し支えないと回答した旨の陳述記載部分があるが、これを否定する乙専門官の陳述書(乙第24号証)の陳述記載部分に照らして、上記庚税理士の陳述記載部分を直ちに採用することはできず、他にはこれを認めるに足りる証拠はない。”
“その他、本件の一切の事情を考慮しても、被控訴人が本件債権の全額を損金の額に算入して本件確定申告を行ったことについて国税通則法65条4項にいう「正当な理由」が認められるものとはいえない。五本件更正処分及び本件再更正処分等の適法性前記三のとおり、本件債権の額に相当する3760億5500万円は、本件事業年度における被控訴人の所得金額に加算されるべきであるところ、請求原因1(二)の事実、並びに抗弁2のうち別紙1の②、④、⑦及び⑩の各項目及び金額については当事者間に争いがなく、別紙1の③のとおり、所得金額を加算すると、控除可能な外国税額が別紙1の⑧となることは、甲第1号証及び弁論の全趣旨によって明らかであり、そうすると、控訴人が納付すべき法人税額が別紙1の⑤、過少申告加算税が別紙1の⑪となることは計数上明らかであって、これは、本件更正処分及び第一過少申告加算税の各内容と一致する。
本件更正処分等は、いずれも適法である。
以上の次第で、被控訴人の本訴請求は、いずれも理由がないから、これを認容した原判決を取り消して、被控訴人の請求をいずれも棄却することとし、主文のとおり判決する。”
最高裁/平成16年12月24日判決(滝井繁男裁判長)/(破棄自判・被上告人の控訴棄却)(納税者勝訴)(確定)
(※A銀行=原告を指す。)
“原審の上記判断は是認することができない。その理由は、次のとおりである。
法人の各事業年度の所得の金額の計算において、金銭債権の貸倒損失を法人税法22条3項3号にいう「当該事業年度の損失の額」として当該事業年度の損金の額に算入するためには、当該金銭債権の全額が回収不能であることを要すると解される。
そして、その全額が回収不能であることは客観的に明らかでなければならないが、そのことは、債務者の資産状況、支払能力等の債務者側の事情のみならず、債権回収に必要な労力、債権額と取立費用との比較衡量、債権回収を強行することによって生ずる他の債権者とのあつれきなどによる経営的損失等といった債権者側の事情、経済的環境等も踏まえ、社会通念に従って総合的に判断されるべきものである。”

“これを本件債権についてみると、前記事実関係によれば、次のとおりである。
ア母体5社は、平成7年9月にBを整理する方針を確認したところ、その後の農協系統金融機関との協議において、農協系統金融機関が、その元本損失部分についても母体行が責任を持つ完全母体行責任による処理を求めたのに対し、A銀行は、その貸出金全額の放棄を限度とする修正母体行責任を主張し、債権額に応じた損失の平等負担を主張することはなかった。
イその背景として、A銀行は、Bの設立に関与し、独禁法で許容される上限まで株式を保有し、役員及び職員を派遣し、多額の融資を行うなどして、その経営に深くかかわっていたという事情があった。そして、同4年に策定された第1次再建計画によってはBの経営再建ができなくなり、同5年に本件新事業計画が策定されるに至ったが、農協系統金融機関が融資残高の維持及び金利の減免を内容とする同計画に応じたのは、母体行が責任を持って再建計画に対応することが明確にされたからであった。そうすると、A銀行は、本件新事業計画を達成することができなかったことにつき、農協系統金融機関から信義則上の責任を追及されかねない立場にあったということができる。
ウ本件新事業計画は、Bの再建を前提としたものであって、その破綻後の整理を前提としたものではないものの、Bの余裕資金による返済順序の第2順位が母体ニューマネー、第4順位が農協系統金融機関の債権とされ、母体行の従前からの債権がそれらに劣後するという内容であったところ、A銀行は、Bの整理が避け難い情勢になった後においても、Bから母体ニューマネーを回収していた。
したがって、農協系統金融機関が完全母体行責任を主張することには無理からぬ面があり、A銀行も、上記のような経緯を考慮して、修正母体行責任が限度であると主張して、本件債権の放棄以上の責任を回避しようとしていたものということができる。
エ母体5社は、本件閣議決定及び本件閣議了解で示された住専処理計画に沿ってBの処理計画を策定し、同計画において、A銀行は、本件債権を全額放棄すること、すなわち、本件債権を非母体金融機関の債権に劣後する扱いとすることを公にしたということができる。”
“A銀行においてせいぜい修正母体行責任しか主張することができない情勢にあったことをも考慮すると、仮に住専処理法及び住専処理に係る公的資金を盛り込んだ予算が成立しなかった場合に、A銀行が、社会的批判や機関投資家としてA銀行の金融債を引き受ける立場にある農協系統金融機関の反発に伴う経営的損失を覚悟してまで、非母体金融機関に対し、改めて債権額に応じた損失の平等負担を主張することができたとは、社会通念上想定し難い。”
“オ前記のBの処理計画において、Bの正常資産及び不良資産のうち回収が見込まれるものの合計額は、非母体金融機関の債権合計1兆9197億円を下回る1兆2103億円とされたが、この回収見込額の評価は、本件閣議決定及び本件閣議了解で示された公的資金の導入を前提とする住専処理計画を踏まえたものであるから、破産法等に基づく処理を余儀なくされた場合には、当時の不動産市況等からすると、Bの資産からの回収見込額が上記金額を下回ることはあっても、これを超えることは考え難い。”
“以上によれば、A銀行が本件債権について非母体金融機関に対して債権額に応じた損失の平等負担を主張することは、それが前記債権譲渡担保契約に係る被担保債権に含まれているかどうかを問わず、平成8年3月末までの間に社会通念上不可能となっており、当時のBの資産等の状況からすると、本件債権の全額が回収不能であることは客観的に明らかとなっていたというべきである。そして、このことは、本件債権の放棄が解除条件付きでされたことによって左右されるものではない。”
“したがって、本件債権相当額は本件事業年度の損失の額として損金の額に算入されるべきであり、その結果、A銀行の本件事業年度の欠損金額は118億7390万0838円となるから、本件各処分は違法である。
以上と異なる原審の判断には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。論旨は、この趣旨をいうものとして理由があり、原判決は破棄を免れない。そして、上告人の請求を認容した第1審判決は正当であるから、被上告人の控訴を棄却すべきである。よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。”

東京地方裁判所 判示要旨
- 1.
- ■債権の全額が回収不能か否かについては、法人税法が法人の合理的な経済活動によってもたらされる利益に着目して法人税を課していることからすると(法人税法4条)、合理的な経済活動に関する社会通念に照らして判断するのが相当であり、法的措置を講ずれば、ある程度の回収を図れる可能性がないとはいえない場合においても、債務者の負債及び資産状況、事業の性質、債権者と債務者との関係、債権者が置かれている経済的状況等諸般の事情を総合的に考慮し、法的措置を講ずることが、有害又は無益であって経済的にみて非合理的で行うに値しない行為であると評価できる場合には、もはや当該債権は経済的に無価値となり、社会通念上当該債権の回収が不能であると評価すべきである。
東京高等裁判所 判示要旨
- 1.
- ■不良債権を貸倒れであるとして資産勘定から直接に損失勘定に振り替える直接償却をするためには、全額が回収不能である場合でなければならず、また、同貸倒れによる損金算入の時期を人為的に操作し、課税負担を免れるといった利益操作の具に用いられる余地を防ぐためにも、全額回収不能の事実が債務者の資産状況や支払能力等から客観的に認知し得た時点の事業年度において損金の額に算入すべきものとすることが、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に適合するものというべきであり、法人税基本通達9-6-2も、このことを定めたものということができる。
■その場合の損金算入時期についても、これを恣意的に早め、あるいはこれを遅らせるなどして、課税を回避するための道具として利用することは、法人税法の企図する公平な所得計算の要請に反し、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に適合するとはいえないのであって、その許されないことは当然である。
■債権の貸倒れが損金算入できるのは全額が回収不能な場合に限られ、回収不能とは債務者の実際の資産状況等から資産性が全部失われたことであり、当時の財務状況によると債権が全額回収不能であったとはいえない。
最高裁判所 判示要旨
- 1.
- ■法人の各事業年度の所得の金額の計算において、金銭債権の貸倒損失を法人税法22条3項3号(各事業年度の所得の金額の計算)にいう「当該事業年度の損失の額」として当該事業年度の損金の額に算入するためには、当該金銭債権の全額が回収不能であることを要すると解される。そして、その全額が回収不能であることは客観的に明らかでなければならないが、そのことは、債務者の資産状況、支払能力等の債務者側の事情のみならず、債権回収に必要な労力、債権額と取立費用との比較衡量、債権回収を強行することによって生ずる他の債権者とのあつれきなどによる経営的損失等といった債権者側の事情、経済的環境等も踏まえ、社会通念に従って総合的に判断されるべきものである。
■当時の状況では債権者(銀行)の債権の全額が回収不能であることは客観的に明らかである。
認定事実
■本件は、B株式会社(以下「B」という。)に対する残高3760億5500万円の貸付債権(以下「本件債権」という。)を有していた原告が、平成8年3月29日付けでBとの間で債権放棄約定書を締結して本件債権を放棄し、本件債権相当額を平成7年度の事業年度(平成7年4月1日から平成8年3月31日までの事業年度。以下「本件事業年度」という。)の損金の額に算入して青色確定申告をしたところ、被告が、本件債権相当額は本件事業年度の損金の額に算入することができないとして、平成8年8月23日に更正処分及びこれに係る過少申告加算税賦課決定処分を行い、さらに、平成10年3月31日には、再更正処分並びにこれに係る過少申告加算税賦課決定処分及び重加算税賦課決定処分を行ったことから、原告が、被告に対し、右再更正処分並びに過少申告加算税賦課決定処分及び重加算税賦課決定処分の取消しを求めるものである。
■原告は、更正処分の段階で、更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分取消の訴えを提起し、その後、再更正処分がされたことにより、同処分によって新たに更正の理由とされた点については争わないものの、そのことを前提としても同年度については納付すべき法人税はないとして、再更正処分並びに過少申告加算税賦課決定処分及び重加算税賦課決定処分の取消しに訴えを交換的に変更したものである。

■前提となる事実
原告は、長期信用銀行法4条1項に基づく大蔵大臣の免許を受けた長期信用銀行である。
■Bは、日本ハウジングローン株式会社(「JH L社」)である。いわゆる住宅金融専門会社(以下「住専」という。)として設立され、活動していたものであるが、平成8年6月26日に開催された株主総会における特別決議を経て、同年9月1日に解散した。原告は、Bの設立発起会社五社のうちの一社であり、Bに対して一定の資金援助等を行ってきたBのいわゆる母体行であった。
なお、原告以外のBの設立発起会社は、株式会社C銀行(平成8年3月当時。現在の商号は株式会社D銀行であり、B設立当時の商号は株式会社E銀行であった。以下「E銀行」といい、原告と併せて「本件母体二行」という。)、F証券株式会社(以下「F証券」という。)、G証券株式会社(以下「G証券」という。)、H証券株式會社(以下「H証券」といい、F証券、G証券と併せて「本件証券母体三社」という。)であった(以下、右の五社を併せて、「本件母体五社」という。)。
■原告は、Bに対して有していた3760億5500万円の本件債権について、平成8年3月29日付けで、Bとの間で、債権放棄約定書(以下「本件約定書」という。)により、本件債権を債権放棄(以下「本件債権放棄」という。)する旨の契約を締結した。
■原告は、平成8年7月1日、本件事業年度の法人税について、本件債権放棄をしたことを理由として、本件債権相当額を損金の額に算入した上で、欠損金額を132億7988万7629円とする青色確定申告(以下「本件確定申告」という。)をした。
■これに対し、被告は、同年8月23日、所得金額を3627億7511万2371円及び納付すべき税額を1285億1210万6600円とする更正処分(以下「本件更正処分」という。)並びにこれに係る過少申告加算税を191億9263万3500円とする過少申告加算税賦課決定処分(以下「本件第一過少申告加算税賦課決定処分」といい、本件更正処分と合わせて「本件更正処分等」という。)を行い、同日、その旨を原告に対して、「法人税額等の更正通知書及び加算税の賦課決定通知書」(以下「本件通知書」という。)により通知した。
■原告は、本件更正処分等を不服として、平成8年8月30日、国税不服審判所長に対し審査請求をしたが、平成9年10月27日、右審査請求は棄却された。
■そこで、原告は、平成9年10月30日、本件更正処分等の取消しを求める訴えを提起した(以下「本件訴え」という。)。
■その後、被告は、平成10年3月31日、原告の本件事業年度の法人税について、所得金額を3641億8109万9162円及び納付すべき税額を1306億9127万2600円とする再更正処分(以下「本件再更正処分」という。)並びにこれに係る過少申告加算税を3億1919万7000円とする過少申告加算税賦課決定処分(以下「本件第二過少申告加算税賦課決定処分」という。)及び重加算税を311万8500円とする重加算税賦課決定処分(以下「本件重加算税賦課決定処分」といい、本件再更正処分、本件第一過少申告加算税賦課決定処分及び本件第二過少申告加算税賦課決定処分と併せて「本件再更正処分等」という。)を行い、同年4月1日、その旨を「法人税額等の更正通知書及び加算税の賦課決定通知書」(以下「本件再更正通知書」という。)によって原告に通知した。
■原告は、本件再更正処分等が行われたことを受けて、本件訴えを本件再更正処分等の取消しを求める旨に交換的に変更した。
■平成7年12月19日付けで、損失の処理、関係金融機関に対する要請、公的関与及び債権回収の促進について所要の法的措置を講ずるなどにより、住専の処理を着実に進めることを内容とする「住専問題の具体的な処理策について」と題する閣議決定(以下「本件閣議決定」という。)が行われた。
■平成8年1月22日、住専問題の処理のための資金支出等が織り込まれた平成8年度予算案につき、衆参両院本会議で趣旨説明が行われ、衆議院予算委員会に付託された。
■平成8年1月30日付けで、本件閣議決定にのっとり、さらにその処理方策を具体化する旨の「住専処理方策の具体化について」と題する閣議了解(以下「本件閣議了解」という。)が行われた。
■平成8年2月15日、原告の〈A〉頭取は、衆議院予算委員会において、住専問題参考人として、政府処理案の趣旨にのっとり、最善の方策を見出すべく努力する所存であり、閣議決定における関係金融機関に対する要請を受諾する旨の意見を述べた。
■平成8年3月4日、当時最大野党であった新進党が平成8年度予算案の審議に応じないとの方針を決定し、同党議員が予算委員会の会場の第一委員室に座り込みを開始した。
■Bの母体五社の幹事である原告は、Bに対して融資を行っている金融機関に対し、平成8年3月21日付け「B株式会社の損失処理に関するご連絡」と題する書面(以下「本件損失に関する連絡」という。)を送付した。その書面の内容は、①Bが新事業計画に沿って事業を継続していくことが、極めて困難な状況となっていること、②政府は、本件閣議決定及び本件閣議了解を行ったこと、③関係金融機関は政府案に沿って処理を進めるとの方向であること、④Bの母体五社も、政府案に沿った具体的処理策を検討中であること、⑤平成8年3月期末を迎えるに際し、現時点での関係金融機関の債権額及び政府処理案に基づく債権放棄予定額を計算したので、別添計算書のとおり案内するものであること、⑥最終債権放棄額については最終資産譲渡等により確定するので変動することがあること、⑦平成8年3月末決算において損失処理を検討する場合には、別添記載の債権放棄予定額の9割を目処とすること、⑧この連絡に意見等がある場合には、3月25日までに連絡頂きたい、というものであった。
■平成8年3月26日、Bは同社の母体行に債権放棄を要請した。
■平成8年度暫定予算案(期間50日)が、平成8年3月26日、衆議院予算委員会に付託され、同月27日衆議院本会議において可決された。また、同案は、同日参議院予算委員会に付託され、同月29日参議院本会議において可決された。
■平成8年3月28日、Bは一般行に債権放棄を要請した。
■平成8年3月29日、Bの母体各社は、債権放棄に関する協定を締結した。
■平成8年3月29日、原告は、Bと本件約定書により本件債権放棄をする旨の契約を締結した。
■平成8年4月11日、平成8年度予算が衆議院本会議で可決され、同日参議院予算委員会に付託された。
■平成8年5月10日、平成8年度予算が参議院本会議において可決された。
■平成8年5月21日、「特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法(案)」につき、衆議院本会議において趣旨説明が行われ、同日委員会に付託された。
■平成8年6月18日、右(一四)の法律案が可決されて成立(以下「住専処理法」という。)した。なお、住専処理法においては、I株式会社(以下「I」という。)、株式会社J(以下「J」という。)、株式会社K(以下「K」という。)、L(以下「L」という。)、M株式会社(以下「M」という。)、N株式会社(以下「N」という。)及びBが対象とされていた(以下、右の7社を併せて「住専七社」といい、住専処理法において処理の対象とされなかったO株式会社(以下「O」という。)と併せて「住専八社」という。)。
■平成8年6月21日、住専処理法が施行された。
■平成8年6月26日、Bは、株主総会における特別決議により、同社の定款に「当会社の存立時期は、営業全部を譲渡する旨の営業譲渡契約が締結された日又は平成8年12月31日のいずれか早い日までとする」との存立時期の定めを新設する解散及び営業譲渡に関する定款一部変更の決議をした。
■平成8年8月31日、株式会社P(以下「P」という。)とBとの間で、平成8年10月1日に営業譲渡をする旨の財産譲渡契約を締結した。
■平成8年9月1日、Bが解散した。
■平成8年10月1日、Bは、Pに対して営業譲渡を行った。
(補足)興銀事件とは
JHL社(当事案におけるB社)の設立から解散の経緯

■JHL社は,興銀,株式会社日本債券信用銀行(設立時の商号は株式会社日本不動産銀行。以下「日債銀」という。),証券会社3社(以下,この5社を「本件母体5社」という。),その他を発起人として設立されたいわゆる住専7社の一つである。
■興銀は,JHL社の設立母体として,役員等を派遣し,その経営に深く関与してきたが,バブル経済の崩壊による地価の下落で,同社の財務・経営状態は急激に悪化した。JHL社は,平成4年5月,第一次再建計画を立案し,本件母体5社及び非母体金融機関にたいして支援要請を行った。
■その前後から,農協系統金融機関(以下「系統」という。)の債権回収の動きがみられたため,興銀は系統の融資残高の維持を図るため,母体が責任をもってJHL社を支援していく旨を表明し,さらに,系統の短期貸付金(担保の対象外)を中長期債権(担保の対象)に振り替えると同時に,興銀及び日債銀が有する中長期債権を短期債権に振り替えることを行った。
■第一次再建計画の策定以後,住専各社の経営環境はよりいっそう悪化し,JHL社においても第二次再建計画(本件新事業計画)の策定を求められるに至った。JHL社を含む住専7社の再建計画の策定に当たっては,大蔵省が再建計画の骨格を示し関係金融機関の協力を得ることとなり,系統との関係ではその監督官庁である農林水産省を通じ折衝した。交渉は難航したが,系統も最終的には再建計画に協力するとの態度をとった。
■その結果,大蔵省と農林水産省は,平成5年2月3日,①(住専各社の)再建については,母体金融機関が責任を持って対応する,②系統(の住専各社)に対する金利減免の水準については4.5%とする等を内容とする覚書(大蔵・農水覚書)を締結した。
■これを受けて,JHL社は平成5年5月に本件新事業計画の概要を固め,関係金融機関の同意を得て,興銀及び日債銀の金利を0%,一般行2.5%,系統4.5%とする,金利減免が実施されることとなった。また,大蔵省に対して再建計画に沿って責任をもって対処する旨の念書を差し入れるとともに,系統を構成する農林中金等に対しても,原告が本件母体5社とともに本件新事業計画に対する協力を要請する書面を提出した。
■新事業計画に基づく支援は開始されたが,JHL社の経営はさらに悪化し,平成7年9月22日,本件母体5社は,同社を整理する方針を確認し,大蔵省に報告した。興銀及び日債銀は,JHL社の整理に向けて系統との協議を開始したが,大蔵省中小金融課金融会社室から債権額に応じた損失の平等負担を求めることは避けるように要請されていた。
■系統はいわゆる完全母体行責任を主張し,興銀及び日債銀は,いわゆる修正母体行責任を主張し,貸出金の全額を放棄するのが限度であるとしたため,交渉は平行線をたどったところ,平成7年11月29日に大蔵省は母体行の役員を招集して,大蔵省として住専処理について関係当事者間の仲介を行う旨伝えた。大蔵省は,農林水産省と協議し,住専各社の有する第W分類債権相当額の6兆2,700億円及び欠損見込額1,400億円を一次ロスとして,母体行債権3兆5,000億円の全額放棄,一般行は1兆7,000億円の債権i放棄をする,という大蔵省案を平成7年12月17日に原告側に提示し,原告及びほかの母体行も,おおむね一次ロスの処理については同意すると回答した。平成7年12月19日,①住専処理機構iの設立,②関係金融機関に対し,次のとおり要請すること,すなわち,母体行は債権3兆5,000億円の全額放棄,一般行は1兆7,000億円の債権放棄,系統は貸付債権の全額返済を前提として住専処理機構に対する5,300億円の贈与,③政府は預金保険機構の住専勘定に対して6,800億円を支出する等を内容とする本件閣議決定を行った。
■さらに,残る第皿分類資産に係る損失見込額1兆2,400億円の二次ロスの処理について,平成8年1月25日,最終的な合意が成立した。上記合意を受けて,政府与党は二次ロスの処理案を最終的に決定し,同年1月30日に本件閣議了解がされた。
国会審議等の状況

■平成8年1月22日,住専問題の処理のための資金支出等が織り込まれた平成8年度予算案につき,衆参両院本会議で趣旨説明が行われ,衆議院予算委員会に付託された。政府は,同年2月9日,本件閣議決定及び本件閣議了解の内容を実現すべく住専の整理に伴う住専処理法案を国会に提出した。
■当時最大野党であった新進党は,平成8年度予算案に計上している6,850億円の住専関係予算を削除する,という方針を平成8年2月27日に発表し,同年3月4日には同党議員が予算委員会の会場の第一委員会室に座り込みを開始し,同月25日まで継続した。また,新進党は,平成8年3月13日には,「住専問題に関する具体的方針」を発表した。その内容は,①住専処理に税金を投入しない,②予算案からの6,850億円の削除,③住専の処理は法的処理により公正・透明なルールの下で行う,④会社更生法の適用,⑤「不良債権処理公社(日本版RTC=整理信託公社)」(仮称)の設立,等であった。
■共産党も税金の投入に反対し,マスコミ・世論も,法的処理によるべきとの意見もあったが,母体行の責任を追求し,税金の投入に反対するとの意見が多く存在した。
本件債権放棄等

■興銀は,住専7社に対する減免予定債権額6,607億円と大手銀行21行の中で突出していたが,一般貸倒引当金の残高が極めて不十分であり,住専債権についての債権償却特別勘定の設定もしていなかった。このため平成8年3月期決算において,引当金不足が問題視され,商法285条の4第2項違反の責任を追及される可能性があった。このため興銀は,JHL社に対する債権を平成8年3月期決算において貸倒処理による直接償却をするほかないと判断し,平成7年11月27日,中間決算報告の記者会見でこの方針を公表し,赤字額の圧縮のため,同月以降含み益を実現する目的での株式売却を行い,その利益の額は平成8年3月までの間に合計4,603億円に達した。
■興銀は平成8年1月以降,顧問税理士を通じて国税庁に対して,本件債権は全額回収不能であるとして直接償却できないか相談したが,国税庁の担当者は法人税基本通達(以下「法基通」という。)9-6-2の全額回収不能に基づく貸倒償却の方法で税務処理を行うことはできないこと,住専7社の母体行が債権放棄をすれば法基通9-4-1によって,寄付金認定を行わず,損金算入することができると述べた。興銀としては,住専処理法案が成立する見通しもない段階で本件債権を放棄し,その後,法案が成立しなかった場合には,株主代表訴訟による責任追及されるおそれがあったことから,債権放棄することは避け,全額回収不能であるとして税務処理したいと考え,再度,国税庁と協議したが,答えは変らなかった。
■他方,平成8年2月以降,大蔵省の主導で住専処理案の実行に伴う事務的・細目的事項の詰めを行う母体行代表者会議が行われたが,会議の場等において,大蔵省担当官から債権放棄を実行することを強く懲悪された。
■住専向け債権を平成8年3月期において,税務上どのように処理するかは,銀行各社で慎重な議論が重ねられた模様であるが,結果的に住専向け債権を放棄したのは,興銀の他に株式会社日本長期信用銀行(以下「長銀」という。)や株式会社和歌山銀行(以下「和歌山銀行」という。)であり,それぞれ債権放棄を行い,これに損金算入して法人税の申告をした。
■和歌山銀行については,法基通9-4-1の適用が否定されなかったが,長銀については損金算入が否認されたが,その後長銀が経営破綻し一時国有化されたためか,訴訟には至らなかった。
■この両行を除いては,他の住専母体行は,平成8年3月期での債権放棄は時期尚早と判断し,債権放棄を見送っている。
■興銀は,平成8年3月21日にJHL社の一般行すべてに対して,政府処理案に基づく債権放棄等予定額を計算し,これを案内する内容の「日本ハウジングローン株式会社の損失処理に関するご連絡」と題する書面(本件損失に関する連絡)により通知した。本件損失に関する連絡には,これに意見等がある場合には,同月25日までに連絡してほしい旨の記載がされていたが,一般行から特段の意見は表明されなかった。
■本件母体5社は,平成8年3月29日,JHL社の営業譲渡の日までに貸出債権を全額放棄することを確認し,書面を作成した。興銀は,同日,取締役会を招集し,JHL社向けの母体行債権の全額放棄を決議し,同日付けで,JHL社との問で,債権放棄約定書を締結し,本件債権放棄をした。右債権放棄約定書には,興銀が対象債権を,同日付けでJHL社の「営業譲渡の実行及び解散の登記」が平成8年12月末日までに行われないことを解除条件として,放棄すること等を内容としていた。なお,取締役会の際に配布された資料中には,「仮に政府案の不成立により法的整理となっても,平等弁済の主張は社会的責任不履行による信用失墜を招きかねず,何れにしても債権放棄は不可避」と記載され,また,解除条件について,「実際上想定し難い破産の場合(プロラタ配当)との比較において,本行に損害を与えたとの代表訴訟上の主張誘発を防止する効果」があると説明されていた。
■本件損失に係る連絡では,正常資産及び不良資産のうち回収が見込まれるものの合計額は,1兆2,103億円であり,実質的には一般行及び系統に返済される合計額は,1兆791億円ということになっていた。平成8年5月10日,平成8年度予算案が参議院本会議で可決され,同年6月18日には,住専処理法が成立して,同月21日施行された。これを受けて,JHL社は,同月26日,株式総会における特別決議により,解散及び営業譲渡等の決議をし,同年9月1日解散した。また,興銀は,同年6月26日ころ,貸付契約証書,約束手形等の関係書類を返還した。
■興銀は,平成8年7月1日,本件債権相当額を損金算入した上で,本件事業年度の確定申告書を提出した。これに対して,所轄の麹町税務署長は,東京国税局の職員の調査に基づき,平成8年8月23日付で本件債権相当額の損金算入を否認する内容の更正処分とこれに係る過少申告加算税賦課決定処分(以下,これらを合わせて「本件更正処分等」という。)を行った。興銀は,本件更正処分等を不服として平成8年8月30日,国税不服審判所長に対し審査請求をしたが,平成9年10月27日付で棄却されたため,同年10月30日,本件更正処分等の取消しを求める訴えを提起した。その後,麹町税務署長は,平成10年3月31日,興銀の本件事業年度の法人税についての再更正処分とこれに係る過少申告加算税及び重加算税の賦課決定処分(以下,「再更正処分等」という。)を行なった。興銀は,本件再更正処分が行なわれたことを受けて,訴えを本件再更正処分等の取消しを求める訴えに交換的に変更した(以下,本件更正処分等と本件再更正処分等を併せて「本件各処分」という。〉。
編集者コメント
かの有名な藤山判決

■我が国金融史上でも希有な住専破綻処理の一環として行われた不良債権をめぐる巨額な貸倒損失計上事件で、しかも第一審が有名な「藤山判決」で,藤山雅行裁判長は貸倒れの認定に当たり「通達基準」を採用せず,「社会通念基準」を持ち出し納税者を勝訴させた。
■債権の全額が回収不能か否かについては、法人税法が法人の合理的な経済活動によってもたらされる利益に着目して法人税を課していることからすると(法人税法4条)、合理的な経済活動に関する社会通念に照らして判断するのが相当であり、法的措置を講ずれば、ある程度の回収を図れる可能性がないとはいえない場合においても、債務者の負債及び資産状況、事業の性質、債権者と債務者との関係、債権者が置かれている経済的状況等諸般の事情を総合的に考慮し、法的措置を講ずることが、有害又は無益であって経済的にみて非合理的で行うに値しない行為であると評価できる場合には、もはや当該債権は経済的に無価値となり、社会通念上当該債権の回収が不能であるとの判決は秀逸と、現在も評価されている。
貸倒損失の意義

■法人の有する貸付金その他の金銭債権の貸倒れは,各事業年度の所得の計算上,損失として損金の額に算入される(法人税法22条3項3号)。
■そして,同法33条2項が金銭債権の評価損の計上を認めていないことから,金銭債権の貸倒損失を損金の額に算入するためには,当該金銭債権の全額が回収不能であることを要すると解されている。これが,現在の通説・判例ともいうべきであり,一審から最高裁まで全てに「貸倒れ」とは「債権の全額が回収不能」な状態であるとしている。興銀と国側の訴訟での主張も,この見解を前提としている。
■そして,「回収不能」か否かということは,本来事実認定の領域に属する問題である。しかしながら,一審判決と二審判決,さらには最高裁と,判断内容には差があり,論者による判決の評価にも隔たりが生じていることは,周知の通りである。
■見てきたように、「貸倒れ」の状態,あるいは「回収不能」の意味内容についての基本的な理解の仕方の違いが,判決や各論者が結論を出すにあたっての大きな差となって表れている。「貸倒れ」事例をめぐって,これまでの判決から抽出された要因や判断基準が,個別の事案における個別の事情に止まることが多く,事実認定をする際の決定的基準としては十分に機能し得ないことも念頭に置くべきであろう。
■すなわち,過去の事例における判断要因が一応の目安となったり,あるいは,ある種の傾向を示したりすることがあるとしても,必ずしも常に将来の問題を解決する決定的切り札となるわけではない。これまでの個別事案をめぐる議論においても,これらの事実や要因のうち,どの点を強調するか,何を重視するかは,判決や論者により異なる傾向がある。結局は,「貸倒れの事実」あるいは「回収不能」状況の認定判断は,将来的にも,個別的・具体的な事実状況を踏まえて裁判所が行う認定判断を待つ他はないであろう。さらに,「回収不能」の判断枠組みをどのように設定するかによっても,その具体的な判断に大きな違いが生じてくると考えられる。
■税法は常に進化の過程にある。今後も、租税訴訟が活性化されることを切に願う。
日銀のプリンス バブルを止めた平成の鬼平

■大蔵省の存在感が際立つ判例であったので、ここで、簡単に、当時の日銀総裁の時代という観点から、時代的風景を描写しておく。
■1989年12月、澄田智前日銀総裁からバトンを引き継いで登場した三重野康第26代総裁は、苛烈なバブル経済の火も引き継ぐこととなった。戦後経済史上不名誉な「バブルの時代」の絶頂期でのバトンタッチであった。やがて「バブルをとめた平成の鬼平」というニックネームを冠せられることとなったが、数年を経て一転バブル経済の後遺症が顕在化するたびに「不良債権は鬼平の遺産」と辛口の批判を受けることとなった。三重野総裁時代の約5年間は、前半はバブルの退治に、後半はバブル後遺症の対応に奔走し奮闘した歳月であった。
■三重野総裁の在任期間(1989年~1994年)は、日本経済が文字通りバブル経済に翻弄された時代であった。金融引き締めや総量規制によりようやくバブルは収束を遂げるが、その後今度は一気にバブルが崩壊し、不況対策、金融機関の破綻処理に悪戦苦闘の連続であった。
■ところでこの時代、経済情勢だけではなく、政治情勢も混沌を極めた。自民党の一党支配体制が崩れ、非自民政権が生まれた。海外情勢に目をむけると、歴史的な米ソ冷戦の終結、東西ドイツの統一、湾岸戦争の勃発など予断を許さない状況が続き、国際金融情勢や為替市場も動揺、国内の政策運営にも種々の問題を惹起し、総じて、波乱が渦巻く時代であったと言える。激動のこの期間、我が国の政権を担当したのは、海部内閣(橋本龍太郎蔵相)、宮沢内閣(羽田孜蔵相、林義郎蔵相)、細川内閣(藤井裕久蔵相)、羽田内閣(藤井裕久蔵相)、村山内閣(武村正義蔵相)であった。
■1991年、バブルはとまった。しかし、その後に大きな崩落が待ち伏せていた。山高ければ谷深しである。以後日本経済は、資産デフレに向かって、急転落の坂道を下ることとなった。三重野総裁は、1991年7月から1993年9月までの間に、実に7回(6%から1.75%へ)に及ぶ公定歩合の引き下げを行い、さらに政府も累次の緊急経済対策を行ったが(1992年、1993年、1994年の3度に渡る財政出動により事業規模で約30兆円、国債発行約8兆円)、それでも焼け石に水のごとき様相を呈した。
■急転落の坂道はすさまじいばかりの「資産のデフレ」であった。「資産デフレ」は、戦後では初めての経験であった。後にこれには次のような要因があったと分析されている。①資産価格の低下による「逆資産効果」(いわゆる逆ピグー効果)、②資産価格低下の反面、負債残高は減少しない(いわゆるフィッシャー効果)、③それら両面からくる総需要(消費、投資)の大幅縮減、④景気対策として打ち出された国債発行に随伴すると言われる円高効果(いわゆるマンデル・フレミング効果)が重なり、劇症をもたらした。
■なかでも、過剰債務は金融機関の不良債権と表裏一体であって、深くかつ長い後遺症を残すこととなった。三重野総裁時代、この不良債権の重荷に耐えかねて、自力再建が困難となった金融機関の破綻がにわかに表面化してきた。東邦相互、東洋信金、太平洋銀行、兵庫銀行、東京協和信組、安全信組、そして、住宅金融専門会社である。これらの破綻も、あとから見ればまだ序の口であったわけであるが、当時は銀行安泰神話の時代、一般はもとより政策当局にあっても驚きで、まさに、金融システム全体の問題として日銀の前に立ちはだかった。
松下康雄日銀総裁 金融修羅場の時代

■三重野総裁の後任として第27代総裁に就任した松下総裁の時代は、バブル崩壊の悪影響が、社会のさまざまな側面に一気に露呈した暗澹たる世相の時代であったと言われる。
■1つには、バブル崩壊不況の長期化から、金融機関の倒産が相次いだこと、2つめには、その裏面でバブル絡みの企業犯罪や金融不祥事が多発したこと、そして3つめには、こうした事態に、政官癒着スキャンダルが垣間見え、日本国民のひんしゅくをかい、大蔵省をはじめ金融当局への批判となって噴出たこと、が挙げられる。
■松下総裁時代に生じた主な金融機関の倒産事件は、三重野前日銀総裁から引き継がれた住専の不良債権処理と東京協和、安全両信組の破綻処理である。前者については、当記事でみてきたように、1996年の通常国会が「住専国会」と呼ばれたほど、糾弾一色の大問題であった。住専問題とほぼ並行して、コスモ信組と木津信組の東西大手両信組の破綻と、地方銀行の兵庫、太平洋、阪和各行の破綻が生じ、各地に取り付け騒ぎが起こった。さらに、平成金融危機のクライマックスと評される翌1997年には、三洋証券や、山一証券の経営破綻、北海道拓殖銀行の破綻と言った、昭和金融恐慌以来の恐慌もどきの修羅場が展開され、松下総裁は大変な政策運営を強いられた。
■バブル崩壊期にあって、不良債権の重圧に耐えかね経営破綻に追い込まれた金融機関は、三重野、松下、次の速水総裁三代にかけて続出したのであり、まさに未曾有の出来事であった。松下総裁はその渦中にあったのであり、松下総裁を補佐した福井副総裁も、「金融界は戦場のごとく荒れている」「倒産した金融機関が爆発した地雷のごとく戦場に散らばっている」と苦衷を吐露するほどであった。
■既述の通り、バブル崩壊後の金融不祥事や、監督庁の不手際が、国民批判を高ぶらせ、官僚サイドからの数々の抵抗と曲折を経て、1998年、金融監督庁の発足、金融再生委員会の発足、さらに2000年の金融庁の発足、大蔵省の解体に至った。「火事場の中で消防車を改造する愚」だとか「諸悪の大蔵支配の終焉」とか、政官さまざまに入り乱れての難産ではあったものの、一連はすなわち、もはや時代不適合となった「護送船団方式」から、金融自由化時代への衣替えであった。
重要概念/社会通念
それでも法人税基本通達9-6-2は変わらない

■興銀事件において、第1審判決、最高裁判決のいずれにおいても、社会通念上、回収不能な状態にあったということで貸倒損失の計上を認めている。
■この「社会通念」という内容であるが、債権の無価値とは、当該債権から最早一銭たりとも回収できないという程に厳格なものではなく、その回収に要する費用や回収に踏み切った場合に被る損害等を考慮して、社会通念上当該債権から実質的に意味のある経済的利益を回収できなくなった状態を含む概念であると考えられる。
■社会通念とは法解釈だけでなく、事実認定においても考慮されるべきものであるため、本事件においても、回収可能性の判断において、「社会通念」という概念を織り込んだものといえる。また、社会通念という概念について、裁判官が自分の根拠のない判断を判決で正当化するための特製の裁判用語である、と批判的にこの用語をとらえる見方も存在する。
■確かに、過去の判決で「社会通念」に言及された判例は枚挙にいとまがない。
「社会通念に従って総合的に判断」、「社会通念をも勘案しつつ」、「社会通念に照らして」、「社会通念上相当な程度」、「社会通念に基づいて」、「社会通念上妥当な」、「社会通念上明らか」等判示されてきた。「社会通念」が多様に理解される余地があり、「社会通念」に名を借りた恣意的な判断基準として利用される場合も懸念されるところである。
■しかしながら、社会通念により回収可能性を判断するというのは至極当然のことであり、法人税基本通達の前文においても、以下のように謳われている。
”この通達の具体的な運用に当たっては、法令の規定の趣旨、制度の背景のみならず条理、社会通念をも勘案しつつ、個々の具体的事案に妥当する処理を図るように努められたい。いやしくも、通達の規定中の部分的字句について形式的解釈に固執し、全体の趣旨から逸脱した運用を行ったり、通達中に例示がないとか通達に規定されていないとかの理由だけで法令の規定の趣旨や社会通念等に即しない解釈におちいったりすることのないように留意されたい。”
■ところで、最高裁判決の後、現在まで法人税基本通達9-6-2は改正されていない。この点について課税当局は、最高裁判決を踏まえ、「債権者側の事情等を考慮する必要があることは認識している」という。とはいえ、最高裁判決の後に「貸倒損失の損金算入に係る事前照会窓口」を設けたにもかかわらず、照会がほとんどなかったことから、「最高裁判決で指摘された課税上の弊害は実際に存在していない」というのが課税当局の認識であり、通達改正を行わなかった理由もそこにあるのであろう。
併せて読みたい/手形が不渡りになったことのみでは、貸倒損失として必要経費に算入できないとされた事例
名古屋高裁平成2年(行コ)第24・27号、同3年(行コ)第7号所得税更正処分取消 請求控訴・同附帯控訴事件)/平成4年10月21日判決(納税者敗訴)(確定)
回収不能の認定基準につき、興銀事件以前の事案。
所得税法51条2項(資産損失の必要経費算入)により貸倒損失として必要経費に計上できるのは、原則として、債務者に対し債務免除の意思表示をしたときなど債権が法律上消滅した場合、又はその債務者の資産状況、支払能力等からみて貸付金等の全額が回収できないことが明らかになつたときなど、法律上債権は存在するがその回収が事実上不可能である場合のいずれかに該当することが必要であるとされた事例。そして、右の後者の場合に当たるというためには、前者の場合との均衡、課税金額計算の明確性の要請等に照らし、当該年中に弁済期が到来している債権につき、債務者の倒産、失踪等の事情が生じ、貸付金の回収の見込みがないことが客観的に確実になつた事実が必要として、納税者の貸倒損失の損金算入が認められなかった。


