残波事件
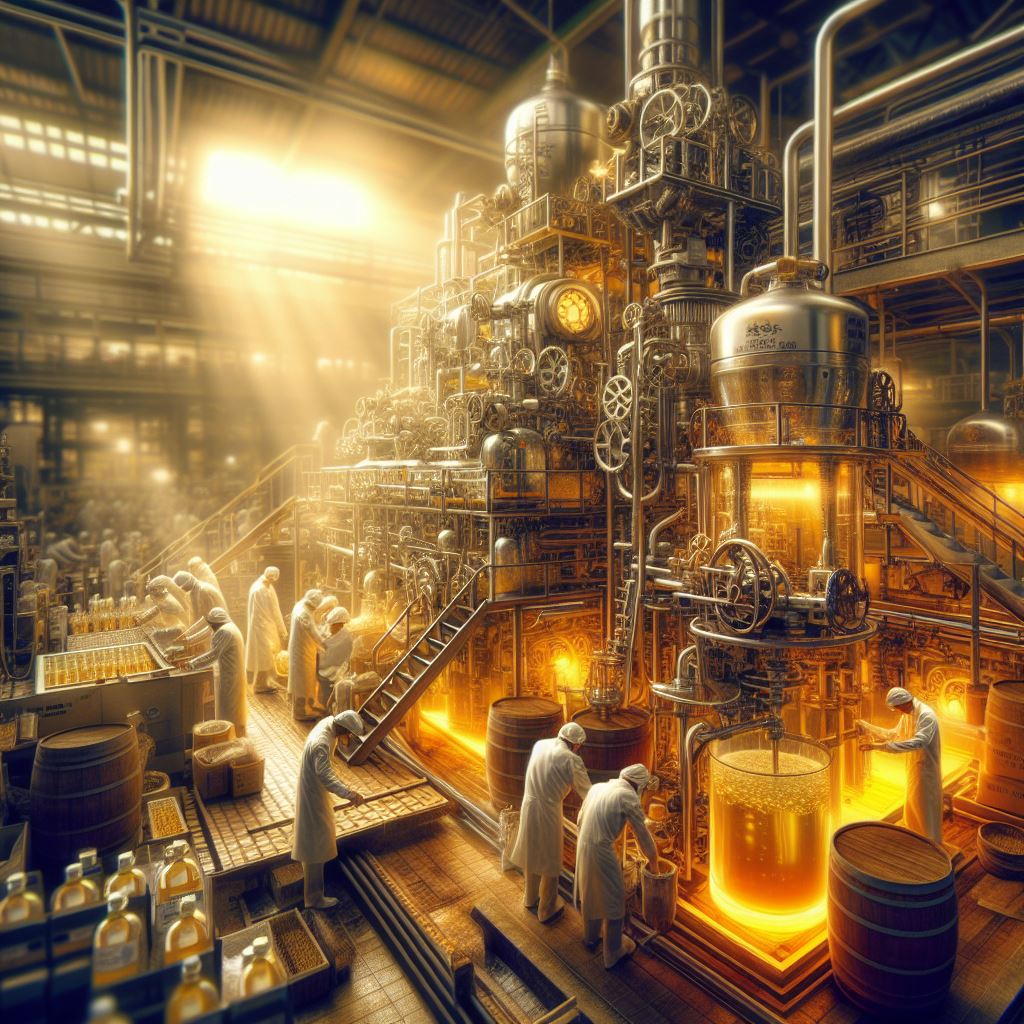
目次
「最高額の平均」ではなく「最高額」まで可
概要
役員給与及び役員退職給与についてそれぞれ不相当に高額な部分の有無及びその金額が争われ、役員給与については各類似法人の役員給与等の最高額の平均ではなく最高額、退職給与については類似法人中の役員給与最高額を基準にした判断が示された。
泡盛とは

■泡盛とは、日本の琉球諸島で造られる伝統的な蒸留酒。
■泡盛の大きな特徴は次の4点。
1. 原料に米を使用する。
2. 黒麹菌を用いる。
3. 仕込みは1回だけの全麹仕込みである。
4. 単式蒸留機で蒸留する。
■日本酒には黄麹、焼酎は主に白麹が使われるのに対し、泡盛造りに使用される麹菌は、「黒麹」。泡盛の特徴はこの「黒麹」を使うという点である。
■泡盛の原料には一部の銘柄を除き、インディカ米(長粒種米:細長い系統の米)が使用されている。
■これは粘り気の強い日本の米(ジャポニカ種)に比べ、硬質でさらさらしているため黒麹菌が菌糸を伸ばしやすい(米麹をつくりやすい)という特性があり、香りや味わいに泡盛独特の風味を出す要因となっている。
■原料の米を、黒麹を使って米麹にし、それに水と酵母を加えてもろみにし、2週間ほどアルコール発酵させる(「全麹仕込み」)。
■蒸留機は「単式蒸留機」を用いる。単式蒸留機は、もろみに含まれる成分をほどよく蒸気に含ませるため、原料の風味をあますところなく蒸留酒に反映させるという特徴がある。
役員らに支給した役員給与(本件給与)及び代表取締役を退任した者に対して支給した役員退職給与(本件退職給与)に、不相当に高額な部分(不相当高額部分)がないかどうかが争われた。
本件給与について課税庁は、倍半基準で抽出した類似法人の役員給与支給実績に照らし、類似法人の各最高額の平均額を超える部分を不相当高額部分であると主張したが、裁判所は、「最高額の平均」ではなく「最高額」を超える部分を不相当高額部分と判断。
本件退職給与については、類似法人間で最高額の乖離が大きいことや、本件の代表取締役は法人に相当の貢献があったことから、類似法人の中の最高役員給与額を用いて算出した金額を超えない限りは不相当高額部分があるといえないと判断して課税庁の主張を認めなかった。
結果、本件給与は原処分維持、本件退職給与は原処分取消しとなった。
納税者は主張が認められなかった部分について控訴したが、高裁で棄却され、上告受理申立ては不受理決定で確定。
■裁判所情報
東京地方裁判所 平成28年4月22日判決判決(舘内比佐志裁判長)(一部取り消し)(原告控訴)
東京高等裁判所 平成29年2月23日判決(高野伸裁判長)(棄却)(控訴人上告)
最高裁判所 平成30年1月25日決定(木澤克之裁判長)(棄却・上告不受理)(確定)
争点
判決
東京地方裁判所
→納税者一部勝訴
本件給与は原処分維持、本件退職給与は原処分取消し
東京高等裁判所
→納税者敗訴
原審維持
最高裁判所
→上告不受理(確定)
役員報酬
法人が役員に対して支給する給与は、その額の決定に役員自身が関与することなどから、損金算入に制限を置いている。
役員への給与や賞与は以下の3種類のいずれかであり、かつ、「相当な額」に限って損金と認められる。
■定期同額給与
■事前確定届出給与
■業績連動給与
キーワード
■キーワード
過大役員給与、不相当に高額、同業類似法人
■重要概念
費用性否定説(利益処分説)
東京地裁/両者の主張
納税者の主張
本件役員らは、各種製造機械及び製造ラインを自らの力で作ることができる特殊技術を有し、安く購入してきた中古機械により、原告の商品製造に最も適した機械・製造ラインを製作するということを行ってきており、これにより優良な収益構造をもたらしている。また、原告においては、平成18年以降、本件役員らの職務内容が大きく追加されており、これに伴い、役員給与が増額された。
“本件役員らは、各種製造機械及び製造ラインを自らの力で作ることができる特殊技術を有し、安く購入してきた中古機械により、原告の商品製造に最も適した機械・製造ラインを製作するということを行ってきており、これにより優良な収益構造をもたらしている。”
“経済合理性に照らすと、優秀な経営者は、そうでない経営者よりも役員報酬が高くなり、また、同等の能力の経営者同士は、同等の水準の役員報酬になるのであるから、本件役員ら給与が適正であるかを検討するに当たり他の法人の役員給与の額を用いる場合、かかる他の法人の役員は、本件役員らと同等以上の経営能力を持つ者となっていなければならない。”
被告が採用する倍半基準によると、売上高が2分の1から2倍の範囲に入る法人のみを抽出し、それ以外の法人は全て抽出しないこととなる。しかし、費用低減の重要性が認識される現代の経営において、役員の経営能力が、売上げが2倍を超える法人の経営能力と同等ないしそれ以上あるという例は多数存在するから、倍半基準によると、本来抽出されなければならない同等の経営能力を有する役員に係る同業種法人の抽出漏れを招いてしまう。同等の経営能力を有する役員に係る同業種法人は、日本全国から漏れなく抽出されなければならないが、被告は、沖縄国税事務所・熊本国税局管内に限定して抽出しており、このような抽出方法は失当である。また、原告と比較する法人の抽出に当たっては、単式蒸留しょうちゅう製造業のみならず、酒類製造業全部を抽出すべきところ、被告は、単式蒸留しょうちゅうに業種を限定して抽出しており、このような抽出方法は失当である。
“被告が採用する倍半基準によると、売上高が2分の1から2倍の範囲に入る法人のみを抽出し、それ以外の法人は全て抽出しないこととなる。
しかし、費用低減の重要性が認識される現代の経営において、役員の経営能力が、売上げが2倍を超える法人の経営能力と同等ないしそれ以上あるという例は多数存在するから、倍半基準によると、本来抽出されなければならない同等の経営能力を有する役員に係る同業種法人の抽出漏れを招いてしまう。”
適正給与額が、比較法人の役員給与の平均額であることはもとより、最高額であるともいえず、比較法人の資料から適正給与額を導く手法は、いずれも失当である。
“被告は、本件役員ら給与の額が、比較法人の役員給与の平均額であると主張する。
したがって、適正給与額が、比較法人の役員給与の平均額であることはもとより、最高額であるともいえず、比較法人の資料から適正給与額を導く手法は、いずれも失当である。”
平成17年の会社法の成立に伴い、利益処分とされていた役員賞与は、費用として整理され、平成18年法律第10号による改正前の法人税法35条は、削除されることとなり、隠れた賞与支給は観念することすらできなくなったのであり、また、平成18年法律第10号による改正により、法人税法34条1項は、損金算入が認められる役員給与の支給方法は、定期同額給与(同項1号)又は事前確定届出給与(同項2号)という期初段階であらかじめ支給額を決定しなければならないものに限定されることとなり、期中における恣意的な役員給与の支給も不可能となった。
このように、平成18年の法人税法の改正によって、隠れた賞与支給概念が消失し、期中における恣意的な役員給与の支給が不能となったのであって、法人税法34条2項の趣旨は実現されて死文化し、納税者への同項の適用は観念されないものとなった。
法人税法34条2項の規定が存置されたのは、損金算入できる役員給与の支給形態が、定期同額給与と事前確定届出給与の二つに限定されることとなり、期中にその支給額を変更することについて、極めて厳しい制限がかかるようになったことからすれば、期初の段階において、事業継続のために必要な利益が確保されないような予算計画が立てられ、その原因が役員給与の高額化にあるというような究極的な場合に過大役員報酬として否認できるようにするためであり、このような場合に適用されるにすぎない。
しかるに、原告においては、新事業年度開始の1ないし2か月前から予算計画の作成を開始し、売上高、粗利益率、売上総利益、必要的販管費及び事業利益を客観的合理的に算出した上、目標経常利益の枠内で役員報酬の支給枠を算出し、最終的にその支給枠の中で役員報酬を決定してきたのであって、期初の段階で必要な利益が確保されないような予算計画が立てられてはいないから、法人税法34条2項の適用の余地はない。
“過大役員給与を定めた法人税法34条2項は、以下に述べるとおり、既に死文化した規定であり、同項を原告に適用すること自体がそもそも誤っており、本件各更正処分等は取り消される必要がある。”
法人税法34条2項、法人税法施行令70条そのものは違憲性を有するものではないが、憲法84条の趣旨からすれば、納税者側からも十分に認識可能な、法人税法施行令70条1号イで明示された要素のうち、①当該役員の職務の内容、②その内国法人の収益、③その使用人に対する給与の支給の状況に基づき、職務対価相当額を求めた後、その相当性補強の一環として、④事業規模類似の同業種法人における役員給与の支給状況を用いて確認する場合には、納税者の予測可能性の担保されたもので、特に違憲の問題は生じない。
しかし、上記④を用いなければ職務対価相当額が導かれないのであれば、法律で納税者側で把握することの不可能な事項によって課税処分を行うことが法定されていない限り、納税者の予測可能性が害された違憲の課税であるというべきところ、法人税法34条2項には、その旨の明文の規定がないから、本件各更正処分等は、憲法84条に反するものである。
法人における役員給与支給額を把握することは、現在不可能であり、課税庁から事業規模類似同業種法人の役員給与支給額が提示されても、法人名等の一切が秘匿されていることにより、その内容が正しいか、意図的に納税者側に有利な資料が除外されていないか、といったことを納税者側では一切検証することができない。
原告において、その適法性を一切検証することが不能となっているから、本件各更正処分は、憲法31条に違反するものとして取り消されなければならない。
被告主張の倍半基準及び平均額法により、上場企業の役員給与について検討すると、自動車業界については、日産自動車の同業種類似法人として抽出されるトヨタ自動車及び本田技研工業の役員給与と比較して、日産自動車の代表取締役であるカルロス・ゴーンの役員給与は、過大役員給与となり、電気機器業界については、ソニーの同業種類似法人として抽出される日立製作所、パナソニック、東芝、富士通及び三菱電機の役員給与と比較して、ソニーの代表取締役である平井一夫の役員給与は、過大役員給与となり、総合商社については、伊藤忠商事の同業種類似法人として抽出される三菱商事、丸紅、三井物産及び住友商事の役員給与と比較して、伊藤忠商事の代表取締役である岡藤正広の役員給与は、過大役員給与となる。
被告は、上記各上場企業については、過大役員給与額に係る課税処分を行わず、原告に本件各更正処分をしたところ、合理的な理由を欠いた不平等な課税処分であるから、本件各更正処分は、憲法14条に違反する。
“しかし、上記④を用いなければ職務対価相当額が導かれないのであれば、法律で納税者側で把握することの不可能な事項によって課税処分を行うことが法定されていない限り、納税者の予測可能性が害された違憲の課税であるというべきところ、法人税法34条2項には、その旨の明文の規定がないから、本件各更正処分等は、憲法84条に反するものである。”
“本件退職給与については、以下の点により、不相当に高額であるとはいえない。
国税庁の主張
本件役員らの平成15年1月20日から平成21年6月28日までの職務の内容については、本件各事業年度の間に本件役員ら給与を大幅に増額させなければならないほどの職務内容の変化を示す事実は認められない。
“本件役員らの平成15年1月20日から平成21年6月28日までの職務の内容については、要旨、次のとおりであるところ、これらは、いずれも酒類の製造及び販売等を目的とする一般的な法人の役員において想定される職務内容を超えているものとは認められず、本件各更正処分時における調査担当者の調査に基づいても、本件各事業年度の間に本件役員ら給与を大幅に増額させなければならないほどの職務内容の変化を示す事実は認められない。”
“抽出基準は、原告と業種及び事業規模等において類似牲を有する法人となるように設定したものであり、これにより抽出した類似法人の役員給与支給事例は、沖縄国税事務所長からの管内各税務署長及び熊本国税局への通達指示及び依頼といったいわゆる通達回答方式による方法に基づき、沖縄国税事務所及び熊本国税局管内の各税務署長が抽出条件に該当するものを機械的に抽出したものであるから、いずれもその抽出に当たって恣意の介入する余地はない。したがって、抽出された役員給与事例については、正確性と普遍性が担保され、調査結果が合理的なものであることは明らかである。”
“比較法人の役員報酬ないし役員給与の最高額を採用した場合には、比較法人の中にたまたま不相当に高額な部分の金額が含まれる役員給与を支給しているものがあった場合には不合理な結果となるし、平均値を算出することによって比較法人間に通常存在する諸要素の差異やその個々の特殊性が捨象され、より平準化された
“原告が本件各事業年度において本件役員らに支給した役員報酬ないし役員給与の額に不相当に高額な部分の金額があることは明らかであり、旧法人税法34条1項及び法人税法34条2項の規定により、その不相当に高額な部分の金額については、損金の額に算入されないこととなる。”
“しかし、旧法人税法施行令69条及び法人税法施行令70条は、職務執行の対価として相当である役員給与額を判断する基準として、その勘案すべき要素の一つに、その法人の「使用人に対する給与の支給の状況」を明示して挙げているところ、使用人は法人と雇用関係にあり、自らの労働の対価を決定する権限を持たないことから、使用人に対する給与の額については恣意性の入る余地が少ないと考えられるのに対し、法人の役員は、法人の委任を受けてその業務を執行する立場にあり、法人が獲得した利益の分配にあずかる地位にもあるため、その給与の額のうちに、法人利益の分配と目される部分の金額が潜在する可能性があるのであるから、役員給与の相当性を判断する要素の一つとして、使用人に対する給与の支給状況を採用し、これに照らして判断することは客観的かつ合理的であるというべきである。したがって、使用人に対する給与の支給状況の検討が必要となるのは、使用人兼務役員の場合に限定されるとする原告の主張には理由がない。”
“そもそも、旧法人税法施行令69条及び法人税法施行令70条1号においては、役員給与の相当性を判断するに当たり、その法人と同種の事業を営む法人で事業規模が類似するものの役員に対する給与の支給の状況に照らして判断することとされているところ、高い経営能力を有する役員が必ずより多くの役員給与を受けるという原告の上記主張を前提とすれば、その判断の際には、当該役員の経営能力と類似法人の役員の経営能力を個々に比較して優劣をつけるという判断をする必要があることとなるが、そのような判断は極めて主観的、恣意的なものとならざるを得ず、客観性を欠くこととなるから不合理である。”
“総売上金額は法人の事業規模を示す最も重要な指標の一つであることから、総売上金額に着目した基準である倍半基準は、事業規模の類似する同業者を抽出するための基準として優れた合理性を有するものとして一般に承認されているものであり、他方、旧法人税法施行令69条1号及び法人税法施行令70条1号が定める類似法人の抽出は、適正役員給与月額を算定する一つの資料、指標を得るための手段にすぎないことに鑑みれば、類似法人の範囲を事業規模の点から一定の範囲内に絞るために使用される倍半基準の適用においては、事業規模に関する指標である売上金額のみに適用することで十分というべきである。”
“また、類似法人を抽出する上で、業種を同業種の法人に限定することは、旧法人税法施行令69条1号及び法人税法施行令70条1号が「同種の事業を営む法人」と規定することに基づくものであるところ、その抽出においては、業種、業態、規模(売上金額、期末資産合計額、従業員数)、収益状況等ができるだけ当該法人と類似するものであることが望ましいとされているのであるから、類似法人を抽出するに当たり、原告の製造する酒類のほとんどが単式蒸留しょうちゅうであることを踏まえて、単式蒸留しょうちゅうを製造する法人を抽出することに何ら不合理はない。”
“法人が支給する役員給与については、役員に直接的に経済的利益を帰属させるという態様からお手盛り的な支給が懸念され、会社法制上も特段の手続的規制に服するものとされているところ、税法上の観点からは、このような性質の経費の損金算入を安易に認め、結果として法人の税負担の軽減を容認することは、課税の公平上問題がある。そこで、我が国の税制では、従来から役員給与の支給の恣意性を排除することが適正な課税を実現する上で不可欠であると考え、具体的には、法人段階で損金算入される役員給与の範囲を職務執行の対価として相当とされる範囲に制限することとされてきたところである。これは、役員報酬が不相当に高額であれば役務提供の対価として当該事業年度の期間収益に対応する費用という性格を超えたものになるという考え方によるものである。”
税務調査時における原告の説明によると、平成22年7月12日時点では、報酬については業績に応じて決めているのであって、行き当たりばったりに決めているわけではないと説明していたが、これに先立つ平成22年2月10日時点では、役員報酬額は経営状況を見て役員4人で決めており、算定根拠及び参考資料とした資料はないとしているのであって、説明が変遷している上、当初の説明は、本件における原告の主張と齟齬している。原告が異議申立て及び審査請求段階において添付書類として提出した予算計画書は、本件で提出する予算計画書と数値に多数の食い違いがあり、実際に後者の予算計画書に記載された予算計画が存在していたかどうかについては合理的な疑いが存する。
したがって、法人税法34条2項の意義が「究極的な場合」に過大役員報酬として否認できるようにするためにあるとか、死文化したなどという原告の主張は、法令を正解せずに独自の見解を述べるものにすぎず、何ら理由がない。
“したがって、法人税法34条2項の意義が「究極的な場合」に過大役員報酬として否認できるようにするためにあるとか、死文化したなどという原告の主張は、法令を正解せずに独自の見解を述べるものに
“しかしながら、租税法においては、多分に専門的技術的かつ細目的な事項が存在するから、それぞれ諸条件等が異なる個々の課税客体について、公平に課税するとともに、課税標準算出の手続等を明確にするためには、専門的で複雑な規定を必要とし、これらの課税要件全てを法律で規定することは実際上困難であって、一定の範囲で課税要件等を法律よりも下位の法形式である政令省令等に委任されることも憲法上許容されている。”
“しかし、原告の主張する各上場企業の比較のみをもって、過大役員給与の認定を受けるべきか否かを判断することはできないし、実際に過大役員給与を理由とした課税処分がされたか否かも明らかではないから、原告の主張は前提を欠き、失当である。”
法人税法施行令70条2号に規定される、従事した期間、退職の事情、類似法人の退職給与の支給状況等に照らし「その退職した役員に対する退職給与として相当であると認められる金額」を具体的に判定するためには、功績倍率法(退職する役員の最終月額給与の額に、その役員のその内国法人の業務に従事していた年数及び功績倍率を乗じて算出する方法)が合理的である。
原告における乙の退職給与の額の算定における功績倍率は3倍であるところ、類似法人における功績倍率は2.7倍である。したがって、原告が採用した功績倍率は類似法人が採用した功績倍率を0.3ポイント上回るが、原告が採用した3倍の功績倍率は妥当な範囲と考えられる。
“法人税法施行令70条2号に規定される、従事した期間、退職の事情、類似法人の退職給与の支給状況等に照らし「その退職した役員に対する退職給与として相当であると認められる金額」を具体的に判定するためには、功績倍率法(退職する役員の最終月額給与の額に、その役員のその内国法人の業務に従事していた年数及び功績倍率を乗じて算出する方法)が客観的であり合理的と認められる。”
原告は、比較法人は、比較対象として適切でないと主張する。
しかし、上記各法人を含めた比較法人は、恣意の介入する余地のない客観的な条件によって抽出されたものであり、このような過程で抽出された法人を適切な理由もなく排除するのは適正額の算定の合理性を保つ上で許されるものではない。
すなわち、売上高や改定利益の金額と役員給与の適正額は必ずしも比例的関係になく、改定利益の金額や自己資本比率が低いことをもって原告よりも経営判断が劣っていると断言できるとはいい難く、役員給与の適正額が低くなるともいい難いし、そもそも原告よりも経営判断が劣っているか否かという要素は極めて主観性が強く、恣意的な判断が介入する余地が大きいから、役員給与の適正額の算定において考慮すべきものとは認められない。
平均功績倍率法は、当該退職役員の当該法人に対する功績はその退職時の報酬に反映されていると考え、同種類似の法人の役員に対する退職給与の支給の状況を平均功績倍率として把握し、比較法人の平均功績倍率に当該退職役員の最終報酬月額及び勤続年数を乗じて役員退職給与の適正額を算定する方法であるところ、ある法人のある役員の退職給与に係る適正額の算定において、当該法人の他の役員の功績倍率を直接用いて算定すべきものではない。乙の功績倍率は3.0としたのは何ら不合理ではなく、原告の主張は理由がない。
“しかしながら、戊への退職給与が税務調査の際に否認されなかったとしても、功績倍率が■■■■であることにつき税務上何ら問題がないと是認したものではないことはもとより、その後の事業年度の他の役員らに対する役員給与等に係る申告内容をそのまま是認する根拠となるものではない。
東京高裁/両者の主張
納税者の主張
“加えて、本件役員らは、役員として稼働する実態があるのみならず、控訴人に対する多大な貢献も認められる。すなわち、本件は、租税回避のため実体のない名目的な役員に過大な給与を支給する事案とは一線を画すものである。このような事案に対し、みだりに過大役員給与を認定して役員給与支給額の抑制化を招くことは、結果として、役員に対する報酬インセンティブの鈍化をもたらし、日本企業の活力を削ぎ、法人税収の大幅減少につながるものである。”
売上高は役員給与額との相関関係の弱い指標であるから、施行令にいう事業規模について、売上高を指標として類似法人を抽出するときは、絞り込みを極力緩やかにする基準を採用しなければならないところ、原判決は、売上高を指標とする抽出に際し、厳格な近似性を要求する倍半基準を採用している。原判決が採用する基準は、役員給与相当額の判定を歪めるものである。
しかも、施行令にいう事業規模が類似するとの文言は、社会通念に照らして事業規模が類似していることを意味すると考えられるから、その抽出基準は、社会通念上事業規模が類似していると考えられている法人を抽出できるものとなっていなければならないところ、売上高倍半基準では社会通念上事業規模が類似していると考えられている法人を抽出することができない。
以上のとおり、施行令にいう事業規模の類似する法人の抽出基準として売上高倍半基準を採用することは、旧法人税法施行令69条1号及び法人税法施行令70条1号イに反するものであるから、違法である。
“原判決は、施行令にいう事業規模が類似するものの抽出方法として、本件各更正処分と同様、売上高倍半基準を採用した。しかし、最近の研究では、売上高と役員給与額との間には何らの相関関係もないことが明らかになってきており、本件各事業年度である平成19年から平成22年の法人情報を統計分析しても、売上高と役員給与額との間には何らの相関関係も認められない。施行令にいう事業規模は、役員給与額と一定の相関関係に立つ項目として理解されなければならないから、売上高をもって事業規模を測るのは、上記施行令に反した解釈である。”
“しかも、施行令にいう事業規模が類似するとの文言は、社会通念に照らして事業規模が類似していることを意味すると考えられるから、その抽出基準は、社会通念上事業規模が類似していると考えられている法人を抽出できるものとなっていなければならないところ、売上高倍半基準では社会通念上事業規模が類似していると考えられている法人を抽出することができない。
“にもかかわらず原判決は、役員の経営能力を比較対象とすると判断が主観的・恣意的なものにならざるを得ないとして、これを比較検討せず、控訴人の個別事情も検討せず、類似法人の最高額を超える部分の存在を、安易に不相当に高額と判定する評価根拠事実としている。原判決のこのような判断は不合理である。”
原判決は、本件各事業年度中の控訴人の使用人に対する給与の支払状況に大きな変化がない事実と、本件役員ら給与に増額分が認められる事実を、本件役員ら給与が不相当に高額と判断するための評価根拠とした。
しかし、使用人給与額と役員給与額との間に何らの相関関係もないのであるから、使用人に対する給与の支払状況という要素の評価について、原判決の判断は誤っている。
“原判決は、本件各事業年度中の控訴人の使用人に対する給与の支払状況に大きな変化がない事実と、本件役員ら給与に増額分が認められる事実を、本件役員ら給与が不相当に高額と判断するための評価根拠とした。
国税庁の主張
追加主張無し
■国税庁
役員給与を増額させなければならないほどの特段の職務内容の追加があったとは認められないと主張。
比較法人の抽出にあたって、倍半基準を用いた上で、抽出法人の決算書等で、リキュール類など単式蒸留しょうちゅう以外の売上げが5%以上見込まれる事業年度、及び代表取締役に対する役員給与の額が前年に比較して3分の1以下となっている事業年度のような特殊性が高いと認められる事業年度を除外して、適正給与額を算定するべきと主張した。
総売上金額は法人の事業規模を示す最も重要な指標の一つであることから、総売上金額に着目した基準である倍半基準は、事業規模の類似する同業者を抽出するための基準として優れた合理性を有すると主張。
類似法人を抽出するに当たり、原告の製造する酒類のほとんどが単式蒸留しょうちゅうであることを踏まえて、単式蒸留しょうちゅうを製造する法人を抽出することに何ら不合理はないとした。
以上の基準で機械的に抽出したものであるから、いずれもその抽出に当たって恣意の介入する余地はないと主張した。
比較法人の平均値を算出することによって比較法人間に通常存在する諸要素の差異やその個々の特殊性が捨象され、より平準化された数値が得られるため、比較法人の役員報酬ないし役員給与の平均額を用いることとした。
使用人に対する給与の支給状況について、使用人は法人と雇用関係にあり、自らの労働の対価を決定する権限を持たないことから、使用人に対する給与の額については恣意性の入る余地が少ないと考えられるのに対し、法人の役員は、その給与の額のうちに、法人利益の分配と目される部分の金額が潜在する可能性があるのであるから、役員給与の相当性を判断する要素の一つとして、使用人に対する給与に照らして判断することは合理的であると主張した。
さらに、役員給与の相当性を判断するに当たり、高い経営能力を有する役員が必ずより多くの役員給与を受けるという原告の上記主張を前提とすれば、極めて主観的、恣意的なものとならざるを得ず、客観性を欠くこととなるから不合理であると否定した。
平成18年の改正により、法人税法34条は、役員給与が職務執行の対価として相当な範囲内か否かの基準を、従来の役員報酬に相当するものだけでなく、一定の条件のもとで損金に算入することを認めることとしたものであるとして、課税の公平性を確保する観点から、恣意性の排除を図るという、旧法人税法34条1項の基本的な考え方は、平成18年の改正後も継続していると指摘した。
類似法人の役員給与データは、財務省や国税庁がホームページ上で公表している「法人企業統計年報特集」、「民間給与実態統計調査」や税務関係の雑誌である「週刊税務通信」の掲載記事や、税務関係の書籍にも役員数や役員報酬の金額について参考となる資料が数多く掲載されているため、予測可能性が害されるとは言えないと主張した。
憲法14条1項は、国民に対し絶対的な平等を保障したものではなく、合理的理由なくして差別することを禁止する趣旨の規定であるから、各上場企業の役員給与に対し、更正処分を行っていないことは、事実上の差異に相応して法的取扱いを区分することは、何ら同条に違反するものではないと主張した。
なお、本件退職給与の額については、法人税法施行令70条2号に規定される、従事した期間、退職の事情、類似法人の退職給与の支給状況等に照らし「その退職した役員に対する退職給与として相当であると認められる金額」を具体的に判定するためには、功績倍率法(退職する役員の最終月額給与の額に、その役員のその内国法人の業務に従事していた年数及び功績倍率を乗じて算出する方法)が合理的であるとし、法人税法34条2項に規定する相当であると認められる金額を超える部分の金額があるとした。
■納税者
原告は、他の泡盛メーカーと比して、圧倒的に良好な成績を収めており、本件役員らは、各種製造機械及び製造ラインを自らの力で作ることができる特殊技術を有し、安く購入してきた中古機械により、原告の商品製造に最も適した機械・製造ラインを製作するということを行ってきており、これにより優良な収益構造をもたらしているのであり、役員給与が増額されたことは相当であると主張。
役員給与の額と使用人に対する給与の額とは、何ら比例関係に立つものではないから、使用人に対する給与の支給の状況を検討することは、失当であるとした。
優秀な経営者は、そうでない経営者よりも役員報酬が高くなるのであるから、本件役員ら給与が適正であるかを検討するに当たり他の法人の役員給与の額を用いる場合、かかる他の法人の役員は、本件役員らと同等以上の経営能力を持つ者となっていなければならないため、そのためには、客観性を担保できる程度の相当程度の数の法人を抽出する必要があり、同業種法人は全て漏れなく抽出されていなければならないと主張した。
売上高が2分の1から2倍の範囲に入る法人のみを抽出し、それ以外の法人は全て抽出しない被告が採用する倍半基準はふさわしくないと主張。
費用低減の重要性が認識される現代の経営において、役員の経営能力が、売上げが2倍を超える法人の経営能力と同等ないしそれ以上あるという例は多数存在するから、同業種法人は、日本全国から漏れなく抽出されなければならないし、単式蒸留しょうちゅう製造業のみならず、酒類製造業全部を抽出すべきであると主張した。
事業規模類似の同業種法人における役員給与の支給状況を用いなければ職務対価相当額が導かれないのであれば、納税者の予測可能性が害された違憲の課税であると主張した。法人における役員給与支給額を把握することは、現在不可能であり、課税庁から事業規模類似同業種法人の役員給与支給額が提示されても、法人名等の一切が秘匿されていることにより、その内容が正しいか、意図的に納税者側に有利な資料が除外されていないか、といったことを納税者側では一切検証することができない。原告において、その適法性を一切検証することが不能となっているから、本件各更正処分は、憲法31条に違反するとした。
倍半基準及び平均額法により、上場企業の役員給与について検討すると、自動車業界については、日産自動車の同業種類似法人として抽出されるトヨタ自動車及び本田技研工業等の役員給与と比較して、日産自動車の代表取締役であるカルロス・ゴーンの役員給与は、過大役員給与となるにも関わらず、上記各上場企業については、過大役員給与額に係る課税処分を行わず、原告に本件各更正処分をしたところ、合理的な理由を欠いた不平等な課税処分であるから、本件各更正処分は、憲法14条に違反すると主張した。
なお、本件退職給与については、零細泡盛製造業者にすぎなかった原告を、他の酒類製造企業と競争可能な泡盛製造の代表企業にまで押し上げ、酒類業界におけるその不動の地位を確立せしめるに至った乙は、経営者として、原告に多大な資本蓄積をもたらしてもおり、他にも先見性の高い経営判断を行ってきているから、不相当に高額であるとはいえないと主張した。
関連する条文
法人税法(平成18年法律第10号による改正前)
法人税法施行令(平成18年政令第125号による改正前)
法人税法
法人税法施行令
(参考)旧条文と現行条文
平成20年2月期から平成22年2月期までに適用される法人税法等
東京地裁/平成28年4月22日判決判決(舘内比佐志裁判長)/(一部取り消し)(原告控訴)
“旧法人税法34条1項は、内国法人がその役員に対して支給する報酬の額のうち不相当に高額な部分の金額として政令で定める金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない旨を定めている。この規定の趣旨は、役員報酬は役務の対価として企業会計上は損金の額に

“同改正後の法人税法34条は、内国法人がその役員に対して支給する給与について、同条1項において、定期同額給与、事前確定届出給与のうち一定のもの又は利益連動給与のうち一定のもののいずれにも該当しないものの額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しな
“そして、旧法人税法施行令69条は、旧法人税法34条1項の規定を受けて、「不相当に高額な部分の金額」を、同条1号又は2号のいずれか多い金額とし、同条1号において、役員に支給した報酬のうち、当該役員の職務の内容、当該法人の収益及び使用人に対する給料の支給の状況、当該法人と同種の事業を営む法人でその事業規模が類似するものの役員報酬の支給の状況等に照らし相当であると認められる金額を超える部分の金額と定め、法人税法施行令70条1号も、役員に対して支給した給与について同様に定めている。”
“そこで、以下においては、上記のような旧法人税法34条1項及び法人税法34条2項の趣旨を踏まえ、旧法人税法施行令69条及び法人税法施行令70条1号の規定に照らし、本件役員ら給与の額が、「不相当に高額な部分の金額」を含むものであるか否か及びその額について、検討することとする。”
“被告は、本件訴訟において、本件役員ら給与について、各比較法人における代表取締役及び取締役の受ける役員報酬ないし役員給与のうち、最高額のものを平均したものと対比して、これを超える部分が不相当に高額な部分の金額であると主張するが、処分行政庁は、本件役員ら給与のうち、各類似法人の代表取締役及び取締役の受ける役員報酬ないし役員給与のうち最高額のものを超える部分が不相当に高額であるとして本件各更正処分等をしていることを考慮し、以下においては、本件役員ら給与のうち、上記最高額を超える部分が不相当に高額な部分の金額であるか否かとの観点から、本件各更正処分等の適法性について検討する。”

“原告の業務の内容や規模等、本件役員らの職務の内容は、前記(2)アないしウに認定したとおりである。一般に、酒類の製造及び販売等を業とする法人の役員としては、①製造計画及び製造に係る指揮監督・意思決定等、②営業活動に係る指揮監督・意思決定等、③設備投資の計画・意思決定等、④従業員の採用・給与等の人事業務、⑤財務状況の把握及び分析、⑥法人業務全般の指揮監督、⑦法人を代表しての対外折衝などが考えられるところ、本件役員らの職務の内容も、上記①ないし⑦のような職務の内容に比して格別なものがあるということはできず、一般的に想定される範囲内のものであるというほかはないから、特別に高額な役員報酬ないし役員給与を支給すべきほどの職務の内容であるとまでは評価し難いというべきである。”
“原告は、①原告の収益の状況と本件役員ら給与の額の関係については、■■■■■■■■における本件役員ら給与が適正額の最高額であるとはいえず、むしろ、それまで原告の売上高や利益額の増加割合に比して、役員らの給与の額は大幅に抑えられていた、②原告の使用人に対する給料の支給の状況と本件役員ら給与の額の関係については、役員は経営判断を行うのに対し、使用人は経営判断を行わないから、何ら比例関係に立つものでなく、使用人兼務役員の場合でない限り、使用人に対する給与の支給の状況を検討すること自体が失当である旨主張する。”
“しかしながら、旧法人税法施行令69条1号及び法人税法施行令70条1号イは、不相当に高額な部分の金額の検討に当たり、その内国法人の収益及びその使用人に対する給料ないし給与の支払の状況を掲げており、使用人兼務役員の場合に限り使用人に対する給料ないし給与の支払の状況を検討すべきものとはしていないのであるから、これらの要素を検討することは、法令の規定に沿ったものであるということができるし、単にその内国法人の収益又はその使用人に対する給料ないし給与の支給の状況のみから、役員の職務に対する対価として相当であると認められる金額が決定されるのではなく、他に役員の職務の内容やその内国法人と同種の事業を営む法人でその事業規模が類似するものの役員に対する報酬ないし給与の支給の状況等に照らして、役員の職務に対する対価として相当であると認められる金額が決定されることからすれば、原告の主張は採用することができない。”
“沖縄国税事務所長は、類似法人を抽出するに当たり、沖縄国税事務所及び熊本国税局管内の単式蒸留しょうちゅうの製造免許(本免許)を付与された法人で、原告の本件各事業年度と半年以上事業期間を同じくする事業年度につき、総売上金額が、原告の本件各事業年度の総売上金額の0.5倍以上2倍以下の範囲内の範囲内(いわゆる倍半基準)の法人として延べ34法人を抽出した。旧法人税法施行令69条及び法人税法施行令70条1号は、不相当に高額な部分の金額の検討に当たり、その内国法人と同種の事業を営む法人でその事業規模が類似するものの役員に対する報酬ないし給与の支給の状況を考慮要素として掲げているところ、上記のとおり、沖縄国税事務所長が類似法人を抽出し、その代表取締役及び取締役それぞれのうちの最高額の役員報酬ないし役員給与を抽出した方法は、法令の文理に照らし、合理的であると評価することができる。”
“旧法人税法施行令69条及び法人税法施行令70条1号は、「事業規模が類似する」法人の役員に対する報酬ないし給与の支給の状況を、不相当に高額な部分の金額の判断の基準の一つとしていると
“原告は、比較法人となるべき法人の役員らの能力は、本件役員らの能力と同等以上でなくてはならないとの観点から、同等以上の能力を持つ役員らを擁する法人が比較法人として抽出されるべきであるのに、その売上金額が原告の売上金額の2倍以上であることから抽出されていないとして、倍半基準を用いることは不合理である旨主張する。しかしながら、原告の上記主張は、役員の経営能力それ自体を評価することが前提となっているものというべきであるが、主観的・恣意的な要素を排除して経営能力それ自体を評価することは極めて困難であり、このような評価を前提として類似法人を抽出することは客観性を欠いた抽出方法であるといわざるを得ない上、「事業規模が類似する」という法令の文言からも離れた抽出方法によることになるから、原告の上記主張は採用することができない。”

“本件役員ら給与の額は、類似法人の中で役員報酬ないし役員給与の最高額となっている7番又は29番をも上回るのであり、しかも上記2法人は、原告との比較においても、相当に経営状況がよいと評価することができる(前記ウ)ことからすれば、本件役員ら給与には、不相当に高額な部分の金額があるというべきであり、少なくとも、類似法人の代表取締役及び取締役らの役員報酬ないし役員給与の最高額を上回る部分は、不相当に高額な部分の金額に該当するというべきである。”
また、現行の法人税法34条1項に定められた定期同額給与及び事前確定届出給与についても、これらに該当すれば、期中において恣意的に役員給与を増額するものではないということはできても、必ずしも期初の段階で職務執行の対価としての相当性を超える役員給与を定めることが排除されるものではないから、これらに該当するということから直ちに職務執行の対価として相当性を有することとなるものとはいうことはできない。
以上のとおり法人税法34条2項は、旧法人税法34条1項と同様、課税の公平性を確保する観点から、職務執行の対価としての相当性を確保し、役員給与の金額決定の背後にある恣意性の排除を図るという考え方によるものと解されるのであって、その適用の余地がないといえないことは明らかである。
“原告は、平成18年法律第10号による改正前の法人税法35条において、役員賞与は損金の額に算入されない旨が規定されていたものの、役員賞与として支給すべきものを役員報酬名目で支給すると当該規定が骨抜きになってしまうことや、期中に恣意的に役員報酬を増額することにより納税額を軽減させることに対処するため、旧法人税法34条1項において、過大役員報酬の損金不算入が規定されていたところ、平成17年の会社法の成立に伴い、利益処分とされてきた役員賞与は費用として整理され、平成18年法律第10号により改正前の法人税法35条は削除されることとなり、隠れた賞与支給は観念することすらできなくなったのであること、また、同改正により、法人税法34条1項は、損金算入が認められる役員給与の支給方法を、定期同額給与又は事前確定届出給与という期初段階であらかじめ支給額を決定しなければならないものに限定し、これら以外の給与については損金に算入しないこととして、期中における恣意的な役員給与の支給も不可能になったことから、同項の規定の適用があるものを除き過大役員報酬の損金不算入を定める法人税法34条2項は、死文化し、納税者への適用は観念されないものとなった旨主張する。”
“法人税法21条は、内国法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の課税標準は、各事業年度の所得の金額とする旨を定め、同法22条1項は、内国法人の各事業年度の所得の金額は、当該事業年度の益金の額から当該事業年度の損金の額を控除した金額とする旨を定めた上、同条3項は、内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の損金の額に算入すべき金額は、別段の定めのあるものを除き、同項各号で掲げる金額とし、同条4項は、同条3項各号に掲げる額は、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従って計算されるものとする旨を定めている。”
“法人税法34条2項は、役員給与のうち不相当に高額な部分の金額については、損金の額に算入しない旨を定めているところ、その趣旨は、従前は利益処分として会計上処理されてきた役員賞与について、費用として処理されることとなったことをも踏まえて改正されたものであって、同法22条3項の規定における別段の定めとして、会計処理上は損金の額に算入するものを、内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しないものとしているものであり、その規定ぶりは、旧法人税法34条1項と同様のものである。”
“また、平成18年法律第10号による改正により法人税法34条1項に定められた定期同額給与及び事前確定届出給与についても、これらに該当すれば、期中において恣意的に役員給与を増額するものではないということはできても、必ずしも期初の段階で職務執行の対価としての相当性を超える役員
“以上のとおりの平成18年法律第10号による改正の内容や経緯等に鑑みれば、法人税法34条2項は、旧法人税法34条1項と同様、課税の公平性を確保する観点から、職務執行の対価としての相当性を確保し、役員給与の金額決定の背後にある恣意性の排除を図るという考え方によるものと解され
“憲法84条の規定からすれば、課税要件等に関わる租税法規は、できるだけ明確に定められることが求められるというべきであるが、他方において、納税者の実質に応じた課税の公平を確保することも求められることを考慮すると、原告の主張する納税者の予測可能性を含め、当該租税法規が憲法84条の規定に反しないか否かについては、当該法規の趣旨、目的とするところを合理的、客観的に解
“一般に、個々の法人における役員に対する報酬ないし給与の額について、「不相当に高額な部分の金額」の上限を確定的に定めることは、その性質上、極めて困難であり、かえって実質的な課税の公平を害するおそれが生ずることは明らかである。他方において、上記①「当該役員の職務の内容」、②「その内国法人の収益」、③「その使用人に対する給料の支給の状況」に基づき、職務対価相当額を求めた後、その相当性の補強の一環として、④事業規模類似の同業種法人における役員給与の支給状況のような考慮すべき事項をみると、上記①ないし③の事項については、納税者において把握している事項である。”
“そして、上記④の事項についても、一般に公表された統計等により、法人の規模や業務に応じた役員報酬ないし役員給与の傾向ないし概要を把握することは可能であることが認められるところ、このことからすれば、同事項についても入手可能な資料等から一定程度の予測は可能であるというべきであって、これらの各事項を前記に述べたような、旧法人税法34条1項及び法人税法34条2項の規定の趣旨に照らして考慮すれば、納税申告の時点において、「不相当に高額な部分の金額」について、必ずしも確定的な金額までは判明しないとしても相応の予測は可能であるというべきである。したがって、旧法人税法施行令69条及び法人税法施行令70条1号イの規定は、法律により委任された課税要件を規定したものとして一般的に是認し得る程度に具体的で客観的なものであるというべきである。”

しかし、行政手続に憲法31条による保障が及ぶと解すべき場合であっても、納税者において、課税処分に至る経過についてその根拠となった資料等を網羅的に逐一検証できなければならないことまでをも保障したものとは解されず、本件各更正処分等が憲法31条に違反するとはいえない。
憲法14条1項は、国民に対して絶対的な平等を保障したものではなく、合理的理由のない差別をすることを禁止したものであって、国民各自の事実上の差異に相応して法的取扱いを区別することは、その区別が合理性を有する限り、何ら同規定に違反するものではないし、旧法人税法施行令69条及び法人税法施行令70条1号は、旧法人税法34条1項及び法人税法34条2項に定める「不相当に高額な部分の金額」について、類似法人の役員報酬ないし役員給与の支給状況のみならず、当該役員の職務の内容、その内国法人の収益及びその使用人に対する給与の支給の状況も踏まえて判断することとしているのであって、前記に述べたところに照らし、これを踏まえてされた本件各更正処分等の判断に合理性があることは明らかである。
“原告は、本件各更正処分の過大役員給与の認定は、同種の事業を営む法人でその事業規模が類似するものの役員給与支給額を用いない限り、一義的に導くことが決してできず、原告においてその適法性を一切検証することができないから、憲法31条に違反する旨主張する。
“原告は、上場企業については、倍半基準により類似法人を選定すれば、過大役員給与となる場合があるのに、過大役員給与に係る課税処分を行わない一方で、原告に対して本件各更正処分をしたことは、憲法14条に違反する旨主張する。
“以上検討のとおり、本件役員ら給与には、不相当に高額な部分の金額があり、前記で認定した本件役員ら給与の額については、損金の額に算入することができないというべきである。”
“法人税法34条2項は、内国法人がその役員に対して支給する給与(前項の規定の適用があるものを除く。)の額のうち不相当に高額な部分の金額として政令で定める金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない旨を定め、これを受けて法人税法施行令70条2号は、法人税法34条2項に規定する政令で定める金額は、内国法人が各事業年度においてその退職した役員に対して支給した退職給与の額が、当該役員のその内国法人の業務に従事した期間、その退職の事情、その内国法人と同種の事業を営む法人でその事業規模が類似するものの役員に対する退職給与の支給の状況等に照らし、その退職した役員に対する退職給与として相当であると認められる金額を超える場合におけるその超える部分の金額とする旨を定める。”
“各比較法人の代表取締役に対する給与の額とは、いずれも大きく乖離したものとなっているといわざるを得ないが、各比較法人の役員給与について、平均額に比して高額であったり、低額であったりすることについて特殊事情があると認めるに足りる証拠はない。このような各比較法人がそれぞれ支払う代表取締役の給与のうちの最高額の分布及びその平均額等に鑑みると、その平均額については、比較法人間に通常存在する諸要素の差異やその個々の特殊性が捨象され、平準化された数値であると評価することは困難であるといわざるを得ないから、乙に対する役員給与については、その職務の内容等が、原告の経営や成長等に対する相応の貢献があったとはいえない程度のものであるなど、代表取締役として相応のものであるとはいえない特段の事情のない限り、比較法人の代表取締役に対する給与の最高額の平均額を超える部分をもって不相当に高額な部分の金額であるとすることはできないというべきである。そして、前記のとおり、各比較法人のうち代表取締役に対する給与額の最高額の高い上位2法人についてみると、その額(年額)は番号29が■■■■■■■■、番号7が■■■■■■■■であり、これら2法人について、不相当に高額な部分の金額の含まれる役員給与を支給しているということをうかがわせる事情は見当たらないことを考慮すると、上記最高額を超えない限りは不相当に高額な部分の金額があるとはいえないと解するのが相当である。”
“そこで本件において、乙の職務の内容等を検討すると、前提事実及び証拠によれば、乙は、昭和40年に高等学校を卒業すると同時に、原告の前身であるTで働くようになり、昭和60年に原告が設立された際に専務取締役に、平成6年に代表取締役に就任しているところ、Tで働き始めて以来、幅広い層に楽しまれる泡盛の開発を続け、それに成功するなどし、平成21年6月に代表取締役を退任するまで代表取締役を務め続けたこと、原告が、平成8年以降、売上高や経常利益を大きく伸ばすなどの成長をしたことが認められるところであり、これらの事情によれば、乙も原告の成長に際し、実質的にも相応の貢献をし、代表取締役の退任時まで原告の経営に貢献したものと評価することができる。”
“上記のとおり、本件においては、代表取締役に対する役員給与の最高額について、比較法人4法人のうち上位2法人と下位2法人との間に大きな乖離がみられ、しかも、その平均額についても各比較法人の代表取締役に対する役員給与の最高額との間に大きな乖離がみられるという状況であるところ、上記のような乙の原告における従前の職務の内容等に照らすと、原告の経営や成長等に対する相応の貢献があったというべきであって、その職務の内容等が代表取締役として相応のものであるとはいえない特段の事情があるとは認められないから、乙の代表取締役としての役員給与のうち、上記の平均額を超える部分が、不相当に高額な部分の金額であるとすることはできない。”
“そして、上記のとおり、比較法人の代表取締役に対する給与について、不相当に高額な部分の金額があるとはいえない本件においては、乙の役員給与が上記の最高額を超えない限りは、不相当に高額な部分の金額があるとはいえないと解すべきである。この点に関し、被告は、原告の代表取締役に対する適正給与の額は、各比較法人がそれぞれ支払う代表取締役の役員給与のうちの最高額の平均額を超えるものではなく、比較法人として抽出されたものから、適切な理由もなく除外するのは許されないと主張するが、本件で抽出された比較法人の代表取締役の役員給与の分布状況等や、乙の原告における職務の内容に照らして、上記のとおり、最高額を超えない限りは、不相当に高額な部分の金額があるとはいえないと判断をしたものであるから、被告の主張は採用することができない。”
東京高裁/平成29年2月23日判決(高野伸裁判長)/(棄却)(控訴人上告)
“控訴人は、売上高と役員給与額には相関関係がないから、施行令にいう事業規模の類似する法人を抽出する基準として、売上高倍半基準を採用するのは違法である旨主張する。
“また、倍半基準は、対象の中から近似性を有するものを抽出する基準として合理的であり、仮にこの基準に該当しないものの中にも類似性があると一般的に考えられているものが存在するとしても、そのことにより倍半基準が合理性を有しないことにはならない。”

“控訴人は、本件役員ら給与に不相当に高額な金額があるか否かの判断に際し、役員の能力は重要な比較検討要素であり、役員の能力を考慮しないとする原判決の判断は不当である旨主張し、経常利益率、自己資本比率、流動比率、総資本回転率、売上高成長率等の経営分析指標において控訴人は優位な数値を示しており、これらの個別事情を検討すれば、本件役員らに対する役員給与の支給額は不相当に高額であるとはいえないと主張する。”
“しかし、役員の経営能力を別個の判断要素として考慮することは、何をもって役員の能力と評価すべきかあいまいであり、主観的・恣意的要素を判断要素に加えることになるから相当ではない。また、控訴人の指摘する経営分析指標と個々の役員報酬額との関係について確立された一般的な理解があるとはうかがわれず、控訴人の経営分析に係る指標の数値は、類似法人の代表取締役又は取締役の役員報酬ないし役員給与の最高額を超える額を支給することが不相当であるとの前記認定判断を覆すに足りるものではない。したがって、控訴人の主張は採用することができない。”
“また、控訴人は、平成19年2月期の役員給与支給額は平成19年2月期の収益状況により増減させることはできないのであるから、平成19年2月期の収益状況悪化を根拠に平成19年2月期の本件役員ら給与が過大であるとすることは不当である旨主張する。
“控訴人は、本件役員ら給与に不相当に高額な金額があるか否かの判断に際し、使用人給与額の変遷を考慮要素として評価した原判決の判断は不合理である旨主張する。
“控訴人は、本件役員ら給与に不相当に高額な金額があるか否かの判断に際し、租税回避事案ではないことを不相当に高額であることの絶対的評価障害事実と解すべきであり、これと異なる原判決の判断は不当である旨主張する。しかし、旧法人税法施行令69条1号及び法人税法施行令70条1号イの解釈適用において、租税回避事案ではないことをもって役員給与が不相当に高額であるとはいえないとすべき根拠はなく、控訴人の解釈は独自のものであって採用することはできない。”
しかし、相応の予測は可能であること、旧法人税法施行令69条1号及び法人税法施行令70条1号イの規定は一般的に是認し得る程度に具体的で客観的なものであるというべきことは、原判決において説示するとおりである。
“控訴人は、控訴人が本件各事業年度の確定申告をする時点で、本件役員ら給与につき、不相当に高額な部分の金額を予測することは不可能であったので、本件各更正処分等は租税法律主義を定めた憲法84条に反し、取り消されるべきである旨主張する。
納税申告の時点において控訴人に不相当に高額な部分の金額について確定的な金額までは判明しないとしても、相応の予測は可能であること、旧法人税法施行令69条1号及び法人税法施行令70条1号イの規定は一般的に是認し得る程度に具体的で客観的なものであるというべきことは、原判決において説示するとおりである。控訴人は、本件各更正処分において沖縄税務署長が過大役員給与とはしなかった限度の本件役員ら給与額は、入手可能な資料等から予測しうる類似法人の役員給与額を大幅に上回るものであるから、控訴人において相応の予測が可能であったとはいえない旨主張するが、控訴人は、本件役員ら給与の額が予測し得る類似法人の役員給与額に比して大幅に高額であることを認識することができたと認められるから、本件役員ら給与につき不相当に高額な部分が存在することにつき相応の予測が不可能であったとはいえない。したがって、控訴人の主張は採用できない。”
最高裁/平成30年1月25日決定(木澤克之裁判長)/(棄却・上告不受理)(確定)

■東京地裁は、「最高額の平均」ではなく「最高額」を超える部分を不相当高額部分と判断。
■本件退職給与については、類似法人間で最高額の乖離が大きいことや、本件の代表取締役は法人に相当の貢献があったことから、類似法人の中の最高役員給与額を用いて算出した金額を超えない限りは不相当高額部分があるといえないと判断して課税庁の主張を認めなかった。(原告の主張が認められた)
■法人(原告)は主張が認められなかった部分について控訴したが、東京高裁は原審を維持し、「最高額」を超える部分を不相当高額部分と判断、棄却され、上告受理申立ては不受理決定で確定。
■東京地裁の判決要旨は以下である。
納税者の役員の職務内容は、製造計画及び製造に係る指揮監督・意思決定等、格別なものがあるとは思われないため、原告の売上げや利益の増加に貢献したとは評価し難いとした。
■旧法人税法施行令69条1号及び法人税法施行令70条1号イは、不相当に高額な部分の金額の検討に当たり、その内国法人の収益及びその使用人に対する給料ないし給与の支払の状況を掲げているのだから、これらの要素を検討することは、法令の規定に沿ったもので当然であるとした。
■国税庁が、沖縄国税事務所及び熊本国税局管内の単式蒸留しょうちゅうの製造免許(本免許)を付与された法人で、原告の本件各事業年度と半年以上事業期間を同じくする事業年度につき、総売上金額が、原告の本件各事業年度の総売上金額の0.5倍以上2倍以下の範囲内の範囲内(いわゆる倍半基準)の法人として延べ34法人を抽出した方法は、合理的であるとした。
■単式蒸留しょうちゅうについては、製造業における製造コストや設備費、人件費等は、地域によって異なるのが一般的であり、同一国税局管内や近接した国税局管内という比較的近接した地域においては、製造コスト等に類似性が認められるものが多いと考えられること等からすれば、類似法人の抽出範囲を沖縄国税事務所及び熊本国税局管内としたことも合理的であるとした。
■比較法人となるべき法人の役員らの能力は、本件役員らの能力と同等以上でなくてはならないとの観点から、同等以上の能力を持つ役員らを擁する法人が比較法人として抽出されるべきであるとの納税者の主張に対しては、そのような抽出方法は、主観的・恣意的に成らざるを得ないから、採用することができないとした。
■平成18年の法人税法改正によって法人税法34条2項の規定は死文化した、との納税者の主張に対し、現行の法人税法34条1項に定められた定期同額給与及び事前確定届出給与について、これらに該当すれば必ず期初の段階で不相当に高額な役員給与が排除されるものではないから、これらに該当するということから直ちに職務執行の対価として相当性を有するとは言えないとした。法人税法34条2項は、旧法人税法34条1項と同様、課税の公平性を確保する観点から、職務執行の対価としての相当性を確保し、役員給与の金額決定の背後にある恣意性の排除を図るという考え方によるものと解されるのであって、その適用の余地がないとはいえないとした。
■「不相当に高額な部分の金額」の上限を明文化し確定的に定めることは、その性質上、極めて困難で、かえって実質的な課税の公平を害するおそれが生ずるとした。一般に公表された統計等や入手可能な資料等から一定程度の予測は可能であって、「不相当に高額な部分の金額」について相応の予測は可能であるというべきであるとした。したがって、憲法84条や憲法31条に違反するものではないとした。
■以上から、本件役員ら給与について、少なくとも、類似法人の代表取締役及び取締役らの役員報酬ないし役員給与の最高額を上回る部分は、不相当に高額な部分の金額に該当するとした。
■なお、本件退職給与について、乙の原告における従前の職務の内容等に照らすと、原告の経営や成長等に対する相応の貢献があったというべきであるから、不相当に高額な部分はないとし、納税者の主張を認めた。
認定事実

■乙は、原告が設立された時に原告の取締役に就任し、平成6年10月25日、代表取締役に就任し、平成21年6月30日、代表取締役を辞任した。
■乙の長男である甲、乙の妻である丙及び乙の二男である丁は、いずれも平成15年1月20日、原告の取締役に就任し、甲は、平成21年6月29日、代表取締役に就任した(以下、乙、甲、丙及び丁を総称して「本件役員ら」という。)。
■原告は、本件各事業年度において、毎年3月1日から翌年2月末日までを事業年度としていた。
■本件各更正処分等
■すなわち、沖縄税務署長は、原告と類似する法人を抽出し、その代表取締役及び取締役の報酬ないし給与の額(個々の法人における最高額)のうち、代表取締役及び取締役についてそれぞれ最も高い額のものを選定したところ、本件役員ら給与のうち、選定した額を超える部分をもって、不相当に高額な部分の金額であるとした。
■また、沖縄税務署長は、原告と類似する法人を抽出し、その代表取締役の給与の額(個々の法人における最高額)のうち、最も高い額のものを選定したところ、本件退職給与のうち、選定した額(月額)に乙の勤続年数15年及び功績倍率3倍を乗じた金額を超える部分をもって、不相当に高額な部分の金額であるとした。
■審査請求
■訴えの提起
編集者コメント
税務における永遠のテーマ 過大な役員給与

■法人税法3大経費の1つである給与の事案、中でも、永遠のテーマである役員給与の損金算入である。
■役員給与の損金算入規制は,もともと我が国で,役員賞与を利益処分(利益として算定された中から支払うべきもの)としてきた経緯に由来する。役員賞与について,従来,商法上の利益処分案に係る承認決議(旧商283①)により支給される実務慣行が定着していたが,会社法では役員賞与は役員報酬と同様に職務遂行の対価として整理され,役員賞与についても「報酬等」に含まれることになり,その株主総会決議に基づいて支給されるとともに,利益処分案の承認による支給の規定自体がなくなった。
■そして,平成17年11 月29日付け企業会計基準委員会「役員賞与に関する会計基準」(企業会計基準第4号)において,役員賞与は,発生した会計期間の費用として処理することとされた。
■これらを機縁として,平成18年度税制改正が行われ,定期同額給与,事前確定届出給与,利益連動給与(平成29年度改正以後は業績連動給与)という基本3類型が定められ,これらに該当しない役員給与は全額損金不算入とされた。これまで損金算入が認められていなかった役員賞与や業績連動型の役員報酬について,一定の厳格な要件の下で損金算入を認める途が拓かれている。
■このような役員給与税制に対しては,「役員賞与=利益処分」を出発点とする損金算入制限に代わる,新たな考え方である「恣意性の排除」(支給額や支給時期について恣意的な操作のおそれが少ないと認められる役員給与を類型化し限定的に列挙し,それらに限って全額損金不算入の対象外とする考え方)による損金算入制限を採用したという評価がなされている。
■また,役員給与税制について,役員報酬は,他の経費と異なりお手盛り的な(恣意性のある)支給が懸念されるため,法人段階での損金算入を安易に認めることは課税の公平の観点から問題があること及び支給を受ける役員の側において給与所得控除部分が課税されないことから,法人・個人を通じた税負担軽減効果が高く,安易な損金算入を認めることによる弊害が大きいことなどをその趣旨とするという理解に基づいて,お手盛り防止については,会社法上株主総会の決議を要求することで対処しており(会社361),これに加えて法人税法において規制をすべきものかどうか、又、法人税法自体も,不相当に高額な役員報酬は損金算入しないという規制を平成18年度税制改正前から維持しており(法人税34②),その上に損金算入を基本3類型に限るのは過剰な規制ではないか等の疑問も提起されている。
■会社法とは目的が異なる法人税法から見て,会社法に用意されているお手盛り防止装置のみに規律を委ねることが妥当か,現在の防止装置は会社法の観点からも十分な内容であるかという点は議論の余地があろう。
■味噌等の製造、卸、販売等を目的とする内国法人である京醍醐味噌の役員報酬が、実績に見合わず不相当に高額であるとして損金算入が否認された京醍醐味噌事件が、東京地裁(令和5年3月23日判決)、東京高裁(令和6年1月18日判決)で棄却され、2024年5月現在、上告中である。ぜひこちらもチェックしてみて頂きたい。
重要概念/費用性否定説(利益処分説)
過大役員給与の損金性否認

■一般に,役員給与は職務執行の対価としての性質を有する。よって,法人税法22条3項2号の費用に該当し,損金の額に算入されるべきである。
■旧法人税法34条1項は、内国法人がその役員に対して支給する報酬の額のうち不相当に高額な部分の金額として政令で定める金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない旨を定めている。この規定の趣旨は、役員報酬は役務の対価として企業会計上は損金の額に算入されるべきものであるところ、法人によっては実際は賞与に当たるものを報酬の名目で役員に給付する傾向があるため、そのような隠れた利益処分に対処する必要があるとの観点から、役務の対価として一般に相当と認められる範囲の役員報酬に限り、必要経費として損金算入を認め、それを超える部分の金額については損金算入を認めないことによって、役員報酬を恣意的に決定することを排除し、実体に即した適正な課税を行うことにあると解される。
■そして、旧法人税法34条1項は、平成18年法律第10号により改正されているところ、同改正は、会社法制や会計制度において、従前は利益処分として会計処理されてきた役員賞与について、費用として会計処理されることとなるなど制度が変更されたことを機にされたものである。
■同改正後の法人税法34条は、内国法人がその役員に対して支給する給与について、同条1項において、定期同額給与、事前確定届出給与のうち一定のもの又は利益連動給与のうち一定のもののいずれにも該当しないものの額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しないものとし、同条2項において、同条1項の規定の適用があるものを除き、不相当に高額な部分の金額として政令で定める金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない旨を定めているところ、これも旧法人税法34条1項と同様に、課税の公平性を確保する観点から、職務執行の対価としての相当性を確保し、役員給与の金額決定の背後にある恣意性の排除を図るという考え方によるものとされる。
■そして、旧法人税法施行令69条は、旧法人税法34条1項の規定を受けて、「不相当に高額な部分の金額」を、同条1号又は2号のいずれか多い金額とし、同条1号において、役員に支給した報酬のうち、当該役員の職務の内容、当該法人の収益及び使用人に対する給料の支給の状況、当該法人と同種の事業を営む法人でその事業規模が類似するものの役員報酬の支給の状況等に照らし相当であると認められる金額を超える部分の金額と定め、法人税法施行令70条1号も、役員に対して支給した給与について同様に定めている。
■役員給与について,法人税法34条1項に,損金の額への算入に関する別段の定めが設けられたのは,役員給与は,同法22条3項2号に規定する費用の一種ではあるものの,法人と役員との関係に鑑みると,役員給与の額を無制限に損金の額に算入することとすれば,その支給額をほしいままに決定し,法人の所得の金額を殊更に少なくすることにより,法人税の課税を回避するなどの弊害が生ずるおそれがあり,課税の公平を害することとなることから,同号の費用のうち,上記のような弊害がないと考えられる同法34条1項各号に定めるものに限って損金の額への算入を認めることとする趣旨であるとされる(東京地裁判平成29年3月10日)。
現行の役員給与税制は会社法と法人税法の和解

■平成18年度改正前の過大役員給与の損金性否認の規定は,「損金不算入の役員賞与として支給すべきものを損金算入の役員報酬に化体したもの」が不相当に高額な役員報酬として損金不算入とする租税回避否認の個別規定として理解されていたが,同改正により,かかる租税回避の否認法理の趣旨目的は消失し,役員賞与を含む役員給与は職務執行の対価として損金性を許容することを前提として,不相当に高額な役員給与の額は,当該役員の職務執行の対価たる性格を有しない,いわば,「損金算入限度枠のない贈与的支出(寄附金)」ともいうべき性質の支出として損金不算入とする規定に変質したという見解もある。
■現行の役員給与税制は,費用性否定説のみならず,役員給与は,職務執行の対価としての性質が認められる限りにおいて,収益を稼得するための費用として損金に算入されるという原則論を基本としつつも,恣意性の排除や課税上の弊害防止を含む課税の公平の考慮,株主又は広くステークホルダーの目線において「企業価値を高める」というコーポレートガバナンスへの配慮(ないし会社法等への配慮)などをその背後にもち,かつ,執行の便宜等の考慮により,条文化に当たって形式基準等を採用していると解されるため,1 つの視座から単純に説明することは難しいという側面を有する。
■法人税法が,会社法の枠組みを利用して,会社法で求められているよりも厳しい開示を要求することについては,会社法上の規制や実務が緩やかであることを前提としてコーポレートガバナンスの観点から歓迎する見解がある。他方,経営の透明性の確保は,法人税法ではなく,金融商品取引法等の開示規制によるべきであって,法人税法の要請が開示内容に影響する逆基準性は,本末転倒であるという批判もある。
会社法と法人税法の規制の部分的融合を模索する道も考えられよう。
併せて読みたい/京醍醐味噌事件
過大な役員給与に3億8,500万円の追徴課税(東京高判令和6年1月18日判決・棄却・控訴人上告予定)
■京都市山科区に本店をおく味噌製造業者の同社役員に支給した役員給与が不当に高額であるとして否認された事案。
■同社社長と弟ほかに支払われた役員報酬22億7800万円余りのうち、約19億2700万円分を「不相当に高額」と指摘し、法人税約3億8,500万円の課税処分が行われた。
“乙は、平成27年11月までは原告の業務に従事しておらず、ベトナム新規事業に係るベトナムでの業務を全般的に担う予定であったが、月額2億5000万円の給与の支給を受けていた平成27年12月から平成28年3月までの間、ベトナムに赴任したことはなく、日本又は■■においてベトナム新規事業における工場の設計・工場設備の配置に関する検討やベトナムにおける課税の問題を合法的に回避するための方法の検討をしていたにすぎず、そのほか、ベトナム新規事業に貢献していた具体的内容を認めるに足りる証拠ないし事情は見当たらないのであって、また、実際にもベトナム新規事業による収益は生じていない。
仮に、原告の主張するように乙が有能な人材であったとしても、乙のベトナム赴任が具体化せず、ベトナム新規事業再開のめどが立っていない状況において月額2億5000万円もの給与の支給を決定し、それを見直しもしないまま4か月間にわたって続けるということは、企業の意思決定としておよそ合理的なものとはいい難い。”


